- ホーム
- > 和書
- > 教養
- > ノンフィクション
- > ノンフィクションその他
内容説明
不耕起移植栽培の普及と環境再生農業の提唱で2008年度吉川英治文化賞に輝いた著者が、市民と農家が共に楽しめる、地球と人と生きものに本当に優しい市民農園・村おこし構想を提言する。
目次
第1章 思い違いの農業
第2章 大冷害の教訓
第3章 生きものの偉大な力
第4章 田んぼの驚くべき浄水能力
第5章 コメつくりの技術開発物語
第6章 自然と折り合う農業
第7章 田んぼの市民農園制度を
著者等紹介
岩澤信夫[イワサワノブオ]
1932年、千葉県成田市生まれ。旧制成田中学(現・県立成田高校)卒業後、家業の農業に従事。70年代末からコメ作りの研究に没頭。冷害に強いイネ作り、不耕起栽培、成苗の手植えなどについて、試行錯誤しながら工夫と実験を積み重ねる。85年頃から不耕起移植栽培を全国の農家に提唱、農機具メーカーと専用田植機の開発も始める。93年、「日本不耕起栽培普及会」を設立、会長に。2002年、「自然耕塾」を開校(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
Aya Murakami
72
図書館本。wiki情報で自然農法の人として紹介されていて存在を知った著者。 微妙に反米ですが。米に限らず農業全体への熱量が伝わる本。水道の浄水法まで言及していました。 合鴨はおいしいですね。おいしさの裏には8月以降わざわざクズ米を与えて(それも合鴨出荷のころには尽きてしまう)肉質を維持するというのは初耳。他には野犬除けの電気柵(電力なんかもかかる!)もひつようなのだとか…。農家の苦労をまた一つかいまみた1冊でした。2023/02/19
ぱるる
39
大変面白かったです。お米作りのことが詳しくわかります。専門用語を使わずに素人にもわかりやすく書いて下さっています。20年の研究の末に編み出した冬期湛水不耕起栽培。耕さず肥料も農薬も使わない栽培方法。最近、冬でも水を溜めている田んぼをチラチラ見かけますがこれなんでしょうか。冬の間、水を溜めた田んぼにはイトミミズが繁殖して、その排泄物が雑草を抑制し肥料にもなってくれるという。田んぼの食物連鎖によりメダカや赤トンボ、カエルなど生き物が集まる田んぼ。早速試してみたいところですが冬は水路に水がないので難しそう。2022/12/15
ばんだねいっぺい
35
気が遠くなる時間をかけて、前進していく姿勢は、二宮尊徳先生の「小を積んで大を為す」そのものだなと思った。不耕起といっても、イトミミズや細菌や微生物の力と、苗そのものを強くしなくてはいけないのだなと知った。天動説の歴史的転換じゃないけれども、なかなか、慣行農法を変えるのは、難しそうだ。それにしても、合鴨農法ってこんなに大変なんだと驚いた。鳥たちが不耕起の田んぼを見分けるという話には興奮した。 2019/07/30
たまきら
23
ええっ!てかんじ。お米と言えばとても手をかけて…というイメージがあるので。ぜひ自分でやってみたい!と思える内容です。まずは実験してみたいな。2020/09/23
baboocon
19
著者の岩澤信夫さんは80歳近いご高齢にも関わらずなお精力的で、田んぼを耕さない「不耕起」という栽培方法を研究、提唱し、農薬も肥料も使わない安全なコメ作りを日本に広めようとしている。不耕起栽培でとれるコメは冷害にも強く収量も多く、味もよく、何より農薬も肥料も使わないので安全。また不耕起の田んぼには多様な生物が集まり、浄水能力もあるといい事ずくめ。しかしこの農法に限ったことではないが、革新的な手法が受け入れられるには障害も多い。特に日本の農業には硬直的な行政や農協の壁が。それでも誰かがやらなきゃいけないんだ。2010/12/28
-
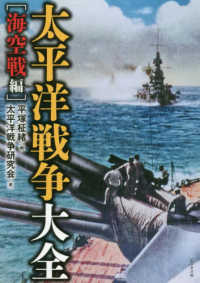
- 和書
- 太平洋戦争大全 海空戦編






