出版社内容情報
グローバリズムへの反乱は始まったばかりだ。「Gゼロ」「世界の10大リスク」で知られる論客が、これから何が起こるのかを見通す。この流れは、もう止められない!
地政学の第一人者が未来を読む!
ドナルド・トランプの登場、ブレグジットは始まりに過ぎなかった。
グローバリゼーションとその恩恵を受ける一部のエリートたちへの憤り。
移民に加え、デジタルとAIに仕事を奪われる中間層の不安。
開発独裁への回帰を望む新興国と、未成熟な政治体制に怒る途上国の市民
──怒りは、世界各地で渦巻いている。
米国や欧州で、中国、ロシア、トルコ、イラン、ブラジル、サウジアラビア……
イアン・ブレマーは格差がさらに広がり、深刻な対立が次々に起こると予測する。
いつ、どこで、どのようなシナリオで起こるのか。地政学の第一人者が、丹念に読み解く。
序 章
第1章 「勝ち組」と「負け組」
第2章 危険信号
第3章 12の断層線
第4章 分断の壁
第5章 ニュー・ディール
結 論
イアン・ブレマー[イアンブレマー]
著・文・その他
奥村 準[オクムラジュン]
翻訳
内容説明
エリート層への怒り。ポピュリズム政党の台頭。仕事を奪うテクノロジーへの不安…数々の「対立」を、世界は克服できるのか。第一人者が未来を読み解く!
目次
第1章 「勝ち組」と「負け組」(破綻するグローバリズム;世界中に波及する「怒り」 ほか)
第2章 危険信号(歴史を塗り替えた「怒り」;成功の被害者たち ほか)
第3章 12の断層線(南アフリカ―若年層に溜まる不満;ナイジェリア―人口の60%が貧困に苦しむ ほか)
第4章 分断の壁(イスラエルの「防護壁」;1930年代・アメリカの教訓 ほか)
第5章 ニュー・ディール(共有される1つの価値観;社会契約という思想 ほか)
著者等紹介
ブレマー,イアン[ブレマー,イアン] [Bremmer,Ian]
ユーラシア・グループ社長。スタンフォード大学にて博士号(旧ソ連研究)、フーバー研究所のナショナル・フェローに最年少25歳で就任。コロンビア大学、東西研究所(East West Institute)、ローレンス・リバモア国立研究所を経て、ニューヨーク大学で教鞭をとるほか、ワールド・ポリシー研究所の上級研究員も務める。2007年には、世界経済フォーラム(ダボス会議)の「ヤング・グローバル・リーダー」に選出される。1998年、28歳で調査研究・コンサルティング会社、ユーラシア・グループをニューヨークに設立
奥村準[オクムラジュン]
武蔵野大学国際総合研究所(MIGA)客員研究員。1950年岐阜市生まれ。1976年東京大学法学部を卒業、通商産業省(現在の経済産業省)に入省。国際関係の業務を中心に、在ブラジル大使館勤務などを経て、JETROニューヨーク・センターの所長。2001年の9.11同時多発テロの際には、日系企業への対応などに当たる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
あすなろ@no book, no life.
TATA
白玉あずき
風に吹かれて
鮫島英一



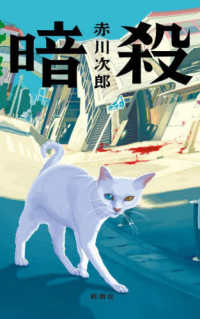

![FABLES DE LA FONTAINE [EN AZULEJOS] DU MONASTERE DE SAINT-VI (GRAND FORMAT)](../images/goods/../parts/goods-list/no-phooto.jpg)



