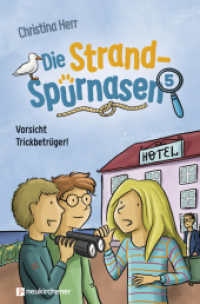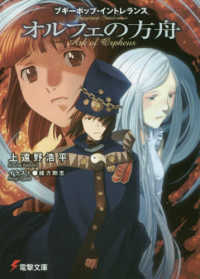内容説明
「どんな政策か?」から導入の効果、疑問や反論に対する回答までコンパクトにまとめた、注目テーマ理解のための決定版。
目次
1 インフレ目標政策とは何か(金融政策の新しい枠組み;インフレ目標政策の具体策;海外先進国ではスタンダードな政策 ほか)
2 デフレ・スパイラルとインフレ目標政策(日本が陥ったデフレの罠;デフレ・スパイラル;お金を借りている人が不当に損をすることを防ぐ ほか)
3 インフレ目標政策導入の論点(インフレを起こすことはできるのか;逆にインフレを止められなくなるのではないか;金融政策にできることには限界がある ほか)
著者等紹介
伊藤隆敏[イトウタカトシ]
東京大学大学院経済学研究科教授兼公共政策大学院院長。1950年生まれ。73年一橋大学経済学部卒業、79年ハーバード大学経済学博士(Ph.D.取得)、同年ミネソタ大学経済学部助教授、86年同准教授(テニュア付き)、88年一橋大学助教授、91年同教授、2002年より東京大学教授。公職等:1994‐97年IMF調査局上級審議役。1999‐01年大蔵省副財務官(大臣官房参事官)。2005‐現在関税・外国為替等審議会委員。2006‐08年経済財政諮問会議民間議員。2011年紫綬褒章受章(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
6
2001年初出。業績良い企業賃金4%↑、悪い企業賃金0%(不変)の平均2%上昇の方が、業績良い2%↑、悪い2%↓の平均0%よりもうまくいくという(31頁)。賃金の下方硬直性の問題。賃下げがよくない。スタグフレーションは日頃から懸念している者の一人だが、金利下げて景気刺激の裁量的金融政策は効果なく、高インフレ率と失業率が同時進行(59頁)。2013/11/09
Kenji Ogawa
1
異次元緩和の効果が出ていないようなので、再度考え方のチェック。やってみなくてはわからない的なニュアンスが書かれている事実。2015/10/14
yuno
1
インフレ・ターゲットの理論的背景を平易に解説した本。よく整理されていて、インタゲ政策は正しいような気もしてくるのだけど、過度なインフレは制御できる、という部分の根拠づけに経済学的な精彩を欠くように感じた(日銀はインフレを制御するのには長けているから、とか…)。この点はもっとも重要なことだと考えているので、インタゲ論者への転向、ということにはならなかったが、インタゲ論者が何を考えているのか、ということを知るためにはとても勉強になった。2014/12/30
Kenji Ogawa
1
長期金利上昇リスクは財政規律にありと、あらゆる他のリスクには言及がない。概ね賛成だけど2013/05/23
void
1
【★★★★☆】エッセンスは最終章のQ&Aだけでも充分。中央銀行がインフレ率2%を目標に物価安定化を図るというインフレ目標政策。なぜ2%か(公表されるのは1%ほど高めの数値、デフレの悪影響を重く見て「のりしろ」を作る)といった理論から始めて、各国の状況は、日銀法上の制約や「手段の」独立性をいかに確保するか、政府・財政政策との関わりは、などやや制度まで踏み込み門外漢にもさほど苦しくないレベルで説明する。効果があるだろうという道筋は示すものの、「どれだけ」効果があるのかという実証面は弱い。2013/04/24