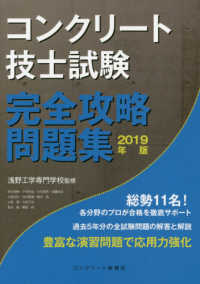出版社内容情報
ハゲタカか?救世主か?なぜ彼らは企業価値向上を実現できるのか?名門外資系ファンドの日本法人を務めた第一人者が本音で語る。*ソフトバンクが3.3兆円で英アーム社を買収するなど、いま空前のM&Aブーム。でもにわか仕立ての日本勢の多くはM&Aで大やけどを負ってきた。外資系のM&Aファンドはどのような企業価値向上策を実行しているかを本書では紹介する。
*外資系ファンドによる買収というと「ハゲタカ」など負のイメージが強いが、企業の生産性を見直し、グローバルな視点で事業を見直す絶好の機会であることを説得的に解説。
*一口にM&Aといっても、ファンド系と事業会社系で目的や手法が大きく違い、買収する会社も違ってくることなどを説明。また、ファンド、投資銀行、コンサルタントなどが案件を巡って、実際にどのように行動し、協力・競争をするのか、現場を知る著者ならではの解説をする。
*「事業提携はまず出資が前提」「中期経営計画の発想はなく、短期目標を基点とした事業戦略」など外資系の行動特性を紹介する。
*著者は名門大型ファンドとして世界的に有名なペルミラの日本法人社長を務め、回転寿司スシローや農薬商社アリスタといった巨額M&Aを成功させた第一人者。
第1章 日本買いM&Aの現状??鎖国から開国へ
第2章 日本買いM&Aの大原則??案件のスカウトから、育成、市場デビューまで
第3章 日本買いM&Aの関係者??チーム構成が勝敗を決する
第4章 日本買いM&Aの実際??外資の経営力取り込み実例
第5章 日本買いM&Aの功罪??「ハゲタカ」外資という誤解
第6章 まとめ??日本買いM&Aで外資経営資源の徹底的利用を
加藤 有治[カトウユウジ]
イースト・インベストメント・キャピタル代表取締役
京都大学理学部、経済学部卒業、1990年総務省入省。OECD出向、エール大学MBAを経て、1998年モルガンスタンレー証券(東京)入社。以降、一貫してM&A業務に従事。メリルリンチ(ロンドン)、GE日本シニアディレクター、ペルミラ日本支社代表などを経て、2014年より現職。
内容説明
総投資額3300億円。名門外資系ファンド元日本代表が明かす、駆け引きと価値創出の実態。
目次
第1章 日本買いM&Aの現状―鎖国から開国へ
第2章 日本買いM&Aの大原則―案件のスカウトから、育成、市場デビューまで
第3章 日本買いM&Aの関係者―チーム構成が勝敗を決する
第4章 日本買いM&Aの実際―外資の経営力取り込み実例
第5章 日本買いM&Aの功罪―「ハゲタカ」外資という誤解
第6章 まとめ―日本買いM&Aで外資経営資源の徹底的利用を
著者等紹介
加藤有治[カトウユウジ]
1966年島根県松江市生まれ、岐阜県育ち。1988年京都大学理学部卒業、1990年経済学部卒業。1990年郵政省(現総務省)入省、OECD(経済協力開発機構、パリ)に出向。1998年米国イェール大学経営大学院修了。1998年以降、モルガン・スタンレー、メリルリンチ(ロンドン)を経て、GEヘルスケア事業開発アジア責任者、直近はペルミラ・アドバイザーズ日本法人社長として、15年間にわたり対日企業投資に携わった。2014年以降、独立系投資会社であるイースト・インベストメント・キャピタル株式会社(EIC)代表取締役として、引き続き企業投資活動に取り組んでいる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Emkay
き
スプリント
Takuya Ikeda
山田
-

- 和書
- ローマ人への手紙