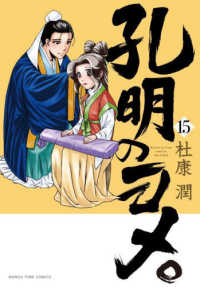内容説明
株主代表訴訟制度改革、過剰な内部統制システム、持ち合い解消への圧力、子会社上場規制、悪しき利益志向経営―。競争力を奪った制度改革を一刀両断。日本企業の強みを取り戻す再生策を提示。
目次
第1章 株式会社とその統治―変遷と多様性(企業統治の概念と二つの企業観;株式会社制度の成立と多様性 ほか)
第2章 企業統治改革の失敗(日本企業の迷走―三つの兆候;悪夢の始まり―株主代表訴訟制度の改革 ほか)
第3章 よりよい企業統治の制度と慣行をつくる(投資家資本主義といかに付き合うか;競争力の源泉としての企業統治制度 ほか)
第4章 長期連帯株主を求めて(よい株主の条件;連帯株主としての従業員 ほか)
著者等紹介
加護野忠男[カゴノタダオ]
1947年大阪府に生まれる。1970年神戸大学経営学部卒業。神戸大学大学院経営学研究科教授を経て現在、甲南大学特別客員教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
miyatatsu
8
加護野忠男先生の評判を聞いて、やっと本書を読むことができました。確かに経営学の世界で有名になるだけあって、普通とは異なる面白い着眼点でした。2018/05/17
ozapin
2
これ予想以上にいい本だった。北野一さんが紹介していてほかの本はあまり残らなかったが、この本は良い。年功序列制度による若年層への安月給と高齢層の高月給は従業員の見えざる投資である点や、株主を選ぶことの重要性がうまくかかれている。内部統制制度、四半期決算など制度は基本的には改悪されてきてしまったと筆者にはうつっており米国追随型でなく欧州追随型の資本主義を目指すべきと語る。種類株にも賛同していたり日本にしか残れなかったチタン業界の事例などから、日本が持ってきた資本主義社会の特性うまくいかすべきと語る。2014/10/19
ミッキー
2
長期連帯による人的資産の先行投資。企業特殊スキルと捉えるだけでなく、前向きに考えるのは参考になりました。継続的なイノベーションしか生まれないから、多機能にして値下げ競争にはまるのかとか、考えが刺激されました。ガバナンスが競争力を決めるという考えも参考になりました。2014/06/14
koji
2
冒頭で、著者は岳父の占部都美教授から「企業支配(企業統治)から、「この問題は年を取ってから取り組め」と言われたというエピソードが紹介されます。それに応えるように、著者が企業支配に悪戦苦闘するさまが描かれ、岳父の寿命を超えた所で漸く本書を纏められたと書いています。そういう意味で、加護野先生より一回り下の私には、まだ青臭さがあるのか、十分に咀嚼できたとは言えません。しかし、長期連帯株主、見えざる出資等論点は面白く、またドイツ経営学は確り勉強したくなりました。出版社には、著者と会社法/法学者の対話を望みます。2014/04/22
templecity
1
◎欧米型の経営とライン川型の経営では、後者の方が有利。企業は全てのステークホルダーのため。日本では株主の事を考える割合が少ない。株主代表訴訟要件の引き下げや、SOX法の導入、四半期決算の導入、時価会計制度の導入は日本の企業を弱くした。プラザ合意も日本企業を弱めるのが狙い。SOX法など導入しなくても内部の監視で十分不正は防げていた。悪いことをしない仕組みよりも良いことをする仕組みの方が大切。日本企業はコンプライアンスなどを気にするあまり、挑戦しなくなった。年功序列も会社への忠誠心を高める上で有効な方法であっ2014/06/14
-
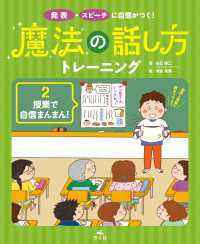
- 電子書籍
- 発表・スピーチに自信がつく! 魔法の話…
-
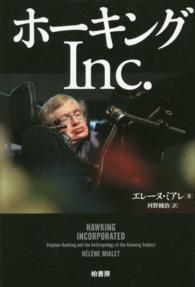
- 和書
- ホーキングInc.