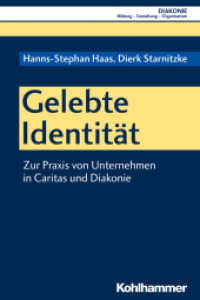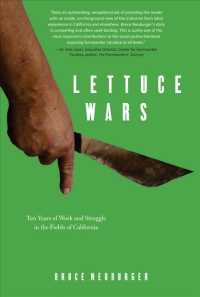出版社内容情報
●問題文が読めない子どもたち
新井紀子教授の『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』によると、中学生の約5割が教科書の内容を読み取れないということだが、著者の周りでも困った学生が増えている。
まず、心理検査やアンケート調査が正確に行えない。質問文の意味がわからないのだ。「内向的って何ですか?」「引っ込み思案って何ですか?」という質問が普通に出てくる。学生たちと話すと、「そんな言葉は日常会話やSNSでは使わないから」ということだそうだ。
読書時間ゼロの学生がいまや50%を超えた。半分の学生は本当にまったく本を読まない。一方で、文科省はアクティブ・ラーニングの方向に舵を切り、プレゼン、対話型の授業を増やしている。ただ、対話と言ってもお互い何も話さずじっとしていたり、プレゼンも自分の持ち時間を使い切れずに終わるなど、悲しい事例がそこかしこにあるようだ。
人間は言葉でものを考えるわけだから、言葉を自分の中に取り込むきっかけとなる読書をしないのは、思考力を身につけるという点においては大きなハンディだ。脳科学の研究データからも、読書習慣は神経繊維の発達や言語性知能の向上と関係していることがわかっている。
本書は、伝えたいことがうまく伝えれない、その原因として、読書量の危機的な減少をあげ、子ども時代にしておくべきことについて語る。
●子どものトラブル増加も「通じない」にある
小学生の暴力件数が高校生のそれを超えたというのは『伸びる子どもは○○がすごい』にも書いたが、自分の状況がうまく言葉で伝えられない、また相手の言葉が理解できないというのであれば、お互いにイライラが生じ、トラブルが生じるのも当たり前だ。一方、読書によって相手の心を能動的に理解でき、心の落ち着きにも効果があるという研究もある。
プレゼンのようなアウトプットが求められる時代だが、それも豊かなインプットがあってこそ。読書環境を作るのは一朝一夕にできるものではない。所蔵する本が多い家は自然と本を読む子どもになるという。親自身の言語能力が子どもにとっての言語環境になる。親と子どもがそろって習慣を身につけることがいま求められる。
内容説明
テストの問題文が理解できない子どもたち。意思疎通がうまくできずに、増える暴力事件。ディスカッション型の学習をしても、発言する内容はお寒いばかり…。読書の効用は語彙力や読解力にとどまらない。子どもが豊かな人生を送るために、いま親としてできることとは何かを説く。
目次
第1章 読解力の危機とは?(国際比較調査の問題からわかる読解力の危機;今の中高生の読解力 ほか)
第2章 言語能力はどうやって身につくのか?(話し始める前の言語発達;語彙の増加 ほか)
第3章 読書はほんとうに効果があるのか?(子どもの読書量と知的発達;読書が語彙力や読解力につながる ほか)
第4章 なぜ読解力が身につかないのか?(小学1年生から読書傾向の二極化が始まる?;中高生の読書傾向 ほか)
第5章 家庭の言語環境を整える(いつ頃から本を読むようになるのか?;「本を読みなさい」では読む気になれない ほか)
著者等紹介
榎本博明[エノモトヒロアキ]
心理学博士。1955年東京生まれ。東京大学教育心理学科卒。東芝市場調査課勤務の後、東京都立大学大学院心理学専攻博士課程中退。川村短期大学講師、カリフォルニア大学客員研究員、大阪大学大学院助教授等を経て、現在MP人間科学研究所代表(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
chiaki
future4227
十川×三(とがわばつぞう)
たまきら
のっち