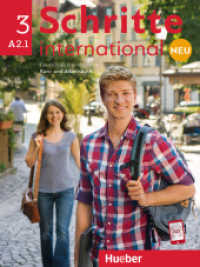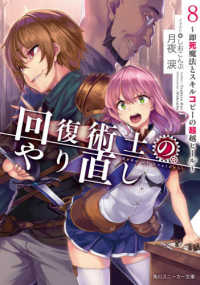内容説明
文学、社会学、哲学、宗教、科学史…幅広いジャンルの本を読んでいくと、あるときふと、点と点がつながって、一つのテーマが浮かび、形になる。ブローデル『地中海』、シュミット『政治神学』からピケティ『21世紀の資本』まで、「資本主義の終焉」を唱える著者が、53冊の書評から、グローバル資本主義の命運を占う。
目次
第1章 超長期で考える―17世紀の利子率革命vs.21世紀の利子率革命
第2章 資本主義はいかにして生まれたか―13世紀の資本論vs.21世紀の資本
第3章 中世の終わり近代の萌芽―コペルニクス革命vs.ニクソン・ショック
第4章 日本の近現代を問う―新中世主義vs.技術進歩教
第5章 帝国とは何だろうか―帝国vs.覇権国
第6章 資本主義とグローバリゼーションの限界点―「蒐集する人」vs.「される人」
著者等紹介
水野和夫[ミズノカズオ]
日本大学国際関係学部教授。1953年愛知県生まれ。77年早稲田大学政治経済学部卒業。80年同大学大学院経済学研究科修士課程修了。同年八千代証券(国際証券、三菱証券を経て現三菱UFJ証券)入社。98年金融市場調査部長、99年チーフエコノミスト、2000年執行役員、02年理事・リサーチ本部チーフエコノミスト、05年より三菱UFJ証券チーフエコノミスト。10年、内閣府官房審議官を経て13年より現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
さきん
24
著者のカールシュミット推しなのは随所で感じる。カールシュミット推しなのにナショナリズムへの考察が物足りないどころかグローバリズムへの対抗軸にナショナリズムが立つことを警戒しているように感じる。なので、富国強兵的な政策である国土強靭化計画や財政出動に対しては批判的である。どちらかというとブータンの幸福度みたいな尺度で世の中を考えるように訴えているので、自分としては、そういう尺度はあるに越したことはないにしても現実性に乏しく、0成長が当たり前になっても、成長への志向まで折る必要はないと感じる。2021/02/13
浅香山三郎
6
水野さんの本は、3冊目。資本主義が前提としてきた、成長や投資による富の増大といふ神話は崩壊した。これまでとは局面が変わつたのに、古い前提で金融緩和を続けるアベノミクスには、何ら効果がないといふ指摘はその通り。様々な、主に世界経済史の本を紹介しながら、或いはその論旨の要約といふ形態を取りながら、水野さんの年来の持論に絡めて、日本の資本主義社会の限界を説く。書評の大半は、日本経済の動態を毎日伝へ続けるはずの『日本経済新聞』に掲載された。読者たちは、どんな面持ちで日曜に水野さんの文章を読んでゐたのだらう。2016/06/26
肉尊
5
資本主義の歩みを時代を追いながら、著者の推薦書レビューをもとに解き明かしていく一冊。「より遠くへ、より速く」を実践した者が巨万の富を獲得できる近代のシステムはパナマ文書に見られるような、不正によって富を得るしかないという状態を見る限り、崩壊してしまったのではないかと著者は分析しています。シュミットの話が随所に盛り込まれているので、次読むならシュミット!って後押ししてくれているような気がしました。2017/08/20
nizimasu
3
水野和夫さんの「利子率革命」という歴史観には圧倒的な説得力があるんだけれどその背景には膨大な読書と検証の手続きがあったというのはこの本をよむとつくづくわかる。それにしても菟集という人間の欲望が海への航海に繋がりそれが利息の発生だったりそしてフロンティアとしての金融空間からサーバースペースへの広がりと帝国主義的な大国の思惑などは水野さんの史観を通してみると実にありありと見えてくるのだから不思議だ。あの柔らかい表情から垣間見える冷徹な人間の征服欲からの転換が求められるのは行き詰まっている資本主義の帰結なのかも2016/03/30
コーヒー豆
2
資本主義がどのような歴史的背景で成り立ち、今はどのような考えが主流になっているのかを、著者の本棚から数冊とりあげ、解説するスタイル。最初は「」が多くて読みにくいのかなと思っていたが、ただ単に自分の知識のなさによる読みにくさだった。勉強の必要性を強く感じるとともに自分の知識のなさを恥じた。紹介されている本を読んでみないことには著者の考えに共感できるか否かわからないので、実際に読んでみたい。その後に再読し、検討を重ねたい。勉強の毎日だ。2016/03/11
-

- 電子書籍
- 機動戦士ガンダムさん【分冊版】 202…
-

- 和書
- 海がみえるよ,ペルー!