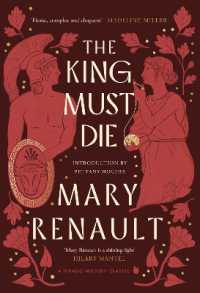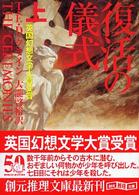内容説明
「過去に起きた津波は必ずまた起きる」。地層は、津波や地震、噴火など、地球上の過去46億年の変動の爪痕が残されている。地層からの“警告”を見逃さず、日本列島で将来起こる可能性のある災害の姿を地質学から読み解く。
目次
第1章 巨大津波は繰り返す
第2章 地層は知っている―過去の巨大津波
第3章 東日本大震災から学び続ける
第4章 地層が描き出す日本の津波災害地図
第5章 石垣島を襲った大津波を読み解く
第6章 世界中に残る巨大津波の爪跡
第7章 「地層からの警告」を見逃すな
著者等紹介
後藤和久[ゴトウカズヒサ]
1977年生まれ。東北大学災害科学国際研究所准教授。東北大学大学院工学研究科附属災害制御研究センター助教、千葉工業大学惑星探査研究センター上席研究員を経て現職。専門は地質学、とくに先史・歴史時代の津波現象、地球外天体衝突と生物絶滅、原生代初期のスノーボールアース現象、火星の地質研究など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
海燕
8
著者は地質学を専門とする研究者で、地層を調べることで過去の津波の履歴や規模を明らかにしようとする。869年の貞観地震による津波が東北地方を襲ったことは有名で、2011年の地震の津波とよく似ていると言われる。何しろ地震発生の間隔は数百年とかそれ以上だから、有史では各地それぞれ数えるほどしか記録がなかったりする。もの言わぬ地層だが大きな手がかりを与えてくれる。著者が述べるように、過去に起きたことは将来にも起こるし、津波は地震以外の要因(海底火山の噴火、地滑りなど)によっても発生する。自然現象はあまりに深遠だ。2023/05/27
葉
1
東日本大震災や石垣島を襲った大津波を地層から学ぶことで将来の減災に繋がる研究を理解できるのではないかと思っている。巨大地震の発生頻度の規則性や過去の津波を知る手段などについて過去の経験から学び、津波の研究でもわかることとわからないことについてコラムなどに書かれている。世界からみると、1960年のチリ地震、1700年のカスケード地震、2004年のスマトラ島地震、1883年のクラカタウ火山噴火などが図によって示されている。東北の三陸ではこれからも注意が必要としている。住まないことも一つの案かもしれない。2014/10/27
N.Y.
1
専門書っぽい匂いもあるけど、素人でも読めると思う。ちょっと津波堆積物に偏ってる感は否めないが。隕石と彗星の対比はNG。地球の外に居る時が小惑星か彗星で、落ちたらどっちも隕石。2014/09/19
かっち
1
東日本大震災のような数百年に一度の長い周期で発生する巨大地震の記録は、世界的に見ても文書等に残るものは少ない。これを読み解く有力な手段が地層研究である。筆者のような研究者が二度と想定外を作らないという必死の思いで明らかにした成果を、一般の人々への教育に落とし込むことが最も重要であろう。2014/08/28
こばこ
0
八重山の話が気になっていたので、早速読んだ。 東日本大震災のころから、よく聞こえ出した地層からの津波痕跡の話の、最新の話が出ていた。八重山には2000年前にも大きな津波の痕跡が有り、その時期と同じくして文明の痕跡がとだえると言う話が興味深かった。明和の大津波のときも人口が戻るのに100年かかったというので、さもありなん、というところで。そして今回の津波でも同じようなことが起こるのだろうと思うと「…」となるところで。2014/06/01
-
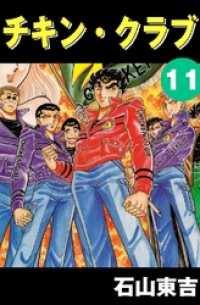
- 電子書籍
- チキン・クラブ -CHICKEN CL…