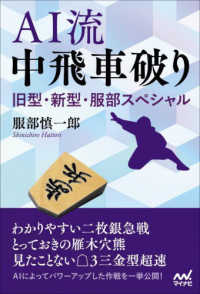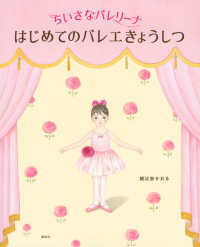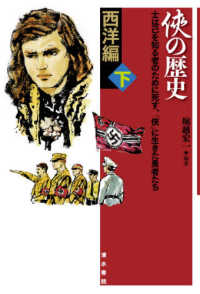内容説明
流行の健康法や食事療法には、残念なもの、危険なものも…。ダマされないために、人体の基本を勉強しましょう。人間と「栄養」の関係をユーモラスに解説し、「肉を食べる意味」「糖質制限食のリスク」「サプリの効果」など、具体的ケースを考えるユニークな一冊です。
目次
第1章 変装する栄養、怪しげな食事の話
第2章 無理して食べなくていいものがある
第3章 胃腸を知らなければ、何も理解できない
第4章 糖質制限は体にいいのか
第5章 それでも脂質を嫌いますか
第6章 なぜ人間は肉を食べるのか―肝腎要のタンパク質
第7章 微量栄養素は、サプリと名を変え大人気
第8章 「これを食べろ、食べるな」は本当か
著者等紹介
林洋[ハヤシヒロシ]
東京有明医療大学学長補佐、同大学院看護学研究科教授。1953年生まれ。78年東京医科歯科大学医学部卒業。米ルイジアナ州立大学医学部研究員、横浜市立みなと赤十字病院第二内科部長、国際医療福祉大学熱海病院内科教授などを経て、2009年より現職。医学博士(東京医科歯科大学)
重松洋[シゲマツヒロシ]
佐藤医院院長。1942年生まれ。67年慶應義塾大学医学部卒業。翌年、同大学医学部付属病院内科入居。81年同大学医学部内科及び保健管理センター兼担講師。87年開業。医学博士(慶應義塾大学)。老年病専門医、内科認定医、臨床栄養指導医(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kenitirokikuti
6
「はじめに」によると、〈本書は、一般の方々を対象にした、栄養の教科書ないし参考書、あるいはアンチョコ〉。私は高血糖になったので糖の代謝については身を入れて学習したが、脂質の代謝についてはおろそかであった▲えーと、リポ蛋白は血液中を通って中性脂肪を脂肪細胞に渡す。その際にリポ蛋白はコレステロールも伴っており、脂肪の運搬が多すぎるとコレステロールが血中に捨てられる量も増す。これが動脈硬化の原因。なお血中コレステロールを肝臓に戻すリポ蛋白もあるため、単なる血中コレステロール総量だけでは良し悪しは不明。2022/01/02
福島雄一
2
栄養の摂取、消化、その働きがそれぞれどのように人体の関わるのかについては非常に分かりやすく俗流健康本の多い昨今、非常に有用な一冊ではないか、ただ40代の自分でさえジェネレーションギャップを感じるこの語り口が少し間口を狭めてる感あり、面白い本でした2015/03/25
mercury
2
タイトルにひかれて読んだが、「なぜ嘘が多いのか言いたい位デタラメがはびこっているので、正しい事をつ伝えます」という本だった。漫談?がすべっている気がするが、食物と人間の体の不思議、絶妙で臨機応変の生体の働きは面白く、難しいく、魅力的だ。コラーゲンを食べてもアミノ酸一個にまで分解され、それをもとに何を作るかは体が決めるのでコラーゲン食品はプラシボ効果しかないとよく理解できた。また、脂肪の取り過ぎの怖さもよくわかった。喉元過ぎれば熱さ忘れるタイプなのでまた読み返したい本。2014/04/12
アセロラ
1
おもしろおかしく書いてある部分もあり、楽しく読めました。でも消化の話などはちょっと難しいので、ちょっと飛ばしました。。。私がこれまで読んだ本では、体内にケトン体が増えても問題ないと研究結果が出ている、と読みました。なので炭水化物よりもほかの栄養を優先して食べるようにしています。でもこの本ではケトン体は体内にためるとよくない悪者になっています。研究も色々で、それぞれの本の著者の立場などあると思いますが、どちらを信じていいのか悩んでしまいます。2018/08/18
茶田
1
理系嫌いにもわかるように、例え話などを多用し、できるだけ易しく解説してあったので読み終えることができました。栄養のことなどさっぱりわからない私にとってはありがたい本でした。2017/03/25