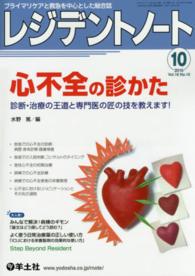内容説明
目上の人を平気で「できていない」と批判する若手社員、駅や飲食店で威張り散らす中高年から、「自分はこんなものではない」と根拠のない自信を持つ若者まで―なぜ「上から」なのか。なぜ「上から」が気になるのか。心理学的な見地から、そのメカニズムを徹底的に解剖する。
目次
プロローグ 「上から目線」とは何か
第1章 なぜ「上から目線」が気になるのか
第2章 「上から」に陥りがちな心理構造
第3章 空気読み社会のジレンマ
第4章 目線に敏感な日本人
第5章 「上から目線」の正体
著者等紹介
榎本博明[エノモトヒロアキ]
心理学博士。1955年東京生まれ。東京大学教育心理学科卒。東芝市場調査課勤務の後、東京都立大学大学院心理学専攻博士課程中退。川村短期大学講師、大阪大学大学院助教授、名城大学大学院教授等を経て、MP人間科学研究所代表。産業能率大学、システムブレーンでも心理学をベースにした企業研修・教育講演を行う(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ito
51
本書は主に若者の「上から」心理事象を扱い、時代や社会変化の背景を論じており、わかりやすく面白い。「上から」に陥る背景として、自己愛の強さやコンプレックスがある。またITリテラシー尊重の空気や、上下関係を経験しない教育環境など社会環境の変化なども背景に存在する。さらに、空気読み社会では人の目に自分がどう映るのかを知ることによる自己認識が難しい。大人世代は現代の若者の心理状況を理解し、メンタルを鍛えるべきだろう。そのままの君でいい、といった思慮の浅い優しさは逆に不幸なのである。2014/01/18
matfalcon
44
目上の人を平気で批判する若手社員、駅や飲食店で威張り散らす中高年、根拠のない自信を持つ若者…。なぜ「上から」なのか? なぜ「上から」が気になるのか? 心理学的な見地から、そのメカニズムを徹底的に解剖する。そもそも「目線」ということばは「上から目線」から始まった。それまでは「視線」しかなかった。2018/06/09
Hideto-S@仮想書店 月舟書房
41
相手の気持ちに立ち入らないことを“やさしさ”と言うようになったのは1990年代からだそうです(第3章)。「上から目線」をキーワードに、さまざまな文献を引用しながら人間関係の距離感について多角的に考察した好著だと思います。主な構成は、第1章「なぜ上から目線が気になるのか」(自信のない人ほど今の自分にこだわる)、第2章「上からに陥りがちな心理構造」(上下・勝ち負けで物事をみる人)、第3章「空気読み社会のジレンマ」、第4章「目線に敏感な日本人」(文化的背景)、第5章「上から目線の正体」(やさしさと弱さの関係)。2014/05/02
はな
37
見下され不安などどうして上から目線はどうしておこるのかなど深く掘り下げている。甘えの強い人は被害者意識を持ちやすい、日本独特の空気を読むなど、すごく納得いき面白かった。今の若者たちの項目は本当にこんななの??とびっくり。新人さんたちと接する時の参考にしようと思った。2018/12/02
hit4papa
29
本書は、上司と部下、同僚、顧客、友人など、他者との関わりにおける「上から目線」の仕組みについて、心理学的アプローチで論を展開するものです。心理学の応用でありがちな、○○効果、××法則を多用して、読者を煙に巻くようなことがありません。引用する図書も手近なもので、全般的にわかりやすく記述されています。ただ、フリーター、派遣社員、はては便所飯まで、話が広がりすぎて、つかみどころが難しくなってしまっているとは思います。他者との関わりについて、ヒントを与えてくれるのは確かなので、一読の価値はありますね。