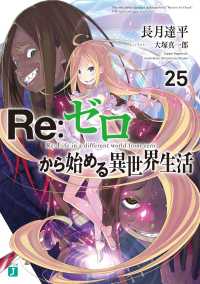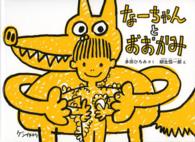出版社内容情報
メソポタミアで生まれたワインは、どのようにして欧州、世界へと広がっていったのか? 日本人による唯一のワイン全史を文庫化。2010年6月に河出書房新社から刊行された『ワインの歴史』を改題、改訂し、文庫化しました。
ワインはメソポタミアに始まり、
エジプト、ギリシャ、ローマを経て、
欧州、世界へどのように広がったのか?
旧約聖書と新約聖書のワイン記述の違い
130種類以上のワインがあった古代ギリシャ
ワインはローマ軍の必需装備だった
ブルゴーニュワインはシトー派修道院が源流
ナポレオン三世が「格付け」を作らせた
--等々、ワインのことをあまり知らない読者も
楽しく読むことができる歴史読み物です。
文庫化にあたっては第10章を改訂し、文庫あとがきを加えました。
序 章 東洋に残る葡萄への思い―日本人はいつからワインを飲んだか
第1章 ワインの源流を探る―メソポタミアの酒宴図
第2章 ワインの育ての親―技術を発展させたエジプト
第3章 古典ワインの形成と確立―ギリシャの神話とのかかわり
第4章 宗教と結びつくワイン―旧約・新約聖書とイスラエル
第5章 ワインにおけるヘレニズムとヘブライズム―ローマの「貴族のワイン」と「庶民のワイン」
第6章 衛生や信仰のためのワイン―多様化する中世
第7章 知と理性のワイン―近代前における変革
第8章 市民社会と科学のワイン―ワインの理想美がつくられた近代
第9章 科学技術が引き起こした大変革―二十世紀のワイン
第10章 ワインの新ルネッサンス時代―世界各国の新たな取り組み
山本 博[ヤマモトヒロシ]
著・文・その他
内容説明
ワインは、メソポタミアに始まり、エジプト、ギリシャ、ローマを経て、欧州、世界へどのように広がったのか。王侯貴族や民衆にどのように飲まれたか。宗教(ユダヤ教・キリスト教)とどのようにかかわりを持ったか。日本人はいつからワインを飲みはじめたのか。フランス革命がワインに及ぼしたものとは?日本人が書いた初のワイン全史。
目次
東洋に残る葡萄への想い―日本人はいつからワインを飲んだか
ワインの源流を探る―メソポタミアの酒宴図
ワインの育ての親―技術を発展させたエジプト
古典ワインの形成と確立―ギリシャの神話とのかかわり
宗教と結びつくワイン―旧約・新約聖書とイスラエル
ワインにおけるヘレニズムとヘブライズム―ローマの「貴族のワイン」と「庶民のワイン」
衛生や信仰のためのワイン―多様化する中世
知と理性のワイン―近代前における変革
市民社会と科学のワイン―ワインの理想美がつくられた近代
科学技術が引き起こした大変革―二十世紀のワイン
ワインの新ルネッサンス時代―世界各国の新たな取り組み
著者等紹介
山本博[ヤマモトヒロシ]
弁護士。1931年横浜生まれ。早稲田大学大学院法律科修了。我が国のワイン評論の先駆け。早くからワインに関心を持ち、世界のワイン生産地を訪れ、その世界に魅了される。フランス食品振興会主催の世界ソムリエコンクールの日本代表審査委員。日本輸入ワイン協会会長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
大先生
Mark X Japan
0010
Wataru Hoshii
るるぴん