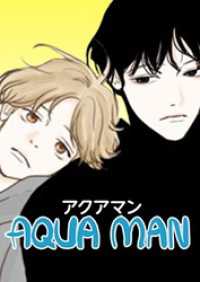出版社内容情報
名門・山一破綻の根底には組織風土の病があった。経営企画室に勤務した社員が顛末をたどり日本企業に共通する「失敗の本質」を抉る。
内容説明
名門・山一證券破綻の背景には深刻な組織風土の病があった。経営企画室に勤務し、山一の最期を見届け、その後、ソニー銀行の創業経営者となった著者が、山一自主廃業までの顛末をたどり、日本企業に共通する「失敗の本質」を抉る。文庫化に伴い、「二十年目の後日談」を加筆。
目次
二十年目の後日談
1 九七年十一月 山一崩壊す
2 失われる求心力
3 飛ばしを生んだ市場の歪み
4 山一はなぜ追い込まれたのか
5 企業風土が会社を壊す
6 いま企業に求められるもの
著者等紹介
石井茂[イシイシゲル]
ソニーフィナンシャルホールディングス社長。1978年山一證券入社。山一證券経済研究所出向、米国留学を経て、93年本社企画室、94年会長秘書役、96年企画室部長、97年11月24日の山一破綻時には事務方として営業休止届を大蔵省に提出した。98年ソニーに転職。ソニー銀行の立ち上げに参加、2001年‐15年ソニー銀行社長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
スプリント
10
エリート証券マンが一夜にして路頭に迷う。この教訓はきちんと生かされているのか。事実とそれに基づいた企業経営論、コンプライアンスのあるべき姿について語られています。2018/09/16
わらびん
4
善人が会社を良からぬ方向に進めるというのが印象に残った。悪意のない者が集まっても組織が先延ばしの社風になると結局はダメになる。社風とは何か、責任を取りたくない経営者、今までの成果のご褒美で経営層になった取締役、現状維持を望む従業員、簡単には述べられないが、現代でも旧態の企業で起きている成人病。考えさせる内容。2017/08/11
undine
3
かつて籍を置いていた会社なので、今でも山一證券の破綻を振り返ることは気が重い。しかしながら、破綻前に感じていた閉塞感が、自主廃業の発表を機に一転吹っ飛び、視界が開けた気がしたことも覚えている。著者の分析の通り、社外の環境変化に背を向け、やるべきことをやらないまま、最後は自滅に至った会社は多くの教訓を与えてくれる。それなのに、山一證券破綻後に転職した今の会社も同様に愚かな失敗を繰り返して苦境に立っている。山一證券の失敗の教訓を日本企業は活かしきれていない気がする。2018/04/15
K.C.
3
会社の同僚から薦められたというより、読めと手渡された夏休みの課題図書(笑)。古い日本企業ならどこにでもあろう光景が負のスパイラルとなって堕ちていく。直前にナショジオの航空機事故の番組を見ていたことの異同としては、必ず伏線があることは同じであるが、航空機事故では最後まで回避の努力をした(が虚しくも墜落した)ことは見いだせない。 我が身を振り返って、この本に登場する人とは逆に、当事者意識はあるかと問われて、自信を持って「はい」とは答えられない。流される前に逃げ出すか、流されてしまうんだろうなと。2017/08/13
nishiyan
3
四大証券会社の一角、山一證券が破たんにいたるまでを 当時、企画室部長であった著者が克明に語っている。 章立ての問題なのか、時系列がごちゃごちゃしているため、読みづらいものの、緊迫した状況が理解できる。 近年、名門が経営危機に陥っている昨今、山一の失敗はどのケースにも当てはまっている。 名門であるが故の暖簾への過剰な思い入れ、前例踏襲主義、そして当事者意識のなさ。必ずしもカリスマ的経営者が企業を潰すのではなく、普通の人の集まりが潰してしまうというところが考えさせられた。2017/07/21