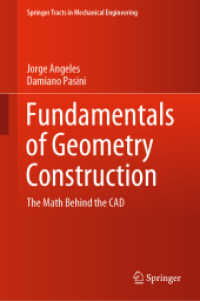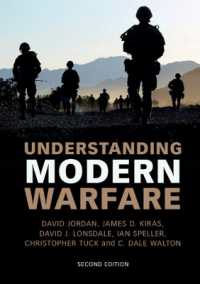内容説明
事業の再編と集中、多角化のためのM&A、社会に対する責任、業界団体の存在―。江戸時代の商人は、成熟した市場経済システムの中で、現代顔負けの熾烈な競争を行っていた。従来の「あきんど」像を打ち破る、ダイナミックな経営の実態を明らかにする。
目次
プロローグ 市場経済システムと競争が経済発展をもたらした
第1章 江戸時代の経済ダイナミズム―市場経済システムの高度な発達
第2章 競争の実際―ビジネスチャンスの飽くなき追求
第3章 競争を勝ち抜くために―競争を通じた企業の発展と継続
第4章 官と民の付き合い方
エピローグ 競争と公のバランス
著者等紹介
鈴木浩三[スズキコウゾウ]
博士(経営学)、東京都水道局東部第二支所長。1960年東京生まれ。中央大学法学部卒業、筑波大学大学院ビジネス科学研究科企業科学専攻修了。83年東京都入庁、水道局建設部管理課長などを経て現職。2007年日本管理会計学会「論文賞」受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
9
2008年初出。「カネだけでは信用は買えなかった」(4頁)。確かに時代は違えど、現代でもカネだけでは人脈も築けない。それは結果に思える。三都と長崎の機能と全国の経済発展の図式はわかりやすい(55頁)。当時の暖簾の意味は、継続営業の結果である信用集積の色彩が強かったという(72頁)。暖簾は単に営業していることをソトに示すものに留まらない、文化資本の象徴なのだ。当時のCSRにも注目できる。当時も法令遵守に透明性が重視されていたという白子組木綿問屋「仲間掟」(1763年 265-6頁)。都の職員にして博士取得。2013/03/28
山田案稜
3
なぜ、日本が明治時代に植民地化せずに自力で資本主義社会を実現できたのか。江戸時代の商人たちのを分析することでなるほどと思える部分がありました。先物取引や、激しい競争、M&A、独自に高度に発展していた資本主義的な仕組み。それだけでなく、日本の株式持ち合い的な発想や、100年以上生き残っている企業の数が他国に比べて圧倒的に多い点など、それらの源流が朧げながら浮かんできます。 「株仲間」や、「暖簾」の重要性や役割の解釈もイメージを覆すもので自分にとって価値のある本でした。2015/01/12
奥山雅之
1
江戸時代は武士や鎖国といった前近代的なイメージがあるが、ここで日本の急成長の礎が形成されたことを明らかにした書。徳川家の天下統一といっても緩やかな連邦制のような国家が地域の多様性を担保していたことも見逃せない。上水道経営では、玉川上水をどのように江戸で活用したかが詳細に描かれている。2015/02/13
枯れる蓮
0
江戸時代も大変だったんだなぁとしみじみ2013/04/18