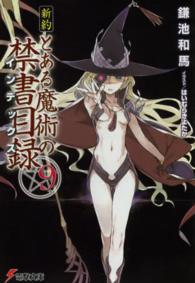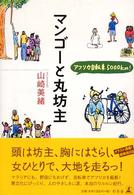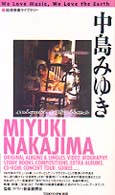出版社内容情報
「経済が成長すれば資源の消費量が増えるに決まっている」
「資本主義と技術が進歩し、社会が豊かになれば、自然環境はダメージを受ける」
――産業革命以降、人間が繁栄すればするほど、地球を壊してしまうという予想が無批判に信じられてきた。
* * *
だが、実際にはどうであったのか。予想とはまったく逆のことが起きたのだ。
資本主義は発展し続け、世界中に勢力を拡大し続けているが、同時にテクノロジーが資源を使わない方向に進歩した。
人類はコンピュータ、インターネットを始めとして多様なデジタル技術を開発し、消費の脱物質化を実現させた。
消費量はますます増加しているものの、地球から取り出す資源は減少している。デジタル技術の進歩により、物理的なモノがデジタルのビットに取って代わられた。かつて複数機器を必要とした作業は、いまやスマホ一つで事足りる。
なぜ経済成長と資源の消費を切り離すことができたのか?
脱物質化へと切り替えられたのはなぜか?
このすばらしい現象について、なぜそれが可能となったのかを解き明かし、どんな可能性を秘めているのかを記していこう。
* * *
テクノロジーの進歩、資本主義、市民の自覚、反応する政府――「希望の四騎士」が揃った先進国では、人間と自然の両方が、よりよい状況となりつつある。この先の人類が繁栄し続ける道がここにある。
内容説明
「経済成長は資源消費量を増やす」「社会が豊かになれば、自然を壊す」―人間が繁栄すればするほど、天然資源は枯渇し食糧生産は限界を迎えるという予想が、無批判に信じられてきた。だが実際には、予想と正反対のことが起きた。もはや人類と自然界のトレードオフの関係は終わった。資本主義は発展しつづけ、世界中に勢力を拡大しつづけているが、同時にテクノロジーが資源を使わない方向に進歩した。人類は多様なデジタル技術を開発し、消費の脱物質化を実現させた。デジタル技術の進歩により、物理的なモノが、デジタルのビットに取って代わられた。かつて複数機器を必要とした作業は、いまやスマホひとつで事足りる。地球から取り出す資源は減少している。人類は経済成長と資源消費量を切り離すことに成功し、経済の脱物質化へと舵を切った。このすばらしい現象について、なぜそれが可能となったのかを解き明かし、どんな可能性を秘めているのかを記していこう。テクノロジーの進歩、資本主義、市民の自覚、反応する政府―“希望の四騎士”が揃えば人間と自然の両方が、よりよい状況となる。この先の人類が繁栄しつづける道がここにある。
目次
マルサス主義者の黄金時代
人類が地球を支配した工業化時代
工業化が犯した過ち
アースデイと問題提起
脱物質化というサプライズ
なぜリサイクルや消費抑制は失敗するか
何が脱物質化を引き起こすのか―市場と驚異
アダム・スミスによれば―資本主義についての考察
さらに必要なのは―人々、そして政策
“希望の四騎士”が世界を駆け巡る
どんどんよくなる
集中化
絆の喪失と分断
この先にある未来へ
賢明な介入
未来の地球
著者等紹介
マカフィー,アンドリュー[マカフィー,アンドリュー] [McAfee,Andrew]
マサチューセッツ工科大学(MIT)スローン経営大学院首席リサーチ・サイエンティスト。MITデジタル経済イニシアティブの共同創設者兼共同ディレクター。デジタル技術がどう世界を変えるのかを研究している。フォーリン・アフェアーズ誌、ハーバード・ビジネス・レビュー誌、エコノミスト誌、ウォール・ストリート・ジャーナル紙などに寄稿するほか、世界経済フォーラム、TEDなどにも登壇している。MITとハーバード大学にて複数の学位を取得。マサチューセッツ州ケンブリッジ在住
小川敏子[オガワトシコ]
翻訳家。東京生まれ、慶應義塾大学文学部英文学科卒業。小説からノンフィクションまで幅広いジャンルで活躍。訳書多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
にしがき
まいこ
ta_chanko
M
朝ですよね
-
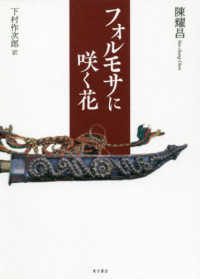
- 和書
- フォルモサに咲く花