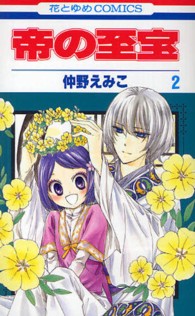内容説明
石油にも原発にも依存しない21世紀のエネルギー安全保障をどうデザインするか?洪水や津波、海面上昇…沿岸の低い土地に大都市が集中する日本の水害リスクにどう対処するか?3人に1人が高齢者となる時代、交通弱者や災害弱者を増やさない都市と社会のあり方とは?エネルギー、気候変動から都市災害、水と食、生物多様性まで、第一線の専門家・実務家をゲストに行われた、地球大学の講義ライブを一冊に。
目次
第1部 宇宙船地球号のエネルギーインフラ(世界を変える自然エネルギー;太陽経済で日本をリセットする ほか)
第2部 未来をつくるソーシャルデザイン(「コストリテラシー」を育てる;地球の未来を可視化する―温暖化懐疑論への回答 ほか)
第3部 地球公共財としての生物多様性(宇宙船地球号の「食」を守る;「食育」の最前線 ほか)
第4部 地球目線で考える都市の未来(東京の生物多様性―陸と海からの視点;ミツバチが媒介する都市革命 ほか)
著者等紹介
竹村真一[タケムラシンイチ]
1959年生まれ。京都造形芸術大学教授。東日本大震災復興構想会議検討部会専門委員。地球時代の人間学を提唱、ITを活用したさまざまな社会実験プロジェクトを推進。「触れる地球」(2005年グッドデザイン賞・金賞)や「100万人のキャンドルナイト」、ユビキタス携帯ナビ「どこでも博物館」などをプロデュース(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
4
脱所有、脱物質、脱貨幣(95ページ)。実際、それなりに最低限の財やサービスは必要で、それらのために貨幣は必要だとは思えるが・・・。社会のしくみを変える必要があるのはよくわかるが、実際にどう市民が行動したらいいのか。赤池学氏は以前から知っていた人であるが、2016年東京五輪招致に乗り出すようで、猪瀬都知事の思惑と合致しそうなプロジェクトを構想しているようだ(157ページ)。BOPを竹村氏は、Base of the Planetという捉え方に変えるべきだ(388ページ)とする。人間の安全保障と絡めたのは卓見。2013/01/05