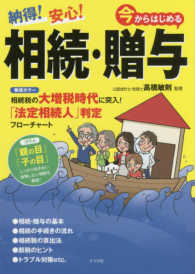出版社内容情報
「取引先との関係強化」というメリットはない
全上場企業のデータから導き出された真実
日本企業は、企業同士で株式を持ち合う政策保有株式(持ち合い株式)が歴史的に非常に多い。しかし、2014年に「スチュワードシップ・コード」、2015年に「コーポレートガバナンス・コード」が導入され、政策保有株式の解消が促されている。近年、政策保有株式は減少し続けているが、いまだに全体の5%程度、27兆円が政策保有株式と推定される。
政策保有株式を持つ企業は「取引先との関係強化」などの効果を主張し、買い増しをする企業もある。一方で、金融庁は、政策保有株式を削減させるため、保有銘柄数やそれらの定量的な効果など開示の強化を求めており、政策保有株式の意義に注目が集まっている。
本書は、政策保有株式が増加した歴史的経緯を解説し、これまで正確に把握されてこなかった政策保有株式の実態を、全上場企業の有価証券報告書のデータを基に明らかにする。その上で、企業の収益性・安定性・成長性に与える影響を定量的に分析。政策保有株式には「取引先との関係強化」などのメリットはなく、「物言わぬ株主」が増えることによるコーポレート・ガバナンスの機能不全、資産の非効率運用などのデメリットが多いことを明らかにする。
政策保有株式を、これほどまでに定量的かつ精緻に分析した研究は今までになく、本邦初の内容となる。
内容説明
多く持つほど利益率が低く、取引関係の維持・強化にはつながらない。買収防衛、高株価維持、取引先との関係強化など様々な目的で導入され、“根雪”のように残る株式持合い。綿密な分析から、もはやそのメリットが乏しいことを明らかにする。
目次
本書の問題意識と用語の定義
第1部 政策保有株式(株式持合い)の成立(株式の集中化とその漂流―戦前~1950年代;株式持合いの本格化;企業集団の形成と株式持合い;株式持合いの変質とバブル崩壊;コーポレート・ガバナンスと政策保有株式の時代)
第2部 政策保有株式の実証分析(株式持合いの効果と経済的影響―先行研究のレビュー;実証分析で用いるデータの特徴;政策保有株式と会計数値の関係;株式売却前後の会計数値の比較;政策保有株式の売却行動の決定要因;日本企業の安定株主の実態;議決権の価値算出の一試案)
なぜ、持合いを続けるのか―日本企業への提言
著者等紹介
円谷昭一[ツムラヤショウイチ]
一橋大学大学院経営管理研究科准教授。2001年、一橋大学商学部卒業。2006年、一橋大学大学院商学研究科博士後期課程修了、博士(商学)。埼玉大学経済学部専任講師、准教授を経て、2011年より現職。2019年、韓国外国語大学客員教授。日本IR協議会客員研究員(2007年~)。日本IR学会理事。2013年、経済産業省「持続的成長への競争力とインセンティブ~企業と投資家の望ましい関係構築を考える~」委員、経済産業省「企業会計とディスクロージャーの合理化に向けた調査研究」委員、2017年、りそなアセットマネジメント「責任投資検証会議」メンバー。専門は、ディスクロージャー、IR(Investor Relations)、コーポレート・ガバナンス研究(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。