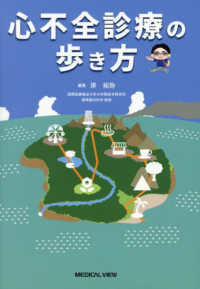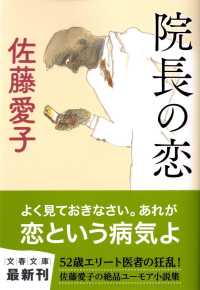出版社内容情報
戦後日本農政の大転機「減反廃止」がついに実現しようとしている。減反政策の功罪をデータに基づき、的確な廃止策を明らかにする。
内容説明
競争力劣化、規模拡大阻害、食料自給率低下の元凶だったのか?悲劇の検証から問題解決は始まる。迷走の40年をムダにするな。
目次
序章 なぜ、今、減反見直し(廃止)を決断したのか
第1章 誤解と真実―日本の減反40年
第2章 乗り遅れた日本―世界の減反80年と廃止の流れ
第3章 負のインパクト―減反の虚像と実像
第4章 シナリオ―減反の終わり方
第5章 ポスト減反廃止の日本農業
著者等紹介
荒幡克己[アラハタカツミ]
岐阜大学応用生物科学部教授、農学博士。1954年生まれ、78年東京大学農学部卒、同年農林省入省、96年岐阜大学農学部助教授、99年より現職、日本学術会議連携会員。この間、2002‐03年アデレード大学経済学部客員研究員、06年メリーランド大学農業政策研究センター客員研究員、12年イリノイ大学農業経済学科客員研究員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
29
経済学理論と実証から成る、本格的な専門書。各章末にポイントも列挙されている。そこから読み、気になった箇所があればその章は読む方向で良いと思う。減反廃止の意思決定は、米大増産と価格暴落のおそれが和らいだことが最重要。背景に、高齢化、担い手不足(19頁)。農協はむしろ減反に引き込まれることに抵抗してきた(45頁)。行政からの要請を断り切れず、巡回指導には参加したという。積極的説得行動はしていなかったようだ(46頁)。2015/11/28
CCC
10
専門性が高くて少し難しかったけれど、面積あたりの米の収量が抜かれまくって10位圏外になっている事や、技術と環境の整備によって、今となっては湿潤地帯より乾燥地帯の方がより多く米が取れる土地になっているというのは知らなかったので、なかなか驚きがあった。2017/04/09
くものすけ
8
約50年継続された減反政策の廃止は2018年、本書の出版は2015年なので実際廃止以降の状況は踏まえられていない。廃止後もコメからの転作には補助金が支払われているというから驚きです。現実としてコメの消費は落ち込み、単収(生産効率)も減反期間中一向に上がっていないと。しかし食料自給率の貢献度は4.31%等々日本のコメ作りの状況を理解する為、大いに参考になる本だった。一方、減退廃止後一時的にコメ作付面積が増えながら、今年のコメ小売価格の急上昇の理由は何なのか?この疑問に対する答えは見つからなかったのが残念。2024/11/28
kaya
6
減反について考えるということは、日本の農業が抱えるあらゆる問題について考えるということ。減反とは具体的に何を行ってきたのか、その結果どうなったのかを、丁寧にデータを示しながら解説されている。経済学の知識が不足しているため、数値に関しては自分で判断できなかったのが悔しいけれど、それでも流れを追って行くことはできた。「聖域」であったコメ、だけど消費の現状を見ると、果たして本当に?とは思う。知らなかったことがたくさん。これから仕事をしていく上でまた読み返す必要があると思った。2016/04/30
Mc6ρ助
5
『「減反をしながら米価を上げるという政策は、冷房と暖房を一緒にかけるようなものだ。長い目で見たら、決して農民のためにならない。(渡辺美智雄・元農林水産大臣)(p35)』担当する施政者がそう喝破していながら40年の長きにわたりそれを続いてきた日本の農政とはなんなのだろう、減反とはなんだったんだろう。生産者と消費者に痛みを分け与え財政の支出を抑えたわけだが、ただ日本の米作の競争力を削いできたように思う。まだ間に合うのだろうか?2016/05/28