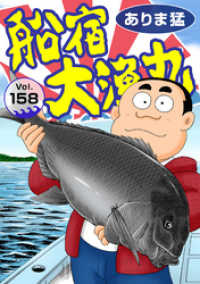内容説明
他人の所得、格差意識、夫婦の役割分担、結婚、地域の所得水準、雇用、初めて就く職、子供時代の貧困・虐待、男と女、国際比較―。何が日本人の幸福感、健康感、生活満足度を決めているのか?経済学だけでなく、社会学、社会疫学的分析も活用し、解明。
目次
序章 主観的厚生とは何か
第1章 つい他人と比べたくなるのが人情―幸せは相対的な概念
第2章 格差社会はやはり嫌だ―所得格差と主観的厚生の関係
第3章 幸せになれる家族とは―家族関係が左右する主観的厚生
第4章 子供は親を選べない―子供時代のつらい経験の長期的影響
第5章 どう働き、どこに住むか―キャリア・居住環境と主観的厚生
第6章 ショックやストレスとどう付き合うか―所得変動ショック・仕事のストレスと主観的厚生
終章 主観的厚生の分析から見えてくるもの―研究成果をどう活用するか
著者等紹介
小塩隆士[オシオタカシ]
一橋大学経済研究所教授。1960年生まれ。83年東京大学教養学部卒業、経済企画庁(現内閣府)などを経て、2009年より現職。大阪大学博士(国際公共政策)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
yurari
3
主観的厚生とは聞きなれない言葉だが、幸せは感じるものであり客観的に測定することが難しい為、あえて「主観的」と言う言葉を使っている。データが豊富で読み応えはあるが、新たな知見はそこまで得られず。→幸福や健康感自分と似た集団との比較によって左右される/貧困地域では幸福感や健康感を感じにくい(→貧困地域への支援が必要)/子供の貧困はその後の人生に及ぼす影響が大きい2021/12/04
まゆまゆ
3
これまでの経済分析では得られなかった、主観的厚生(自分の生活の全体あるいは一部に対する満足度の度合い)という分析により、社会の病理や不公平をあぶり出す。相対的所得仮説(自分に似た境遇の他人の所得と比べて満足感を得る)というのが一番しっくりきたかな。最初の就業で非正規だと今後ずっと満足度が上がらない……というのも興味深い。2014/04/30
ミッキー
0
経済学による行動分析の可能性を感じることが出来ました。内容としては子供の幸せについてが勉強になりました。今迄よんだ著作同様、示唆に富んでいます。そして、今、統計が注文されていますが、統計学の威力を実際に伺えるという意味で、是非とも読みたい本だと思いました。2014/06/24
ぐっさん
0
統計の結果だけでも参考になる。 統計の詳しいやり方までは理解できなかったが、他の分野の分析にも使えそう。国家の運営だけでなく、会社の経営とかにも応用できそう。2014/06/07
peisaku2014
0
授業で読んだ。経済学の分析はその性格上生身の人間が想像できないことが多いが,この本は違った。経済学にもこういう観点が入ってきているのか!と興味深く読んだ。「主観的厚生」という内面的なものを扱っているゆえ,ものすごく分析を慎重に行い,その限界を丁寧に断っている点も好感が持てる。また,政策的提言にも慎重で良い。今後パネルデータを用いるなどして,もっと有益な知見が引き出せていくといいなと感じる。経済的豊かさの成長がほとんど見込めない中で,人々がどう「幸福」を維持しているのか――今後に向けて重要なテーマである。2014/05/13