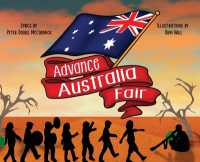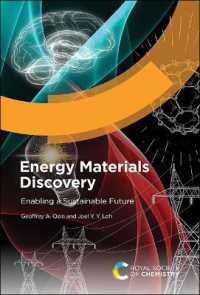出版社内容情報
道路はもっとも身近な交通施設。本書は基本から歴史、作り方や材料まで幅広く、やさしく丁寧に解説した1冊。道路はもっとも身近な交通施設。その下には上下水道管やガス管といったライフラインや地下鉄のような地下空間がある。また、一口に道路の舗装といっても、方法や材料も様々で、伝統的な方法から最新の技術が盛り込まれたものまで多様である。本書は基本から歴史、作り方や材料まで幅広く、やさしく丁寧に解説した1冊。
峯岸 邦夫[ミネギシ クニオ]
著・文・その他/編集
内容説明
皆さんが学校や会社へ通うとき、遊びに出かけるときに、自分の家から一歩外に出るとそこはもう道路です。道路は、空気と同様にあって当たり前のような存在になっているため、ほとんどの人がその存在を意識しません。
目次
第1章 道路とは?
第2章 道路にまつわる歴史と文化
第3章 道路を計画・設計するときに考えていること
第4章 舗装の種類や施工方法
第5章 舗装の材料と道路工事の現場
第6章 道路の管理および保守・点検と更新
第7章 道路事業を行うにあたって
著者等紹介
峯岸邦夫[ミネギシクニオ]
日本大学理工学部交通システム工学科教授。専門:地盤工学、道路工学。1964年東京都生まれ。1987年日本大学理工学部卒業、1989年日本大学大学院博士前期課程修了。日本大学助手、専任講師、准教授等を経て、2014年より現職。博士(工学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
姉勤
31
ムックシリーズの道路にまつわる一冊。道の歴史、舗装の構造、信号や標識、製造車輛やメンテナンスetc。日々の暮らしに欠かせない道路。国の血管と言える道路の不備で経済が停滞するのは道理で、公共事業の無駄使いなる呪符で困るのは生活者たる国民。最近舗装の雑さが目につき、技術が進化しているのに業(わざ)が劣化しているように感じるのも、無知に付け込み、掛けるべき所に金をかけさせないデマゴーグが大手を振って歩いているから。2019/01/31
かず
24
4月から道路管理担当になるため予習。「道路とは?」「道路にまつわる歴史と文化」「道路を計画・設計するときに考えていること」「舗装の種類や施工方法」「舗装の材料と道路工事の現場」「道路の管理及び保守・点検と更新」「道路事業を行うにあたって」の構成。題名のとおり「トコトンやさしい」記述内容となっております。道路は河川と異なり人工物である以上、管理者には最適な利便性を確保していく義務があると思います。安全かつ円滑な交通確保、また道の駅による休憩・情報発信・地域連携各機能の保持の為、微力を尽くしたいと思います。2020/03/24
Kohei
3
仕事柄、勉強のために購入。身近に当たり前のように存在し、当たり前のように利用しているけど、大変な時間と労力と研究によって今日に至っている。さらに、地下の見えないところでも、最先端の高度な理論と技術によって我々の普段の生活が支えられている。 まだまだ長い付き合いになりそうなので、困った時には読み返したい。加えて、同シリーズのダム、トンネル、水道管、橋のあたりも読みたいと思います。2019/05/25
ミユ
1
国道は全て日本橋起点と知って驚いた。 特定の条件が揃うと道路がつくられるのか?県道や国道に制定されるのか?よくわからないが、この辺りもう少し理解したい。 道路にコンクリートではなくアスファルト舗装が利用される理由は割と理解できた。時間をかけず補修もしやすく、慣らしがしやすい。「アスファルト」は正しくは接着剤の意で、アスファルト舗装が砂石とアスファルトを混ぜたもの。2026/01/11
三浦正
1
猛暑日連続中 エアコン無し扇風機中心ライフ! 日中は数独(ナンプレ)ゲームに熱中 夜10時過ぎて、ようやく読書に、、、 「トコトンやさしい」を標榜するシリーズ本の1冊 確かに難しい感じはなく 午前2時前に読了。2025/08/06