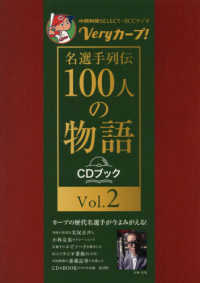目次
第1章 検図の現状と課題(アンケートに基づいた検図の実態と課題内容;検図の実態 ほか)
第2章 あるべき開発プロセスでの検図の仕組み(設計の基本原理;あるべき開発プロセス ほか)
第3章 あるべき検図の詳細プロセスと検図に必要な内容(検図プロセス;検図に必要な準備物)
第4章 3DCADを活かした検図方法(間違った3DCADの使われ方;本来の3DCADの使い方)
第5章 確実な自己検図を実施しよう(間違った自己検図方法(現状の自己検図方法)
自己検図の進め方)
著者等紹介
中山聡史[ナカヤマサトシ]
大阪府大阪市出身。関西大学機械システム工学科卒業後、大手自動車メーカーにてエンジン設計、開発、品質管理、環境対応業務等に従事。ほぼすべてのエンジンシステムに関わり、海外でのエンジン走行テストなども多く経験。現在、株式会社A&Mコンサルトにて製造業を中心に設計改善、トヨタ流問題解決の考え方を展開。理念である「モノ造りのQCDの80%は設計で決まる!」のもと、自動車メーカーでの開発~設計~製造、並びに品質保証などの経験を活かし、多くのモノ造り企業で設計業務改革や品質・製造改善、生産管理システムの構築などを支援している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Thinking_sketch_book
5
★★★☆☆ 3Dはあまり関係無い内容。検図でチェックリストを作れというのは分かるが新しさが無い。 本書で言われている通り検図がハンコを押す儀式や寸法チェック作業になるのは良く無い。 過去の技術を残す方法などをもう少し書いて欲しかった2023/07/25
yoei H
3
決められた工程で、決められたチェックをきちんと行う。 検図権限者は、ルールの改定を定期的に行うことで、より精度の良い教育、検図を実施できる環境を作っていく。 俗人化から制度化にシフトさせる、それに尽きる気がする。2025/04/06
朧月
1
セミナーを聞いてから読了 DFRBMやQFDなどのツールの利用ができてないなぁ。そもそも要求仕様の洗い出しってのがなかなか出来ない。 他の本にもあったけど設計項目を要求内容と属性に分解してパラメータとして管理したり評価したりということを、もうちょっときちんとやってノウハウを蓄積すべきだなぁ2023/02/28
drunkennessgod
0
検図の性質と役割、定義の仕方、自社の検図方法がザルすぎると判明、ザル検図をどうにかしましょうと提言する時に使えそうな記載が多い、自分の仕事内容にあわせて出力するとこまでが検図、参考にしてチェックリスト作りたい2021/05/11