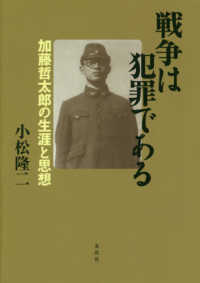- ホーム
- > 和書
- > 理学
- > 環境
- > 資源・エネルギー問題
内容説明
再生可能エネルギーの大型電源確保に向けてついに日本も動き出した。
目次
1 いまなぜ洋上風力発電なのか(洋上風力発電の原理・構造はきわめてシンプル;洋上風力発電のメリット;立ち上がり時期が不幸だった日本の風力発電事業;洋上風力発電の技術開発動向)
2 先行する欧米中、追随する日本(大規模開発が進行中の欧州;政府が総力をあげ推進する米国;風力大国の道をゆく中国、躍進する韓国;動き出した日本)
3 洋上風力発電導入に向けての課題と解決策(海域選定上の技術的条件;先行的に海域を利用している者との利用調整;環境対策;電力系統の安定化;採算性の確保経済成長、地域振興、雇用創出の実現;法制度の整備)
4 洋上風力発電導入のシナリオと提言
著者等紹介
岩本晃一[イワモトコウイチ]
1958年生まれ、香川県出身。京都大学卒、京都大学大学院工学研究科修了後、通産省入省。内閣官房都市再生本部事務局内閣参事官、産業技術総合研究所つくばセンター次長、内閣官房総合海洋政策本部事務局内閣参事官などを経て、現在、経産省地域経済産業グループ産業政策分析官(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Nobu A
9
岩本晃一著書初読。12年刊行。著者は通産省地域経済産業グループ産業政策分析官。現在は経済産業研究所研究員。風力発電関係の書籍は少なく、従って著者も少なくその中の一人。10年以上前に本書だが、国内においての状況はあまり変わらず情報が古い印象はない。陸上の風車数は格段に増えているが、洋上に関してはあまり進展がない。だからだろうか、現在、筆者は専門をAIと経済の関連性に鞍替え。世界の情勢や国別の問題点や課題が勉強になった。また、洋上風車による魚介類の被害はなく、逆に魚が増えた事例もあるが、因果関係は不明。2024/03/12
☆ツイテル☆
2
フライヤー2021/06/28
6haramitsu
1
ちょっと古いが参考になった。石油ショック、チェルノブイリで欧州は再生可能エネルギーに転換。逆に日本は原子力に傾倒し、2011.3.11で行き詰まる。風力発電は、洋上にシフトしている。欧州は台風がなく風力も安定しているため、風車の設計がシンプル。しかし、日本ではそうは行かず、以前に導入した風車は日本の複雑な風や台風などで破損。また、風力発電のノウハウもなく保守ができず終了。三菱重工、日立ともに撤退。福島沖洋上風力発電も2020.12撤去が決まる。今後の開発は大変そうだが、もう一度チャレンジしてもらいたい。2020/12/31
シロマック
1
右綴じ本としては技術解説本としての機能を満足している。図やグラフ等に具体的な資料も含まれているので分かり易い。でも文中の数値、数式やアルファベットのスペルは横書きなので本を横向きにしないと読みずらく苦労する。 遠浅の海岸には海底着床式深いところでは浮体式がよいと思う。風力だけでなくその他の自然エネルギー発電はすべての場所で同じ方式を採用するのではなくそれぞれに合った方式を採用するきめの細かい対応が大切だと思う。2018/06/23
Satellite
1
経済産業省の現役の官僚の方が書いた本。チェルノブイリ原発事故や京都議定書というできごとに、日本がとった原発という道、ドイツがとった再エネという道。その結果を目にした時の衝撃が率直に書かれているのが印象的。私たちの世代の責任、技術者としての倫理を考えさせられる。2018/02/05
-
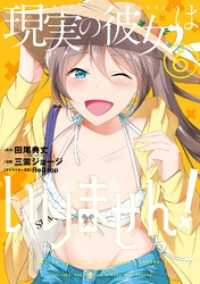
- 電子書籍
- 現実の彼女はいりません! 6巻 ヤング…