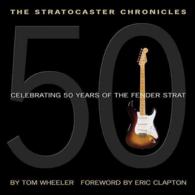出版社内容情報
はじめに
二一世紀に入ったいま、米国のITバブル崩壊が日本を含む様々な国々にも波及して、世界経済はにわかに不透明さを増したように思える。しかしながら、必要以上に強調されがちな悲観的ムードに引きずられて、マクロな視点が曇るようであってはならない。
かつて、未来学者のアルビン・トフラーは『第三の波』を著した。標題の「第三の波」とは、人類の歴史が始まって以来、三番目に直面する大変革を指している。第一の波は紀元前に訪れた。狩猟採集の生活形態と社会構造を抜本的に変えることになった農業化の波である。そして第二の波が一九世紀と二〇世紀をはさんだ時期に訪れた。これは工業化の波である。第三の波は、言うまでもなく「情報化の波」である。これはインターネットが普及し始める前には、やや漠然としたものであったが、九六年頃を境に個人にも企業にもインターネットが浸透するようになって、非常に大きな変化であることが誰にも実感できるものとなった。
仮に ITバブル が崩壊したとしても、それは一〇年二〇年のスパンで眺めるなら局所的な現象であり、トフラーが指摘した情報化の波が人類全体にもたらすインパクトが薄れるものではない。すでにインターネットを 経験 してしまった以上、それ以前の状態に戻るなどということは決してないのである。すなわち、インターネットがもたらす情報化の波は、今後も市場を変え、社会を変え、私たちの生活を様々な側面から変えていくに違いない。
本書の冒頭で、あえてこのようなことを記すのは、二一世紀におけるわが国のエネルギー産業像を展望していくのに、二一世紀の社会ないし市場というものを、概略見定めておく必要があるからである。
筆者は、「情報化の波」の到来とともに訪れる知識資本主義社会の時代に求められる産業像を「智融業」と名付け、過去にも金融業を対象に論考を展開してきた。智融業は、なにも金融業に決して限定されるものではなく、二一世紀にあってすべての産業が備えるべき特性を集約した言葉である。知識や知恵をもっとも大切な資源として捉え、それを有効に活用するなかで社会や市場に真の意味での価値をもたらしていく、そうした企業のあり方がすなわち智融業である。電力をはじめとして、ガス、石油などのエネルギー産業にも、そうした智融業としてのあり方が求められているのである。
今日、世界的なディレギュレーション(規制緩和)の潮流のなかで、エネルギー産業も「市場の自由化」に対処していくことが求められている。そして、情報化の波は「市場の情報化」をもたらし、既存の巨大企業が支配するマーケット構造を壊しながら、従来の成功ルールをドッグイヤーのスピードで一気に陳腐化させていく。
こうした市場の情報化によってもたらされる状況を一言で言うなら、バイヤーセントリック(顧客中心)な市場ということになる。情報化によって、決定権や選択権はサプライヤー(供給者)側からバイヤー(需要家)側にシフトしていくのである。
したがって、これに対するサプライヤーとしてのエネルギー企業の側も変わっていかざるを得ない。顧客がすでに情報を持っている以上、エネルギー企業側はそれに勝る情報を持ち、顧客の動きを読みながら柔軟に商品やサービスを組み替えていく必要がある。また、それができるような経営体制を築き上げていくことが求められるのである。そうした変革ができないエネルギー企業は淘汰されたとしても致し方ない。
企業は、決して永続する枠組みではなく、変革を拒む企業が淘汰されていくというのはどの時代においても必然である。例えば、米国企業を代表するダウ平均採用銘柄三〇社には、一八九六年の初回採用銘柄として唯一ゼネラルエレクトリックが残っている。これは同社が不断の企業変革を遂げてきたからである。その同社にしても、実は細かく見れば、過去に何度かダウ平均からはずされ、再び採用されたという経緯がある。同社もある時期には淘汰されかかったのである。
企業経営の課題に「情報化への対応」という項目が加わった現在、市場が企業を淘汰する勢いはいっそう激しくなっている。仮に一年先までは何とか読めたとしても、三年先、五年先は誰にもわからないという状況が、どの業界に限らず現実としてある。
エネルギー産業も例外ではない。
日本の規制産業の場合、規制がかなり堅固である間はこうした市場の情報化、バイヤーセントリックマーケットへの移行といったことは起こりにくい。直近では、金融業がそうであった。いわば情報化の波が氷結されている状況である。
規制緩和によってこの氷は溶け出していく。それがまさに起こりかけているのがエネルギー業界、なかでも電力業界である。
電力の規制緩和が早くから進んだ米国においては、既存の電力会社が多様な展開を進めてきた。また、パワーマーケター、ESP(Energy Service Provider)、ESCO(Energy Service Company)、アグリゲーターといった新しい業態も出現し、業界全体に活気をもたらしている。これによって、大口需要家のみならず一般家庭においても配電会社を選択できるようになるなど、バイヤーセントリックマーケット化は確実に進んでいると言える(なお、二〇〇一年初頭に輪番の停電という、あってはならない事態を引き起こしたカリフォルニア州については、後述するように規制緩和ゆえの電力危機ではなく、同州固有の事情が原因である)。
こうした動きは「デマンドサイド」という概念の浸透ともパラレルで起こっている。一九七七年、アメリカのエネルギー学者エイモリ・ロビンスは「ソフトエネルギーパス」という論文を発表し、世界で大きな反響を巻き起こした。
「ソフトエネルギーパス」では、「エネルギーの需要」と「再生可能エネルギーの導入」に力点をおいたエネルギー社会像を提唱している。ソフトパスの対の概念である「ハードパス」は、原子力や化石燃料などのエネルギー供給に過度に依存した「サプライサイド」の考え方であるわけだが、それが当時の常識でもあった。それだけにソフトパスの概念は人々に新鮮な驚きを与えた。
「ソフトエネルギーパス」が主張した「デマンドサイド」の概念は、ロビンスの論文が発表されてから二十数年を経た今日に至っても、いささかも色あせてはいない。むしろ、二一世紀を迎えて社会や経済そのものが「デマンドサイド」の色調をますます強めていることからすれば、改めて彼の深い洞察に驚くほかない。例えば、一部で浸透し始めている熱電併給を行う小型マイクロガスタービンの存在によって、小規模な分散電源の姿がにわかに現実味を帯びてきたが、これもデマンドサイド的なアプローチの一つである。
このような環境変化に適応し、新しい産業像への変革に向けて求められる「企業変革」の方法論を、筆者は「eトランスフォーメーション」と名付けている。
Eトランスフォーメーションとは、規制緩和とIT革命の進展で創出されるバイヤーセントリックマーケットに対し、ITによって抜本的な企業変革を遂げるアプローチをいう。具体的には企業における変革を、第一章で述べるようにインサイド(Inside)、バイサイド(Buy-side)、セルサイド(Sell-side)、エクスチェンジ(Exchange)、アウトサイド(Outside)の五つの経営サブ・モデルに分け、それぞれのサブ・モデルにおいて適切な方法論を適用していくものだ。
例えば、米国の石油メジャーや大手電力会社はインサイドの経営サブ・モデルにおいてERP(統合基幹システム)を導入し、間接部門の大胆な合理化を成し遂げると同時に、リアルタイム経営の環境を整えている。このようにインサイドの体制が整った後の段階では、他社との取引を行うエクスチェンジの部分でeプロキュアメント(電子調達)を本格化させたり、eCRM(ネットチャネルを統合したCRM)によって顧客関係の緊密化を行うなど、さらなるeトランスフォーメーションに着手している。トフラーの言う第三の波を企業が乗り越えていくためには、このようなeトランスフォーメーションこそが求められているのである。
本書では、規制緩和とIT革命が同時進展するなかで石油ビジネス、ガスビジネス、電力ビジネスのeトランスフォーメーションについて欧米事例を参照しつつ、日本のエネルギー産業に求められるeトランスフォーメーションの具体論について述べていく。
石油、ガス、電力の各分野について内外で行われている規制緩和については、業界の動向に詳しくない一般読者の方にもある程度の展望を持っていただけるよう、簡略に経緯を記している。すでに把握されている方はその部分は読み飛ばしていただいて構わない。
また、ITに関連した専門知識をお持ちでない方のために、IT関連の記述はできるだけ平易な用語で記すように努めている。これによって一般の読者の方々にも、エネルギービジネスの規制緩和動向全般と、それに適用されるIT関連の諸要素の双方について、はっきりとした構図を描いていただけるよう意図した。
エネルギー業界に関心のある方々はもとより、ITがもたらす企業変革のあり方に関心をお持ちの経営者や、経営管理に携わる方々にもお読みいただき、ご意見等を賜ることができればと考える次第である。
二〇〇一年十一月 鴨志田 晃目 次
はじめに 1
第一章 エネルギー産業に求められるeトランスフォーメーション 11
1 金融業界の規制緩和は何をもたらしたか? 12
2 米国におけるeトランスフォーメーションの先進事例 18
3 eトランスフォーメーションとは何か? 23
第二章 石油ビジネスの業界再編とeトランスフォーメーション 49
1 内外の市場変化と規制緩和 50
2 石油化学工業A社にみるERP導入のプロセス 60
3 大規模な合理化をR/3ベースで実現したB社 70
4 海外メジャーのERP活用 77
第三章 ガスビジネスの動向とeトランスフォーメーション 89
1 将来性のある天然ガス資源 90
2 内外のガスビジネス関連の規制緩和 99
3 ガスビジネスにおけるIT活用の可能性 109
第四章 ITを活用した新しい市場へのアプローチ 119
1 続々と出現する新しい市場 120
2 既存市場電子化型 124
3 企業間取引効率化型 130
第五章 米国の電力規制緩和動向とエネルギービジネス 145
1 米国の電力規制緩和の枠組み 146
2 米国の主な電力ビジネス、展開の特徴 156
3 エネルギー関連ITビジネス 172
第六章 日本の電力規制緩和はどこへ向かっているのか? 191
1 欧米の規制緩和と新しいプレイヤー群 192
2 日本の電力規制緩和の行方 204
第七章 電力会社のeトランスフォーメーション 217
1 ERP導入のポイント 218
2 EAM導入では何に留意すべきか 227
3 eプロキュアメントの段階的発展 232
4 CRMでは目的を明確化させる 239
5 アウトソーシングの活用をどうするか? 246
あとがき 251
謝辞 254
推薦の言葉 255"
内容説明
ERP、eマーケットプレイス、そしてeプロキュアメント、CRM、ASPがエネルギー産業に与える衝撃とは?5つのeトランスフォーメーションの視点から豊富な事例を解説。
目次
第1章 エネルギー産業に求められるeトランスフォーメーション
第2章 石油ビジネスの業界再編とeトランスフォーメーション
第3章 ガスビジネスの動向とeトランスフォーメーション
第4章 ITを活用した新しい市場へのアプローチ
第5章 米国の電力規制緩和動向とエネルギービジネス
第6章 日本の電力規制緩和はどこへ向かっているのか?
第7章 電力会社のeトランスフォーメーション
著者等紹介
鴨志田晃[カモシダアキラ]
デロイトトーマツコンサルティングパートナーエネルギー事業部長。1958年生まれ。1981年横浜国立大学工学部卒業。1989年慶応義塾大学大学院経営管理研究科修了。ロンドン大学経営大学院IEP修了。経営学修士(MBA)。東京電力株式会社、株式会社日本総合研究所を経て、現職。1992年以降、大手民間企業とともに「ソフトエネルギー」「独立系発電事業(IPP)」「省エネルギーサービス事業(ESCO)」の各コンソーシアムを設立・運営。また、1999年10月には、都銀、地銀、コンビニ、通信会社、メーカー各社と海外企業の日米20社を結集し、インターネットを活用した「次世代型金融サービス」のコンソーシアムを設立・運営。現在は、エネルギー業界を中心とした経営・ITコンサルティングに従事。ポストIT時代の産業論・社会論についての論文等も多数発表
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
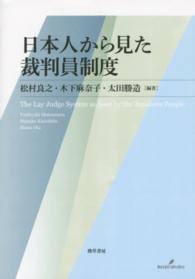
- 和書
- 日本人から見た裁判員制度