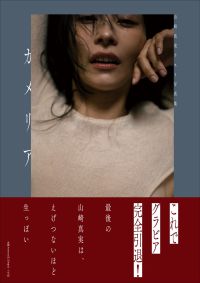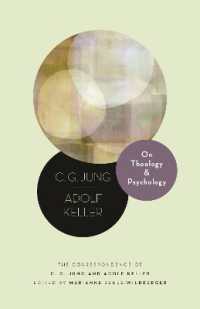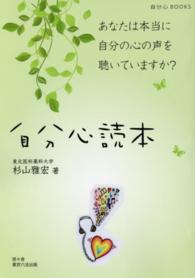- ホーム
- > 和書
- > ビジネス
- > ビジネス教養
- > インターネットビジネス
出版社内容情報
二十一世紀、私たちの暮らしはどのように変わって行くのでしょうか。
こんな話題を投げかけると、「何をとぼけたことをいっているんだ。十年二十年先のことより、今どうしたらリストラされないで済むのか、どうやったら会社が利益を上げられるかを考えるのが先決だ」といった読者の答えが聞こえる気がします。
私は日本人の多くがロマンティストであり、反面、現実主義者ではないかと考えています。未来について「夢想」するのは好きなのですが、その一方で「夢を語るより、今の生活をどうするか」といった方向に思考が強く働いてしまうのです。言葉を換えれば「夢を現実のものにしよう」という貪欲さ、チャレンジ精神に欠けている気がします。
例えば二十世紀から二十一世紀へと、世紀をつなぐ大役を担った森喜朗前首相はe ジャパン構想を高々と掲げましたが、その中身をどれだけ理解して現実の政策に反映させようとしたのか大いに疑問のあるところです。アメリカのビル・クリントン前大統領が、IT (情報技術)のみならず、ナノテクノロジーやE S 細胞といった先端科学技術について、しばしば的確な見解を表明したのとは好対照です。
これは何も政治家だけに限ったことではありません。「近未来学」という学問がありますが、この学問が日本ではなかなか根づかない背景にはそうした現実主義的な国民性が如実に表れている気がします。
未来を語る上で欠かせないのが、科学技術の進歩です。夢を現実にするためには、科学技術の力を借りるよりほかにありません。遠くにいる人と話ができたら、馬よりも速く走れる乗り物があったら、鳥のように空を飛べたら… …こうした人間の夢を科学技術はかなえてきたのです。
一九八〇年代、日本は「電子立国」を標榜し、世界のトップランナーに躍り出ました。
当時不況にあえいでいたアメリカは、その陰でI T 革命を着々と進め、バブル経済の崩壊で機能不全に陥った日本を楽々と引き離してしまいました。そのアメリカに再び追いつき、日本が国際的に強い立場を取り戻すためには、ハード中心である「電子立国」から、I Tはもちろんのことナノテクノロジー、バイオテクノロジーといった先端技術を融合したソフトな「科学技術立国」へと変貌を遂げなければなりません。
ではなぜ、I T 、ナノテクノロジー、バイオテクノロジーが二十一世紀の根幹技術なのでしょうか。
二十世紀、科学技術の進歩は私たちの生活の質を大きく向上させました。ところが、生活の質を向上させた科学技術が、一方で環境破壊の問題やエネルギーや資源の枯渇といった歪みをもたらしたのも事実です。二十一世紀に生きる私たちは、二十世紀の負の遺産をできるだけ解消し、「人間に優しく」、「環境を損なわず」、「エネルギーや資源のむだ遣いをしない」という三つをキーワードにして豊かな地球を取り戻さなければなりません。
その三つのキーワードを実現する省資源省エネルギー型の科学技術がI T 、ナノテクノロジー、バイオテクノロジーなのです。
例えば、私たちの家庭には新聞が毎日届けられます。ところが、印刷された新聞の五%は読まれないままゴミ箱に直行しているそうです。それをエネルギーに換算すれば、毎日膨大なむだを犯しているのです。I T が進展し、「電子新聞」が紙の新聞に取って代われば紙資源の消費が抑えられるだけでなく、そうしたむだも一掃できます。またI T を使った「Bt oC (business to consumer)」や「Bt oB (business to business)」が進めば流通に伴うむだが軽減されます。このように考えるとI T とは省資源省エネルギーを推進する道具にほかならないことがよくわかります。
ナノテクノロジーに関しては、クリントン前大統領が絶妙なたとえ話をしています。
「ナノテクノロジーを使えば、大きな図書館に収められている本の情報すべてを角砂糖ぐらいの大きさに収めることができる」と表現したのです。ナノテクノロジーとは何かがわからなくても、どれだけすばらしい技術であるかはよくわかると思います。
私は、ナノテクノロジーとは生物に学ぶテクノロジーだと考えています。ナノ(一ナノメートルは十億分の一メートル)レベルで「何かをしている」のは現在のところ生物しかいないからです。
例えば、ヒトの遺伝情報(D N A )は三十一億の記号(塩基配列)で書かれています。そのD N A の幅は二ナノメートル、三十一億の文字を並べると長さは一・八~二メートルにもなります。細胞の大きさはだいたい十~百ミクロン(一ミクロンは百万分の一メートル)、核となるとさらに小さくなります。そんな小さいところに三十一億の塩基が収められているのです。ちなみに、私たちの腸内に生息しているバクテリアの大きさは一~四ミクロン、バクテリアよりはるかに小さい存在であるウイルスの標準的な大きさは二十~四百ナノメートルです。
一方、生物の世界がどれだけ省資源省エネルギーであるかは、私たちヒトの活動を見ればよくわかります。ヒトが必要とするエネルギーは一日に三千キロカロリー程度にすぎませんが、そんな少ないエネルギーで歩いたり走ったり考えたりできるのです。
ナノの世界で展開される生物のもつメカニズムを学ぶことによって、ナノサイズの超小型ロボットや「ナノR O M 」のような情報圧縮技術が実現する可能性があります。ナノテクノロジーのモデルとして生物が大きくクローズアップされ、それがバイオテクノロジーと密接に結びついていくといっていいでしょう。
さらにバイオテクノロジーはI T とも密接な関係があります。「ヒトゲノム情報」という言葉を目にする機会が多くなりました。ヒトゲノムとは、人間の体を作るために必要な一セットの遺伝子で、いわば「ヒトのタンパク質の設計図」に相当するものです。ヒトのD N A は約三十一億の記号で書かれていると述べましたが、その三十一億の記号を解読した結果得られた情報がヒトゲノム情報です。ヒトゲノムに秘められた情報が解読され、IT と結びつくことで医療や健康管理に幅広く使われるようになる可能性があります。
このように見ると実は、I T 、ナノテクノロジー、バイオテクノロジーは別々の技術ではなく、省資源省エネルギーという同じ土俵の中で互いにリンクし合っていることがわかります。これがI T 、ナノテクノロジー、バイオテクノロジーの融合が「科学技術立国」の要件になると書いた理由なのです。
では、I T 、ナノテクノロジー、バイオテクノロジーの融合がもたらす未来社会はどのようなものかを描いたのが本書の内容です。参考となるデータは「第七回技術予測調査」の「二十一世紀の科学技術の展望とそのあり方」を下敷きとしました。
「技術予測調査」は文部科学省(旧科学技術庁)科学技術政策研究所が一九七一年から約五年ごとに行っているものです。アンケート形式で調査を行い、アンケート用紙の配布対象者は大学や官民の研究機関の研究者、いわば日本の「頭脳」と呼ぶべき方々です。
二十一世紀に入って初めてとなる今回の調査では、特別にアンケート調査票に総合コメントの記入欄を設け、「二十一世紀中に実現する、あるいは実現してほしい画期的な新技術や、これに伴う生活や社会の根本的な変化など」についてコメントを求めました。回収数は三千八百十三通で、このうち二十一世紀の科学技術に関するコメントが記述されたものは約千二百通ありました。それらのコメントを参考にして同研究所がとりまとめたのが「二十一世紀の科学技術の展望とそのあり方」です。
とりまとめに当たっては、「こうなってほしい」、「こうなるべきだ」、あるいは「こうなってほしくない」というような視点は避け、極力「こういうことが起こり得る」という視点に立って整理されています。
整理に当たっては、二十一世紀の比較的早い時期に実現すると思われるものや、S F 小説にでてくるようなタイムマシン、瞬間移動、反重力装置など現在の科学技術の延長線では実現する可能性がないものは除外されています。見方を換えれば、夢物語の羅列ではなく、「実現性の高い」と判断された未来が描かれています。
二十年先、三十年先の未来がどうなるかを知ることは、単に知的好奇心をみたすだけでなく、人生における大きなチャンスをつかみとることにつながると私は考えています。
私は三十年前にバイオ(生物工学)の時代が来ると予見しました。たまたまかもしれませんが、時代はその通りに動いてきました。なぜ、予見できたかというと、生物には多様で面白い機能がたくさんあることに気がついたからです。しかも、前述したように一部の機能について見ればものすごく効率がいいのです。その生物の多様性と、これから避けては通れない環境問題を重ね合わせたとき、生物を工学に応用する分野が将来は必ず中心になるに違いないという確信が生まれました。
言葉を換えれば、未来を読むことで、「今何をすべきか」がはっきり見えてくるのです。学生や研究者なら、そこにターゲットを絞って研鑽を積むことです。ビジネスマンや経営者なら、そうした未来が現実になったときに、どのようなビジネスチャンスが生まれるかを読みとるのです。
地球に生命が誕生してから約三十五億年になります。その間にたくさんの種が誕生し、数え切れないほどの種が滅んでいきました。忘れてならないことは、強かった種が生き残ったのではなく、環境に順応できる種だけが生き残ったという事実です。
未来という「環境」を予測し、いち早く順応することを考えれば二十一世紀に生き残れるチャンスはそれだけ大きくなります。本書がそうした使われ方をされたら、これに勝る喜びはありません。
最後になりますが、「技術予測調査」からの引用を快諾いただいた科学技術政策研究所科学技術動向研究センターにお礼申し上げます。また本書の執筆を薦めていただいた日刊工業新聞社の鷲野和弘出版局編集企画委員に感謝いたします。
二〇〇一年七月 軽部征夫
はじめに
1章高度先進医療は重大疾患を克服できるか……………………………………17
「高度先進医療」を支えるヒトゲノム………………………………………………18
ビジネスへの思惑が資金と技術を動かした/18
バイオ技術で遅れをとる日本/20
二〇一七年がんは抑制される………………………………………………………23
がんは「偽造」を覚えた反乱分子/2 3
発見相次ぐがん抑制遺伝子/2 5
見えてきた「がん征圧」への道筋/2 9
二〇二五年人間は臓器のスペアを持つ…………………………………………3 3
注目集めるE S 細胞、E G 細胞/3 3
再生臓器ビジネスが脚光を浴びる/3 6
禁断の「クローン人間」作り/4 0
二〇一二年オーダーメード医療が普及する…………………………………4 4
多様性を生むS N P を探せ/4 4
情報収集の有力ツールD N A チップ/4 6
二〇一七年「ミクロの決死圏」が現実に向かう…………………………5 1
一変する外科手術のイメージ/5 1
ナノテク・ロボットが動脈硬化を治療する/5 3
ナノテクは生物に学ぶテクノロジー/5 6
コラム/忍び寄るゲノムカースト/5 9
2章寿命はどこまで延びるのか…………………………………………………………61
今すぐできるゆっくり「老いる」…………………………………………………6 2
ヒトは百二十歳まで生きられる!/6 2
遺伝子研究が解き明かした老化のメカニズム/ 6 4
活性酸素が老化を促進する/6 8
バランスの取れたカロリー制限が老化を抑制する/7 2
ライフスタイルを改善しよう/7 5
二〇一七年ぼけは克服される………………………………………………………8 1
ぼけの二大原因を探る/8 1
「ぼけの遺伝子」を探せ/8 7
脳神経を移植してぼけを治す/8 9
コラム/実現するか犯罪の無い社会/9 4
3章食糧危機は乗り越えられるか………………………………………………………95
二〇一一年安全な遺伝子組み換え食品が普及する………………………9 6
食糧危機が二〇三〇年にやってくる/9 6
組み換えD N A 技術とは/9 9
問われる安全性/1 0 3
二〇一八年光合成技術が食糧問題を解決する……………………………1 0 7
人工葉で食糧を増産する/1 0 7
人工酵素は人工生命体への足がかり/1 0 9
食糧危機回避に向けたさまざまなアプローチ…………………………………1 1 4
牛の肉質をもった豚ができる/1 1 4
マリンバイオの時代がくる/1 1 7
人類は小型化する?/1 2 2
コラム/魅力秘めた人工生命体/1 2 7
4章地球環境は守ることができるか……………………………………………………129
二〇一九年地球温暖化は解決に向かう…………………………………………1 3 0
百年後、平均気温は最大五・八℃上昇する/1 3 0
絶望的になった京都議定書の批准/1 3 3
キメラ植物で環境を保全する/1 3 5
環境対応車の本命・燃料電池車/1 4 1
究極はバイオコミュニケーションの実現/1 4 5
二〇二一年ゼロエミッション社会が到来する……………………………1 4 8
大量生産から資源循環型へ/1 4 8
ナノテクが実現する完全循環型社会/1 5 1
急がれる二十世紀の負の遺産の処理/1 5 5
コラム/「ペットと会話」が実現する/1 5 7
5章エネルギー供給の明日はどうなる………………………………………………159
全世界電力ネットワークが電力問題を解決する……………………………1 6 0
サハラ発・電気エネルギーの時代が来る/1 6 0
課題は超電導ケーブル/1 6 4
エネルギー供給の分散化が始まる……………………………………………………1 6 7
化石燃料は二十一世紀半ばに枯渇する/1 6 7
研究進むバイオマス/1 7 0
移動手段は陸から空へ……………………………………………………………………1 7 3
クリック・アンド・モルタルの先にあるもの/1 7 3
超電導ハイブリッドカー/1 7 7
コラム/世界言語が統一される/1 7 9
6章ロボットはヒトをどこまで助けられるか……………………………………181
コンピューターが「脳」を超える日………………………………………………1 8 2
ディープ・ブルーの歴史的勝利の意味するところ/ 1 8 2
驚くべき脳の情報量/1 8 7
バイオコンピューターとニューロコンピューター/1 9 0
「アトム」が家庭にやって来る…………………………………………………………1 9 5
ロボット技術の限界と可能性/1 9 5
「あなた好み」のロボットが誕生する/1 9 8
義手、義足が生体を超える/2 0 3
資料/重要度の高い上位100課題…………………………………………………………2 0 8
内容説明
日本の頭脳1200人が答えた「第7回技術予測調査」を読み解く!進学に就職にビジネスに、これだけは知っておきたい“実現性の高い未来”。この1冊が明日からのあなたの行動を変える。巻末参考資料には、「重要度の高い上位100課題」付き。
目次
1章 高度先進医療は重大疾患を克服できるか
2章 寿命はどこまで延びるのか
3章 食糧危機は乗り越えられるか
4章 地球環境は守ることができるか
5章 エネルギー供給の明日はどうなる
6章 ロボットはヒトをどこまで助けられるか
著者等紹介
軽部征夫[カルベイサオ]
1942年、東京都生まれ。東京工業大学大学院理工学研究科博士課程修了。東京工業大学資源化学研究所教授を経て、88年4月、東京大学先端科学技術研究センター教授。99年4月、東京大学国際産学共同研究センター長。2001年から同教授、放送大学客員教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。