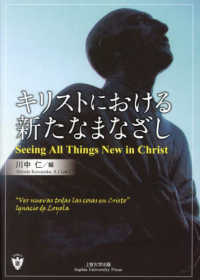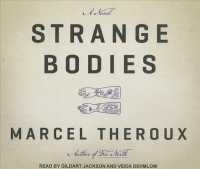出版社内容情報
《内容》 複雑化した肝疾患診療に対し,一般医家はどのように対処したらよいかについて主に肝機能検査の面から取り上げた.検査の本来持っている意味,病態との関わり,他の検査との関連から,病態の把握・診断,そしてどのような疾患ではどのような検査を行うか,さらに,特殊な病態を持つ症例(応用編)ではどのように検査を組み立て,どのように理解すればよいかを,平易に記述・解説した.
《目次》
【主要目次】
1.肝機能検査とは
1 肝細胞障害
2 肝細胞の合成障害
3 解毒・代謝障害
4 胆汁うっ滞
5 膠質反応
6 肝循環動態
7 肝性脳症の検査
8 金属代謝障害
9 免疫学的検査
10 肝炎ウイルス検査
2.肝機能検査
1.トランスアミナーゼ
2.ビリルビン
3.アルカリホスファターゼ
4.ロイシンアミノペプチダーゼ
5.乳酸脱水素酵素
6.コレステロール
7.コリンエステラーゼ
8.空腹時血糖値
9.血清蛋白分画
10.膠質反応
11.Rapid turnover protein
12.免疫グロブリン
13.出血傾向と凝固因子
14.ICG試験
3.肝疾患と肝機能検査
A.病気の原因を知る検査
1.ウイルス肝炎とウイルスマーカー
2.自己免疫性肝疾患と自己抗体
3.糖代謝異常と肝疾患
4.金属代謝異常と肝疾患
5.線維化マーカーと肝疾患
B.病態を知るための肝機能検査
1.劇症肝炎
2.急性肝炎
3.慢性肝炎
4.肝硬変
5.肝細胞癌
6.脂肪肝
7.胆汁うっ滞
A.肝内胆汁うっ滞
B.体質性黄疸
C.閉塞性黄疸
4.肝機能検査と画像診断,組織診断との対比
1.劇症肝炎
2.急性肝炎
3.慢性肝炎
4.肝硬変
5.肝細胞癌
6.脂肪肝
7.食道静脈瘤
5.応用編:次の症例をどう考えるか
1.劇症肝炎
2.HBe抗体陽性のB型慢性肝炎
3.インターフェロン抵抗性C型慢性肝炎
4.肝性脳症をきたした肝硬変
内容説明
本書はただ単に肝機能検査を紹介する本ではなく、肝機能検査から目の前の肝疾患患者の病態をどう読むかに焦点を当てたものである。
目次
1 肝機能検査とは
2 肝機能検査
3 肝疾患と肝機能検査(病気の原因を知る検査;病態を知るための肝機能検査)
4 肝機能検査と画像診断、組織診断との対比
5 応用編―次の症例をどう考えるか
著者等紹介
沖田極[オキタキワム]
山口大学医学部第一内科消化器病態内科学教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 和書
- そらちむらのだいぼうけん