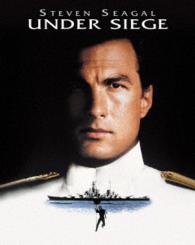内容説明
探偵小説における論理とは何か?不可解な謎に対する筋の通った合理的な説明が与えられたとき、「論理的」であると探偵小説読者は感じる。しかし、ここでいう「論理」とは論理学でいう「論理」のみならず、別の要素が介在している。探偵小説における「論理」を捉えるためには、遡って論理学の「論理」を捉え返す必要がある。ラッセル論理学に基づき、エラリー・クイーンなどの探偵小説における論理を論考する。新しい時代のミステリとコードの変容の係わりを考察し、新しい時代への対応法を大胆に提言する。
目次
第1部 現代論理学の形成と動向―ラッセルの論理哲学を中心として(ロゴスから論理へ;フレーゲとラッセルの論理学的革新;ラッセルの記述理論の意義 ほか)
第2部 探偵小説の論理と公理(ホームズ物語と「モルグ街」の論理;詭弁論理とチェスタトンの逆説論理;ヴァン・ダインによる探偵小説二十則 ほか)
第3部 ロゴスコードの変容と論理物語の新潮流(パウル・ティリヒの別の箱―新時代の物語受容の変化についての一考察の試み;ロゴスコードの変質と現代の探偵小説;モナドロギーからの西尾維新へのアプローチ ほか)
著者等紹介
小森健太朗[コモリケンタロウ]
1965年大阪生まれ。東京大学文学部哲学科卒。82年『ローウェル城の密室』が第二八回江戸川乱歩賞最終候補となる。94年『コミケ殺人事件』でデビュー(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- ヤクザの俺が高校生になった 第23話 …
-
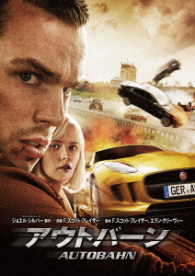
- DVD
- アウトバーン