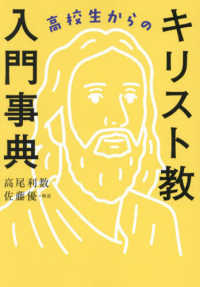出版社内容情報
《内容》 「脳卒中急性期患者データベース」は,わが国における脳卒中診療のEBM確立を目的として平成11年度に構築され,現在,50施設,8000例のデータベースに成長し,すでに院内LANに組み込んで運用している病院もあります.本書はこのデータバンクで得られた最新診療エビデンスを収載し,第一線の医師,ならびに医薬品関係者にとって必須のデータブックとなっています.併せて,日本初のデータバンク構築の意義,将来構想をも記載し,今後のさらなるエビデンス集積に寄与することを願って編集・執筆されています.
《目次》
第1部 脳卒中急性期患者データベースの概要
1. 脳卒中急性期患者データベース開発経緯
2. 脳卒中急性期患者データベースにおける標準化項目
3. 脳卒中急性期患者データベース入力画面
4. 脳梗塞・脳出血患者の脳卒中スケールを用いた重症度、予後の検討
第2部 脳卒中診療のエビデンス
1. 急性期脳卒中の実態
a. 病型別・年代別・性別頻度(欧米、アジアとの比較)
b. 発症の週内・日内変動と、病型別にみた発症-来院時間
c. 病型別入院方法と発症-来院時間、在院日数、退院時予後
d. 病型別神経症状、予後との関係
e. 病型ごとに比較した危険因子、重症度と予後
f. 病型別にみた脳卒中の地域間比較
2. 脳梗塞の実態
a. 脳梗塞病型の時代的推移と国際比較(久山町、欧米との比較)
b. 病型別にみた脳梗塞危険因子の年代別・性別頻度
c. 脳梗塞、一過性脳虚血発作と心房細動
d. 病型別にみた脳梗塞の入院後進行と入院後再発
e. 出血性梗塞:頻度・重症度・血栓溶解療法と予後
f. 脳梗塞の重症度・予後と血圧変化
g. 病型別にみた脳血管狭窄性病変と重症度・予後
h. 通常治療の治療方法別頻度と経過・転帰の比較
i. 各種併用療法の実態----有効性と使い分け
j. 脳梗塞急性期の抗血小板・抗凝固療法と予後の病型別解析
k. オザグレル投与群とアルガトロバン投与群の予後解析
l. オザグレルと脳保護薬(エダラボン)併用療法
m. 抗トロンビン薬と脳保護薬(エダラボン)併用療法
n. ウロキナーゼ6万単位/日点滴の有用性について
o. 抗トロンビン薬(アルガトロパン)・脳保護薬(エダラボン)と抗血小板薬の併用療法
p. 超急性期脳梗塞における血栓溶解療法の実態
q. 超急性期脳梗塞における血栓溶解療法と脳保護薬エダラボンの併用効果
r. 血栓溶解療法の予後に関するCase control studyと多変量解析
s. 外科的治療の頻度と予後
3. 脳出血の実態
a. 脳出血の発症動態と臨床像
b. 脳出血の治療法別予後比較
c. 脳出血重症度とPVH・脳卒中既往歴、抗血小板抗凝固薬使用歴
d. 脳出血重症度と血圧変化・予後
4. くも膜下出血の実態
a. 重症度分類と部位別・CT所見別頻度
b. くも膜下出血の解析--頻度、転帰、開頭手術成績、ISATとの比較
c. くも膜下出血の予後に関与する因子
d. 脳血管攣縮ー脳動脈瘤の部位・重症度・危険因子と予後
第3部 脳卒中急性期患者データベースの付加価値
1. 院内LANによる継続入力とデータの活用
2. 脳卒中データベースによる治療指針作成・検証
3. 脳卒中者データベースの病棟医教育効果
内容説明
日本初の脳卒中データバンクで脳卒中の実態が明らかに。全国50施設、患者数8000人のデータ解析から分かったことは。
目次
第1部 脳卒中急性期患者データベースの概要(脳卒中急性期患者データベース開発経緯;脳卒中急性期患者データベースにおける標準化項目;脳卒中急性期患者データベース入力画面;脳梗塞・脳出血患者の脳卒中スケールを用いた重症度、予後の検討)
第2部 脳卒中診療のエビデンス(急性期脳卒中の実態;脳梗塞の実態;脳出血の実態;くも膜下出血の実態)
第3部 脳卒中急性期患者データベースの付加価値(院内LANによる継続入力とデータの活用;脳卒中データベースによる治療指針作成・検証;脳卒中データベースの病棟医教育効果)
著者等紹介
小林祥泰[コバヤシショウタイ]
島根医科大学第3内科
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。