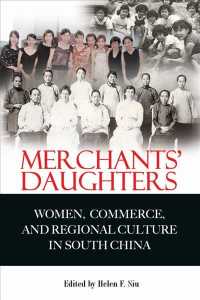内容説明
「原価を知りたい」、さらには「実際に計算したい」という欲求に応えるためにどのような本がいいのか、そんな観点からつくり上げたのが本書です。
目次
序章 本書のねらい
第1章 原価計算の目的と原価計算基準
第2章 原価計算の要素
第3章 原価の製品別計算―実際原価計算
第4章 標準原価計算
第5章 新しい原価計算の視点
著者等紹介
関浩一郎[セキコウイチロウ]
新日本有限責任監査法人公認会計士。米国公認会計士。重工業メーカーでの営業職を経験ののち、平成11年、太田昭和監査法人(現・新日本有限責任監査法人)入所。以降、食品メーカー、自動車メーカー等、主に製造業を中心に国内上場会社の会計監査に従事
菅野貴弘[スガノタカヒロ]
新日本有限責任監査法人公認会計士。平成13年、新日本監査法人(現・新日本有限責任監査法人)入所。以降、食品メーカー、自動車メーカー等、主に製造業を中心に国内上場会社の会計監査に従事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
#26 Kの字
4
製造原価の教科書として、優秀。ただし一定の実務レベルにあれば、改善を期待して読むと、期待はずれかも2023/09/24
RITZ
2
原価計算に関する知識が簿記試験程度しか無いことに気付いたので、肉付けする為に読んでみました。 分かりやすいので、試験勉強をしていた当時に並行して読めていればもっと効率が良かったかも。 良著です。2017/08/19
カラクリ
0
原価計算、特に標準原価計算が何なのか理解するために読んだ。標準原価、原価標準、基準原価など似通った言葉があり、戸惑ったがおおむね理解できた。あとは、知識の構造化を行い、図にて整理すれば知識が定着するので、標準原価計算や、間接費の配賦に関するまとめ図を作成し、ブログに投稿することにする。2016/10/27
rohi
0
原価計算の知識を整理するために読んだ。タイトル通り「本質と実務」に納得感を持てる良書。例えば、様々な製品別原価計算法は根本的には「投入されたインプットをいかにアウトプットに振り分けるか」の違いで、実際そこに着目すれば単純化して整理ができる。実務の点では、補助部門の配賦計算法も実務上は簡便性を優先させ「最も理論的な相互配賦法ではなく、最も不正確な直接配賦法が用いられる場合がほとんど」とあり実務者として非常に納得感が得られる。ルールの説明 だけでなく使い方を適切に指南してくれる。 ★★★★☆(買う価値あり)2021/07/19
登戸ヤスタツ
0
簿記一級の参考本として。前半の原価計算のそもそも話は教科書・論文的な書き口が難解に感じたけど、後半はサラリーマンとしては身近な人事評価的な話も絡めてとっつきやすかったので、ビギナーから原価計算の理解を深めるつなぎには打ってつけの一冊でした。前知識として製造原価計算書から財務3表くらいの話は押さえてから読み始めたのが良かったかな。2018/06/18
-
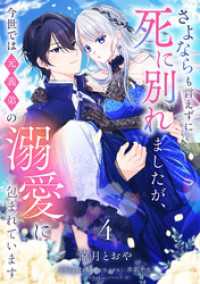
- 電子書籍
- さよならも言えずに死に別れましたが、今…
-

- 洋書
- VOIX CREOLES