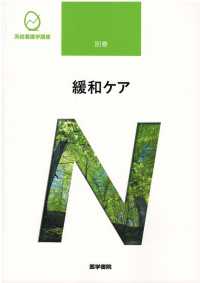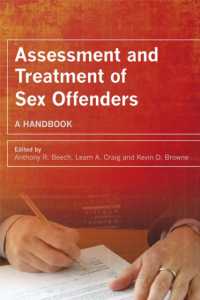内容説明
1980年代以降の円高は「天井」なしに持続的に進み、不規則変動は国内立地から合理性を奪った。本書は、円高が総合電機のポートフォリオを劣化させ、産業組織を解体した事実を明らかにし、財務省・日本銀行一体の長期為替安定スキームの必要を世に問う。
目次
第1部 総合電機産業の凋落をめぐる議論(日本の総合電機産業の盛衰;経営学による総合電機衰退論 ほか)
第2部 持続的円高と空洞化の基本パターンの成立(1980年代後半「海外生産シフトと企業構造の変質」;国内空洞化が高付加価値品に拡大した1990年代)
第3部 総合電機産業の産業組織解体(親企業と協力企業群の協業関係の解体;国内工場の量産機能喪失と「ものづくり基盤」の変質―セル生産方式と「マザー工場」化)
第4部 2000年代の戦略不奏功と事業基盤再構築の明暗(総合電機産業の「失われた10年」;半導体敗戦に続く液晶敗戦―海外移転できないもの ほか)
エピローグ(総合電機産業から複合電機産業へ―道は幽かに見えるが険しく長い;総合電機産業の凋落と「国内空洞化」―国民の雇用基盤をどこに求めるのか ほか)
著者等紹介
榎本俊一[エノモトシュンイチ]
1990年、東京大学法学部卒業後、通商産業省入省。1995~97年、米国コロンビア大学ロースクール留学、コンピュータ・ソフトウェアの特許性及びインターネット上の知的財産権保護、臓器移植に関する法的問題に関する研究等に従事。2010~11年に東北大学大学院法学研究科教授(現代日本経済・経済政策)として、1990年代以降のマクロ政策展開と政治社会システムの変質の分析、内外マクロ環境の変貌の中での企業経営及び企業戦略の展開に関する講義研究を行う(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
-
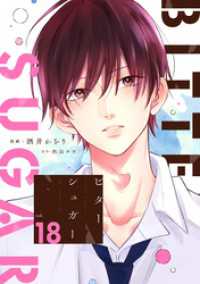
- 電子書籍
- ビターシュガー 分冊版 18 KoiY…
-
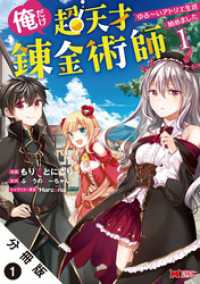
- 電子書籍
- 俺だけ超天才錬金術師 ゆる~いアトリエ…