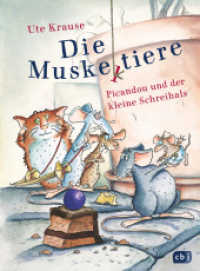出版社内容情報
序
戦後の日本経済の発展を支えた様々な要因すなわち終身雇用制,年功序列制,企業内組合などは,日本人の精神風土に適合する「経済成長装置」といえるものであった。
ところが,日本経済のターゲットが「量」から「質」へ転換されるようになると,企業の求める人材も,組織の和を醸成する協調性から,時代環境の変化に柔軟かつ敏速に対応できるという点に力点が置かれるようになった。すなわち,21世紀の企業経営は「グローバル社会」,「高度情報通信ネットワーク社会」,「環境調和型社会」,および「高齢化社会」といった社会の流れの中で,いかに創造性を発揮して,新しいイメージを描くかが課題となる。特に,新しい経営スタイルを考えるには,「高度情報通信ネットワーク社会」のインパクトに注目すべきであろう。この社会においては,イントラネットやエクストラネットにより,上と下,内と外の情報格差がなくなる。然らば,トップは,ネットワークを通じた「1人対多数」のコミュニケーションをこなし,指導性を発揮できなければ,地位を失う。一九「グローバル社会」,「環境調和型社会」および「高齢化社会」への対応も大きな課題である。経団連は,2020年ビジョン「魅力ある日本-創造への責任」において,「企業は自己責任原則と厳しい企業倫理の下で自由に活動し,国民の真の豊かさに貢献する商品・サービスの開発,提供や経営を行っている」とした理想的企業像を描いている。筆者の理解では,このような時代背景において,「木を見て森を見ず」的人材,すなわち製品の開発技術力は有しているが企業の仕組みや消費者の製品ニーズに疎い人材,あるいは語学カはあるが情報機器操作能力に疎い人材なども評価されなくなり,いわゆる「ストラティジスト」のみが企業側から評価されるようになると考える。
ストラティジストとは,簡潔に表現すれば,将来の企業内外環境の変化を予想し,また,根本的にはスペシャリストであるが環境の変化に応じて他のスペシャリストの代替をも可能にするような柔軟性,予見性および創造性に富む人材のことである。このような人材には具体的に,柔軟な思考力,鋭敏な感受性,および深遠な洞察力が必要であると考える。
本書の目的は,このようなストラティジスト育成の勧点から,営利組織の代表である企業の経営管理論の考察のみならず,この理論を典型的な非営利組織である病院の経営管理論へ適用することについての妥当性の検証をも同時に行うことにある。換言すれば,全ての組織体に普遍的に成立・妥当する一般原理ないし一般理論を形成する普遍経営学の構築に些少の貢献を行うことに目的がある。
また,本書の構成は,まず,経営学とその1対象である企業を巨視的にみる。
それらは,経営学の定義と企業の法的・経済的・社会的意味である。次に,企栄における経営者の職能と管理者の職能を明確にする。それは,大企業における経営の機能,大企業における管理の機能,大企業における経営管理技術,および中小企業の経営管理機能からなる。さらに,非営利組織の典型とされる病院における経営者の職能と管理者の職能を明確にする。これには,医療経営学,医療組織論,医療経営戦略給および医療人事管理論がある。最後に,営利,非営利を問わず適用できる普遍経営論あるいは普遍組織論への進展を若干試みた普遍経営学への小歩がある。
なお,本書の原稿校正に当っては,東京電機大学出版局の橘内文女史に多大なる助力を賜り,深く感謝する次第である。
第2版にあたって
殺伐とし,何ともいえない閉塞感を覚える現代であるが,この思いは,企業の経営者も同じであろうと想像する。
南宋の朱新仲が,“人生の5計”を説いている。それらは,“生計”,“身計”,“家計”,“老計”および“死計”である。まず“生計”とは,「自分が天から授かった使命を考える」,“身計”とは,「社会にどのように貢献するかを考える」,“家計”とは,「家庭をいかに営むかを考える」,“老計”とは,「いかなる価値をもって老いるかを考える」,最後の“死計”とは,「いかに死ぬのかを考える」ことを意味する。
これについて,安岡正篤は,この“人生の5計”が不透明な現代において重要な意味をなすとする。筆者の解釈によると,事前に5計があれば,有意義な内面生活をもっているので,外面的な問題に一喜一憂せず,何があっても平常どおり執務できる。
これにつけ,1980年代の企業経営者は,“JAPAN AS NO.1”であったが,1990年代から現代に至るまで,経営者は“AMERICA AS NO.1”である。君子の豹変ではないが,経済環境の変化があったにせよ,なぜこのように態度が一変するのか再考する必要性があると考えられる。経営者が経営の精髄を消化せず,経営を実行していることも解の1つをなすと考える。
このような問題意識から,“経営の精髄”について考慮すると,企業の経営にのみ適用できる経営学でなく,他の組織にも適用できる経営学こそ“経営学の精髄”であるといえ,本書で,その構築の一歩を形成することを試みる。
本書の構成は,まず,第Ⅰ部企業経営学総論で,経営学の定義と企業の法的,経済的,経営的および社会的意味を考える。それらは,第1章経営学の定義,第2章経営学史,第3章企業形態論,第4章会社設立の手続き,第5章日本的経営論,第6章21世紀の企業社会論から構成される。
次に,第Ⅱ部企業経営学各論では,将来の経営者・管理者として企業に評価される人材を育成することを目的とし,主として大企業の経営者・管理者の職能に重点を置き,大企業の経営機能,管理機能および経営管理技術,中小企業の経営管理職能について論及する。これらは,経営者の職能である第7章経営組織論,第8章経営戦略論,第9章社会的責任論,経営管理者職能である第10章経営意志決定論,第11章経営管理論,第12章経営分析(理論編),第13章経営分析(実践編),および管理者の職能である第14章R&D(研究開発)管理論,第15章 人的資源管理論および第16章情報管理論,第17章生産管理論,である。また,大企業の経営管理の範囲を地理的・経済的に拡張し,第18章国際経営論(理論編),第19章国際経営論(実践編),第20章中小企業論,第21章 ベンチャービジネスをも取り扱う。
さらに,第Ⅲ部医療経営学総論,および第Ⅳ部医療経営学各論では,記述の営利組織のみならずすべての組織体に普遍的に成立・妥当する一般理論である普遍経営学の構築に若干の貢献を行うため,典型的な非営利組織である医療機関(病院)の経営に関する外延と内包について言及する。また,医療経営学を学ぶ目的としては,1993年のWTOウルグアイランド,病院の自由化協定が締結されたことを受けて,わが国においても,早晩,医療の規制緩和が確実に進むことが予想される。その結果として,外資も加わり,多くの医療関連ビジネスが生まれる可能性が高くなっている。例えば,病院・診療所専門の経営コンサルティング,患者への病院・診察所紹介,電子カルテによる診療情報管理,遠隔診断支援,遠隔健康管理などのビジネスがあげられる。また,医療保険産業の市場規模は,自動車産業の16兆6千億円(平成10年)よりはるかに巨大で,平成11年で30兆9千億円を示し,高齢化と相伴って,さらに増加する見込みである。このように,今後急増が見込まれる巨大なマーケットである医療および医療関連サービスの求めている人材を養成することにその目的がある。
第Ⅲ部医療経営学では,医療経営学の外延である第22章医療経営学概論,病院の経営者の仕事として,第23章病院組織概論,第24章医療組織特殊論,第25章病院経営戦略論,第26章病院経営分析,第27章病院のTQMモデル,第28章医療リスクマネジメント,第Ⅳ部医療管理学では,管理者の仕事については第29章病院管理学概論,第30章病院長のリーダーシップ,第31章看護管理職のリーダーシップ,第32章看護管理論,また,各部門管理者に共通の業務として,病院のTQMモデルの下で行う第33章医療機関のTQM手法とCQIツールを記述している。
最後に,第Ⅴ部普遍経営学への小歩では,営利組織である企業,非営利組織であるNPO,法人,学校,官庁,病院などを含めすべての組織体に適用できる普遍経営論,普遍管理論および普遍組織論への進展を若干試みた第34章普遍経営学への小歩がある。
なお,出版事情厳しい中,本書の出版に協力していただいた東京電機大学出版局の長江光男局長,植村八潮課長に深く感謝する。また,本書の現高校性に当たって,当該出版局の松崎真理女史には多大なる叱咤激励と助力を賜り,衷心より謝意を表する次第である。
2002年新春
岩森龍夫
第Ⅰ部 企業経営学総論
第1章 経営学の定義
第2章 経営学史
第3章 企業形態論
第4章 会社設立の手続き
第5章 日本的経営論
第6章 21世紀の企業社会論
第Ⅱ部 企業経営学各論
第7章 経営組織論
第8章 経営戦略論
第9章 社会的責任論
第10章 経営意志決定論
第11章 経営管理論
第12章 経営分析(理論編)
第13章 経営分析(実践編)
第14章 R&D(研究開発)管理論
第15章 人的資源管理論
第16章 情報管理論
第17章 生産管理論
第18章 国際経営論(理論編)
第19章 国際経営論(実践編)
第20章 中小企業論
第21章 ベンチャービジネス論
第Ⅲ部 医療経営学
第22章 医療経営学概論
第23章 病院組織概論
第24章 医療組織特殊論
第25章 病院経営戦略論
第26章 病院経営分析
第27章 病院のTQMモデル
第28章 医療リスクマネジメント
第Ⅳ部 医療管理学
第29章 病院管理学概論
第30章 病院長のリーダーシップ
第31章 看護管理職のリーダーシップ
第32章 看護管理論
第33章 医療機関のTQM手法とCQIツール
第Ⅴ部 普遍経営学への小歩
第34章 普遍経営学への小歩
索 引
内容説明
本書は、ストラティジスト育成の観点から、営利組織の代表である企業の経営管理論の考察のみならず、この理論を典型的な非営利組織である病院の経営管理論へ適用することについての妥当性の検証をも同時に行うものである。
目次
第1部 企業経営学総論(経営学の定義;経営学史 ほか)
第2部 企業経営学各論(経営組織論;経営戦略論 ほか)
第3部 医療経営学(医療経営学概論;病院組織概論 ほか)
第4部 医療管理学(病院管理学概論;病院長のリーダーシップ ほか)
第5部 普遍経営学への小歩
著者等紹介
岩森龍夫[イワモリタツオ]
現職は、東京電機大学工学部教授、芝浦工業大学工学部講師、早稲田大学特別研究員、日本ベンチャー学会理事他。1952年広島県広島市生まれ。早稲田大学大学院博士課程満期終了。国立保健医療科学院(厚生労働省)・厚生技官、米国ハーバード公衆衛生大学院客員研究員などを経て現職
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 和書
- 微分方程式 - 工学基礎