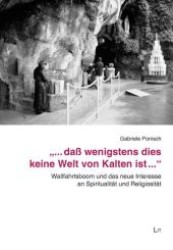出版社内容情報
本教科書は理工学の基礎となる物理学の初頭教育から応用力を高めるまでを念頭において書きまとめた。この力学編は物理現象の本質を記述するに当たって,ベクトルの扱いと微分積分が必要となり,数学的な素養を身に付けながらの物理学の講義内容となっている。従って初学年の諸君にとっては初めての数学的手法が随所に現れることになろう。しかし丁寧な解説を付けたので少々の努力で総てを理解することができよう。
本書の特色としてMathematicaを用いた力学的運動の計算機シュミレーションを随所に取り入れ,力学法則と具体的な運動をつぶさに把握できるようにした。こうしたシュミレーションは,解析的に解を求めること無しに物体の運動を調べ図示できるので,学力のある諸君にとっては解析解のチェックに利用できて便利である。また単に複雑な運動系を調べることに用いても,簡単にその運動が図示されるため,数学的な困難を感じずに物理現象を楽しむことができる。さらに物理の苦手な諸君にとっては,同じアルゴリズムで書いたプログラミングで多様にシュミレーションが楽しめるので,物理現象の本質は嫌でも理解できるようになろう。
力学的物理現象は,冒頭のページにも書いた様に,物理空間の性質を述べた3つの法則を理解すればその総てを把握することができる。運動の計算機シュミレーションが通り一辺倒のプログラミングで済むのはそのためである。従って間違った思考の道筋に入らなければ,力学はいたって簡単な学問であり矛盾の無い世界と言える。ぜひ間違った思考の道筋に入らないように順序良く力学を学んで頂きたい。力学現象は自然現象として,日常生活の中で,体で会得していることが多い。幼いころからのささいな思い違いが理解を妨げることもあろう。バーチャル・リアリティなる空想画の悪影響も残っていよう。まず3つの保存則をしっかり身につけた上で,各基本法則を矛盾無く理解していくことが肝心である。諸君が本書になじみ難い場合は原康夫先生などの書かれた教科書をもう一冊入手し,並べ読みをすると良い。私の経験であるが,どんな学問でも教科書は数を増やすほど学び易い。
問題を解くことは理解したことをチェックしさらに理解を深めるために非常に大切である。本書の段落ごとの問題は,数は少ないが本質的な所を問題のテーマにしているので,ぜひ全部を解答して頂きたい。本書はコマの首振りまで理解することを目標に書きまとめられている。ここまでの問題を解く知識と思考力は理工系大学生の基本的な素養として不可欠なものと考える。
本書は篠原正三先生の書かれた「物理学概論」を基礎とし現在風の内容にして執筆したものです。私が院生から教員に至るまでの間篠原先生から一貫して教えて頂いたことは物理学の透明感でした。学ぶ程に,高い山から透明な空気を通して遠く景色を見渡すような心地よさを覚えました。ここに篠原正三先生への感謝の意を心に込めて記します。
物理で透明感を得るには,ある程度の難しい数学も理解する必要が有りますが,無駄の無い思考過程を会得することが肝心と思います。本書をして皆さんに篠原先生の透明感が少しでも伝えられれば幸いです。
2000年8月
著者
第1章 空間座標とベクトル量
1.1 三次元直交座表系と位置ベクトル
1.三次元空間ベクトル
1.2 ベクトルの演算
1.ベクトルの定義
2.ベクトルの和
3.ベクトルの内積
4.ベクトルの外積
5.ベクトル計算の公式
1.3 力とベクトル
1.力の釣り合い
2.力の移動
1.4 位置ベクトル量の平均と積分
1.面積積分,体積積分
第2章 ベクトルの時間変化
2.1 位置ベクトルの時間変化
2.2 極座標表現
2.3 ベクトルの平面内の変化
2.4 極座標表現でのベクトルの時間変化
第3章 質点系の運動と力学法則
3.1 質量と重量
3.2 重心の位置ベクトル
3.3 物体の直進運動と運動量保存の法則
1.運動量と保存則
2.運動の三法則
3.4 物体の回転運動と角運動量保存の法則
1.角運動量と保存則
2.円錐振り子
3.惑星の運動
3.5 エネルギーとエネルギー保存の法則
1.エネルギーと保存則
2.位置エネルギーの色々
3.中心力の場におけるエネルギー
4.エネルギーと力
3.6 最小作用の原理
1.ラグラジアンと最小作用の原理
第4章 質点系の衝突,摩擦,振動
4.1 物体の衝突
1.一次元衝突
2.二次元衝突
3.ロケット燃料噴射
4.ポテンシャル場の衝突
4.2 分子動力学法
4.3 摩擦
1.静止摩擦と動摩擦
2.斜面と滑り
3.速度に比例する抗力
4.4 物体の振動
1.ばね振動
2.振り子の振動
4.5 条件のある振動
1.摩擦振動
2.位置を拘束された運動
3.減衰振動
4.強制振動
第5章 剛体の釣り合い
5.1 釣り合いの条件
1.並進力の釣り合い
2.回転力の釣り合い
5.2 弾性と歪み
1.棒のたわみ
2.ポアッソン比
3.線のねじれ
4.体積弾性率
5.ヤング率,剛性率,体積弾性率
6.物性の変形
第6章 剛体の運動
6.1 剛体の並進運動と回転運動
1.剛体の重心
2.並進運動と回転運動
3.角運動量と慣性モーメント
4.トルクと角運動量変化
5.回転エネルギー
6.2 慣性モーメントのいろいろ
1.回転体の慣性モーメント
2.細い棒の慣性モーメント
3.円盤の慣性モーメント
4.直交軸の定理
5.並行軸の定理
6.色々な慣性モーメント
7.球殻と球の慣性モーメント
6.3 剛体の運動
1.剛体の衝突と運動
2.剛体振り子
3.スケートのスピン
4.こまの首振り運動
5.束縛された剛体の運動
6.剛体運動のシミュレーション
解答
物理定数表/天文部
物理/科学部
物理科学史
索引
内容説明
本書の特色としてMathematicaを用いた力学的運動の計算機シュミレーションを随所に取り入れ、力学法則と具体的な運動をつぶさに把握できるようにした。こうしたシミュレーションは、解析的に解を求めること無しに物体の運動を調べ図示できるので、学力のある諸君にとっては解析解のチェックに利用できて便利である。また単に複雑な運動系を調べることに用いても、簡単にその運動が図示されるため、数学的な困難を感じずに物理現象を楽しむことができる。さらに物理の苦手な諸君にとっては、同じアルゴリズムで書いたプログラミングで多様にシュミレーションが楽しめるので、物理現象の本質は嫌でも理解できるようになる。
目次
第1章 空間座標とベクトル量
第2章 ベクトルの時間変化
第3章 質点系の運動と力学法則
第4章 質点系の衝突、摩擦、振動
第5章 剛体の釣り合い
第6章 剛体の運動
著者等紹介
小畑修二[オバタシュウジ]
東京電機大学理工学部助教授。博士(工学)。研究分野は計算物理学(不規則性材料の電子構造計算)。日本物理学会所属
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。