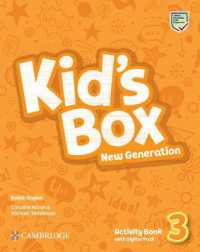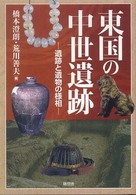出版社内容情報
この本は,工科系大学の人文社会科目として開講されている『教育工学』のテキストとして作られた。「一体この科目の名称とこの本の内容がどのような関わりがあるのか。」という疑問は,この本全体で答えなければならないほどの重要な問いである。
しかし,それでは答えにならないので,かいつまんで言えば,教育工学が依拠していた当時の学習心理学は,いまや人工知能の研究によって発達した認知科学によって大きく塗り替えられている。
パソコン上で人工知能のまねごとをしてみることは,その意味重要であろう。まず初めに,へーえこんなに人間をまねることができるんだと感心し,また,そのカラクリの意外な単純さにびっくりし,そして,しばらくすると人間と違うところが見えてくる。少なくとも私にとってLogoを使ったAnimalと出会ったときはそのような経験をした。これは実は,人間の「知」に対する経験でもあったのだ。
この本は,Aminalを理解できることを目標に,Logoの基本テクニックをトレーニングしていく。1章は入門的な内容,2章にはその実力養成のために(問0-1)という形で問が数多く含まれている。その方面の力を付けようとする読者は,前半の問になるべく多く挑戦していただきたい。
しかし必ずしもそうでない方は,時には読みとばしていただいてもよい。必要になったときに索引などを介して戻っていただければ充分だろう。特に,2章2.5以降の応用例は,かなり豊富な内容を含んでいる。問にすることによって豊富な内容をコンパクトに収めようとしたのが,正直に言えば,著者の意図である。ご自分の興味によってつまみ食いをしていただきたい。3章,4章では具体的プログラムが利用の局面に応じて紹介されている。そして5章と6章で,前述の学習心理学の塗り替えられる様子が描かれ,7章で,Logoを使ったプログラムでその場面の追体験を狙っている。
Logoという教育用のプログラム言語も,このような教育工学の新しい流れの中の産物である。まるでエッシャーのある作品のように,手を描いている手をもとの手が描いている。このような循環的連鎖を本では前述のように描いている。工科系の学生が,そしてちょっと背伸びした高校生が,実際のプログラムの腕を研きながら人間の「知」を体験的に考察できる機会を本書が提供できるならば言外の喜びである。
なお,Logoにはいくつかの処理系があるが,Logo Writer for Windowsを標準として記述し処理系による異同を記録へ記した。また,Pc Logoは異同が利用者にとって不安に思える程度に大きいので,Pc Logo(Terrapin Logo)として適宜本文中にも註を付けた。
1 Logoとは何か
1.1 Logoの特徴
1.2 ロゴライターを使う
1.3 パラメータ
1.4 関数型言語と画面への書き込み
1.5 条件分岐
1.6 Mainはいらない
2 リストと再帰的定義
2.1 リストとは何か
2.2 文字列処理
2.3 再帰的定義の練習
2.4 再帰的定義に関する注意
2.4.1 ユークリッドの互除法
2.4.2 フィボナッチ数列を求める速さ
2.5 リストの応用例
2.5.1 数学での応用
有理数
整式と巨大数
Runと数列
集合と順列
行列
2.5.2 アニマルというプログラム
3 亀を動かすテクニック
3.1 等加速運動
3.2 二体問題
3.3 利用者の入力
3.4 ダイナタートル
3.5 曲線を描く
3.5.1 デカルトの正葉線
3.5.2 包絡線
3.5.3 漸化式であらわされた数列の収束
4 すこし発展した話題
4.1 コッホ曲線とツリー
4.2 ポアンソの図形
4.3 複素写像
4.4 ロジスティック曲線からカオスまで
5 認知科学前史
5.1 教育に工学が関与した3つの形態
5.2 ティーチング・マシン
5.3 工学的手法の教育
5.4 内言への注目
6 認知科学概説
6.1 認知心理学への系譜
6.2 人工知能研究
6.3 スキーマとは何か
6.4 記憶の実験とシミュレーション
6.5 やる気の研究
6.6 コンピュータを何に使うか
7 Logoでみる認知科学
7.1 スキナー型ティーティングマシン
7.2 クラウダ型ティーティングマシン
7.3 系統的試行錯誤
7.4 三段論法を理解する会話
7.5 英語の発音の学習
7.6 計算間違いのシミュレーション
7.7 アニマル
おわりに
内容説明
本書は、工科系大学の人文社会科目として開講されている『教育工学』のテキストとして作られた。教育工学が依拠していた当時の学習心理学は、いまや人工知能の研究によって発達した認知科学によって大きく塗り替えられている。パソコン上で人工知能のまねごとをしてみることは、その意味で重要であろう。まず初めに、へーえこんなに人間をまねることができるんだと感心し、また、そのカラクリの意外な単純さにびっくりし、そして、しばらくすると人間と違うところが見えてくる。これは実は、人間の「知」に対する経験でもあったのだ。この本は、Animalを理解できることを目標に、Logoの基本テクニックをトレーニングしていく。
目次
1 Logoとは何か
2 リストと再帰的定義
3 亀を動かすテクニック
4 すこし発展した話題
5 認知科学前史
6 認知科学概説
7 Logoでみる認知科学