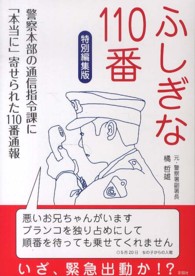出版社内容情報
バイオメカニズム・ライブラリー発刊の趣旨
バイオメカニズムとは,人間を含む生物の形態・運動・情報および機能との関係を,工学や医学・生物学などのさまざまな方法論で解析し,その応用を図る学問分野です.同様の研究領域を持つバイオメカニクスと対比させれば,単なる力学的解析ではなく,生物が本質的に内在している「機構」がキーワードになっているといえます.このこだわりが,その後,ロボット工学やリハビリテーション工学に大きく発展することになりました.
バイオメカニズム学会の創立は1966年で,この種の境界領域を扱う学会としてはもっとも古く,隔年で出版される「バイオメカニズム」は,この分野を先導するとともに,そのときどきの興味と学問水準を表す貴重な資料にもなっています.
バイオメカニズム・ライブラリーは多岐にわたるバイオメカニズムの方法論や応用例をわかりやすく解説し,これまでにと蓄積されたさまざまな成果を社会に還元してさらに新たな挑戦者を養成するために企画されました.これからの高齢化社会で必要とされる身近な介護一つをとっても,バイオメカニズムの方法が負担の軽減や新たな商品開発に多くの示唆をもたらします.生物の仕組みを学ぶこのライブラリーが,これからの社会に求められるより柔軟な発想の源泉になれば幸いです.
バイオメカニズム学会
・ ライブラリー編集委員会
はじめに
科学技術が進むにつれて人間との関りは一層緊密になり,エンジニアとして生体についての基礎的な知識を備えておくことが必要となってきている.ヒトにやさしい機械をつくろう.としたとき,人間についての知識が不足していたのでは,行き届いた設計はできないであろう.また,現在の進んだ技術をもってしても,到底及ばないような優れた機能が生体には多くある.科学技術は生体から多くを学ぶことができる.
生体情報工学は,生体情報のセンシング・処理・制御を対象とする工学の分野である.生体情報といっても,遺伝情報から,細胞・器官・生体システムの情報,人間の心理的なものまで,・ミクロからマクロなレベルまでさまざまである.電気,電子,通信,情報,機械,システムなどの理工学系の教育を受けた者にとつては,独学でこれらを理解するのはかなりの困難が伴う.
本書は,理工学系の学部上級生および大学院生向けの教科書として,できるだけ平易に書いたものである.1990年から生体情報工学を学部学生および大学院生に教えてきた.生物にほとんどなじみのない工学部学生に生体情報工学への知的な興味を抱かせるため,毎年悩みながら資料をつくり,講義をしてきた.本書は,それらをまとめたものである.生体機能を理解するだけでなく,工学との関連がわかるよう課題を設定した.課題はさまざまであり,自らの専門に応じて,適切なものを選べばよい.また章の初めに,身近な例をあげ導入部とした.
、生体情報工学をより深く知りたい人は,この本を学んだあとで別の書物によって勉強をしてはしい.最後に,ご指導頂いた先生方と研究室の諸兄に深謝.
2001年3月
宝塚の自宅にて
著者しるす
第1章 序 論
1.1 生体情報工学
1.2 機械と生体の比較例:カメラの手ぶれ補正と前庭動眼反射
1.3 生体システムの特徴
1.4 ヒューマンインターフェース
1.5 生体情報工学の役割
1.6 課題
第2章 センシングとシミュレーション
2.1 X線CT
2.2 生体センシング技術の基礎
2.3 モデル化とシミュレーション
2.4 課題
第3章 細胞膜と活動電位の発生
3.1 ししおどし
3.2 細胞膜の構造と静止電位
3.3 細胞膜の電位変化
3.4 活動電位のセンシング
3.5 課題
第4章 受容器と感覚情報
4.1 ロータリーエンコーダとマウス
4.2 感覚とその種類
4.3 感覚情報の符号化
4.4 感覚の一般的な性質
4.5 工学センサとの比較
4.6 課題
第5章 ニューロン
5.1 アクティブな非線形素子:真空管
5.2 ニューロンの構造と興奮
5.3 二ューロンのモデル
5.4 線形しきい値素子モデルの応用例
5.5 課題
第6章 神経回路と脳
6.1 フリップフロップ
6.2 神経の結合様式
6.3 側抑制
6.4 脳の構造と機能
6.5 課題
第7章 記憶・学習とニューロコンピューティング
7.1 鍛錬
7.2 神経系の学習の本質
7 .3 シナプスの可塑性の例
7.4 ニューロコンピューティング
7.5 ニューロコンピュータの例
7.6 課題
第8章 筋の収縮と張力制御の神経機構
8.1 形状記憶合金と筋
8.2 節の収縮と力学的特性
8.3 張力の随意制御
8.4 人工のアクチュエータ
8.5 課題
第9章 運動の機構と神経制御
9.1 パンクした自転車
9.2 脳による節張力とスティフネスの調節
9.3 運動サーボ
9.4 運動の中枢プログラム
9.5 人工の手
第10章 触庄覚
10.1 道具と感覚
10.2 触圧覚受容器の構造と応答特性
10.3 高位中枢における触圧覚の情報伝達と情報処理
10.4 感覚代行
10.5 課題
第11章 視覚系の情報処理
11.1 アニメーション
11.2 眼
11.3 外側膝状体と視覚野の情報処理
11.4 視覚の心理現象
11.5 画像処理のフィルタ
11.6 課題
第12章 聴覚系の情報処理と音声
12.1 静かさと音
12.2 聴覚器官の構造と儀覚の神経機構
12.3 聴覚の心理物理的特性
12.4 音声の解
12.5 課題
第13章 遺伝子と進化
13.1 技術の継承
13.2 遺伝子とタンパク質
13.3 進化論的計算論
13.4 課題
付録 補習課題
参考文献
索 引
内容説明
本書は、理工学系の学部上級生および大学院生向けの教科書として、できるだけ平易に書いたものである。1990年から生体情報工学を学部学生および大学院生に教えてきた。生物にほとんどなじみのない工学部学生に生体情報工学への知的な興味を抱かせるため、毎年悩みながら資料をつくり、講義をしてきた。本書は、それらをまとめたものである。
目次
序論
センシングとシミュレーション
細胞膜と活動電位の発生
受容器と感覚情報
ニューロン
神経回路と脳
記憶・学習とニューロンコンピューティング
筋の収縮と張力制御の神経機構
運動の機構と神経制御
触圧覚
視覚系の情報処理
視覚系の情報処理と音声
遺伝と進化
著者等紹介
赤沢堅造[アカザワケンゾウ]
工学博士。1943年倉敷に生まれる。1965年大阪大学工学部電気工学科卒業。1971年大阪大学大学院博士課程修了。大阪大学工学部助手、講師、助教授を経て、1990年神戸大学工学部教授。2000年大阪大学大学院工学研究科教授、現在に至る
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
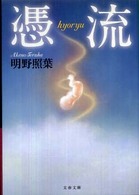
- 和書
- 憑流 文春文庫