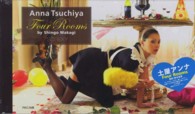出版社内容情報
農業の工業化に引きずられるかのように、農学の工学化がとどまることのない今、果たして工学に従属しない「農学」はどのようにして存在可能なのか、という問いから書き起こす、今までにない農学思想書。「農本主義」の提唱者にして我が国の代表的農学者である横井時敬を軸に、満洲移民政策に深く関与した橋本傳左衛門、報徳思想に傾斜した転向農学者杉野忠夫、ナチス農業政策の満洲移植を試みた法学者川島武宜、公害病研究でも著名な反骨の農学者吉岡金市ら、極めて個性的な農に関わる思想と実践を限界と可能性の視点から詳述。中・東欧やロシア各国の農業政策と農学のなかに日本の農を置き、旧来の農本主義的疑似ロマン主義に流れることなく、医・食・心・政・技を総合する、未来の農学を目指す史的試論。農学を原理的に塗り替えんとする意欲作。
内容説明
工学に従属しない“農学”は、果たして存在可能なのか?ロマン的農本主義を乗り越える、新たな“農学原論”の試み。
目次
序章 科学はなぜ農業の死を夢見るのか
第1章 夢追い人の農学―チャヤーノフと横井時敬の理想郷
第2章 八方破れの農学―横井時敬の実学主義
第3章 大和民族の農学―橋本傳左衛門の理論と実践
第4章 転向者の農学―杉野忠夫の満洲と「農業拓殖学」
第5章 「血と土」の法学―川島武宜のナチス経験
第6章 反骨の実学―吉岡金市による諸科学の統一
終章 農学思想の瓦礫のなかで
著者等紹介
藤原辰史[フジハラタツシ]
1976年北海道旭川市生まれ、島根県奥出雲町出身。2002年京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程中途退学。博士(人間・環境学)。東京大学大学院農学生命科学研究科講師などを経て、2013年より京都大学人文科学研究所准教授。専門は農業史・環境史。著書に、『ナチス・ドイツの有機農業』(柏書房、2005年、第1回日本ドイツ学会奨励賞)、『カブラの冬』(人文書院、2011年)、『ナチスのキッチン』(水声社、2012年/決定版共和国、2016年、第1回河合隼雄学芸賞、上記三作を主な対象として第15回日本学術振興会賞)、『給食の歴史』(岩波新書、2018年、第10回辻静雄食文化賞)、『分解の哲学』(青土社、2019年、第41回サントリー学芸賞)などがある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
無重力蜜柑
はる
Go Extreme
PETE
meòrachan