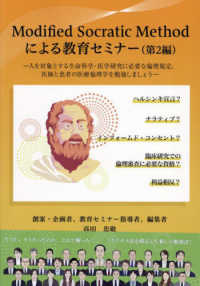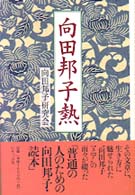- ホーム
- > 和書
- > 工学
- > 電気電子工学
- > 電気工学・電子・通信工学その他
出版社内容情報
直流で送電や配電をしようと努力したのは,あの発明王のエジソンである。当時は直流電圧を高めるのに信頼できる方策がなかったので成功しなかった。しかし,現在では,変圧器と半導体の組み合わせによる交流・直流変換装置の開発により,直流送電は世界各国で広く活用されるようになった。
直流送電は,送電線路の建設費が安価なので長距離送電になれば,特にケーブル送電では経済的になる。さらに直流送電は安定度問題がなく大電力長距離送電に適し,かつ非同期連系ができ,迅速な潮流制御が容易で,かつ運用制御がしやすい。また短絡容量を増大しないで,電力系統間の連系ができるなどの利点がある。
世界の直流送電設備は計画中のものも含めて,図1と表1に示したように,60箇所以上ある。世界初の設備は,1954年に運転開始したスウェーデン本土・ゴットランド島間の直流送電である。1970年代以前の設備は水銀整流器だったが70年以降はほとんどサイリスタバルブが用いられている。これは,信頼性のある高電圧・大電流のサイリスタ素子が開発できたからである。
ヨーロッパでは,直流送電が国際間の電力系統の連系に,積極的に活用されている。これは直流による交流系統間の連系が,無効電力を流さず有効電力のみの融通が実施できる特徴があり,系統故障時の緊急応援が容易だからである。電力系統間の連系の目的は,電力の相互融通による経済的メリットと,予備力および信頼度の向上となっている。北アメリカでは,カナダからアメリカへの長距離直流送電とアメリカ内の東西間の直流による非同期連系(BTB連系)が目立っている。このような国際連系は,技術的・経済的課題のほかに政治や社会の安定があって,初めて実現できるものである。
中国やインドには,運転中の直流送電設備といくつかの計画があり,また他のアジア地域にも直流送電の計画であり,経済復興とともに大いに期待がもたれている。
わが国では,50Hzと60Hz系統間および同一周波数の電力系統間の連系に,直流設備が適用されている。さらに,世界最大級で本格的な直流送電として,紀伊水道プロジェクトが着々と完成に近づいている。
21世紀以降の電力系統には,50Hzと60Hz系の電力融通を容易にするために,日本縦断の直流送電や海底ケーブルによる電力各社間の連系構想も考えられる。今後,より安価で損失の少ない変換所と超長距離送電用の高電圧大容量ケーブル,たとえば500kV以上のCVや超電導ケーブルが開発されると,さらに飛躍的に適用が拡大される。ロシア・日本間,日本・南北朝鮮間など,台湾,中国などの多国間送電網の構想も描けて,ヨーロッパや北アメリカなどで行われている国際間の電力相互融通が,技術的・経済的に容易となる。これは,時差や気候差を利用して,地域の負荷平準化や経済融通が可能でしかも,国ごとに過剰な電源などを持つ必要がなくなる。当然50年や100年先を見すえ,環境問題に有効な再生可能なエネルギーの融通問題や地球温暖化問題の対応,エネルギーセキュリティーの確保などを念頭におきながら,直接燃料を運搬する問題のほか,直流送電による電力連系とパイプラインによる天然ガスの輸送などを,経済比較する必要が出てくるだろう。
また,最近,パワーエレクトロニクスの発達により,送電系統や配電系統にも,電力用半導体の活用が,電力の安定供給や,供給力確保の面で,大いに期待されている。今後,さらに多励式並みの高電圧大容量の自励式変電所が開発されてくれば,交流送電網のように多端子の直流送電網が構築できるようになる。
これまで,直流送電の本は水銀整流器時代に執筆されたもので,急激に発達した半導体技術の時代にそぐわない面も多々あり,しかもパワーエレクトロニクスの応用の趨勢に適した本が少ない。また,電力会社,メーカー,大学などからも適切な本の要望が出ている。
以上のことから,製造・製作,応用および研究の各方面から,幅広く専門家を結集して執筆した。執筆にあたり,読者ができるだけ直流送電全般を広く捉らえて,かつ多くの知識を吸収し,理解できるように心がけたつもりである。
そこで,新しく,この分野の知識を習得し,最近の動向と技術的課題が何であるかを知ろうとする電気事業に関連した企業の社員,ならびに大学,工業専門学校の学生の皆さんに参考になれば幸いである。
終わりに,このような執筆の機会を与え,始終励ましていただいた電力中央研究所の依田理事長に心から感謝するとともに,出版にあたり種々御協力を賜った本書著者以外の方々ならびに東京電機大学出版局の関係各位に深謝の意を表します。
1999年1月
編著者一同
第1章 直流送電の特徴と内外の直流設備
1.1 直流送電の特徴と適用分野
1.1.1 直流送電の特徴
1.1.2 直流送電の適用分野
1.2 外国の直流設備
1.2.1 海底ケーブル送電
1.2.2 長距離架空送電
1.2.3 BTB(back-to-back)
1.2.4 短絡容量対策
1.3 わが国の直流設備
1.3.1 佐久間周波数変換所
1.3.2 新信濃周波数変換設備
1.3.3 北海道・本州直流連系
1.3.4 紀伊水道直流送電
1.3.5 東清水周波数変換設備
1.3.6 南福光直流連系設備
第2章 直流送電の基礎構成
2.1 直流送電方式
2.1.1 直流単独方式
2.1.2 交流・直流連系方式
2.2 直流系統構成
2.2.1 直流二端子送電
2.2.2 直流多端子送電
第3章 直流送電設備の基本設計
3.1 交直変換所の主要機器
3.1.1 主回路構成
3.1.2 変換用変圧器と直流リアクトル
3.1.3 サイリスタバルブ 3.1.4 直流避雷器
3.1.5 直流ガス絶縁開閉装置
3.1.6 フィルタ
3.2 直流送電線
3.2.1 架空電線路
3.2.2 直流ケーブル
3.3 絶縁協調
3.3.1 直流系統の電圧ストレス
3.3.2 変換所機器の直流絶縁性能
3.3.3 直流系統の絶縁協調
第4章 変換装置の動作と基本特性
4.1 他励式変換装置の動作
4.1.1 三相ブリッジ変換器
4.1.2 順・逆変換器の運転特性
4.1.3 コンデンサ転流型変換器
4.2 自励式変換装置の動作
4.2.1 直流送電用の自励式変換器
4.2.2 電圧型変換器の動作と基本特性
4.2.3 系統運用時の有効・無効電力特性
4.2.4 変換器各部の電圧・電流波形
4.2.5 開発課題
第5章 他励式直流送電の制御保護方式
5.1 基本制御
5.1.1 制御の原理
5.1.2 位相制御方式
5.1.3 変換器制御方式
5.1.4 順・逆変換器の協調
5.1.5 制御・保護用の検出器
5.2 保護方式
5.2.1 故障の分類と保護操作
5.2.2 変換所内の故障と保護例
5.2.3 直流側の故障と保護例
5.2.4 交流側の故障と保護例
5.3 情報伝送方式
5.3.1 伝送回路
5.3.2 信号伝送方式
5.3.3 信頼性
第6章 他励式直流送電の運転特性と運用制御
6.1 直流送電の運転特性
6.1.1 系統事故時の運転特性
6.1.2 交流電圧安定性
6.1.3 高調波安定性
6.1.4 軸ねじれ共振現象
6.2 直流送電による系統制御
6.2.1 系統周波数制御
6.2.2 交流電圧・無効電力制御
6.2.3 系統安定化制御
6.3 直流多端子送電の制御保護方式
6.3.1 制御保護方式
6.3.2 系統事故時の運転特性
6.3.3 起動・停止
6.3.4 潮流反転
第7章 自励式直流送電の制御・保護方式
7.1 自励式変換器のみの送電
7.1.1 直流系統の回路構成
7.1.2 制御・保護装置
7.2 自励式・他励式変換器の組合せ送電
7.2.1 系統構成
7.2.2 制御・保護方式
7.2.3 ハイブリッド直流送電設備の実例
第8章 パワーエレクトロニクス応用
8.1 半導体電力変換装置
8.1.1 電力用半導体素子
8.1.2 電力変換装置
8.2 電力システムへの適用
8.2.1 発電機の制御
8.2.2電力系統の安定化制御
8.3 配電・需要家システムへの適用
8.3.1 分散型電源用インバータ
8.3.2 系統連係装置
8.3.3 電磁両立性(EMC)問題
内容説明
これまで、直流送電の本は水銀整流器時代に執筆されたもので、急激に発達した半導体技術の時代にそぐわない面が多々あり、しかもパワーエレクトロニクスの応用の趨勢に適した本が少ない。また電力会社、メーカー、大学などからも適切な本の要望が出ている。以上のことから、製造・製作、応用および研究の各方面から、幅広く専門家を結集して執筆した。
目次
第1章 直流送電の特徴と内外の直流設備
第2章 直流送電の基本構成
第3章 直流送電設備の基本設計
第4章 変換装置の動作と基本特性
第5章 他励式直流送電の制御保護方式
第6章 他励式直流送電の運転特性と運用制御
第7章 自励式直流送電の制御・保護方式
第8章 パワーエレクトロニクス応用