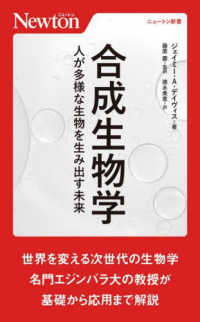出版社内容情報
《内容》 癌の専門医から,一般臨床家,研修医,ナースまで,誰でも理解でき,誰でも参加できる癌の疼痛対策を目指して解説されたユニークな入門書である. 内容は麻薬による癌性疼痛の治療,WHO方式の特長と応用,オピオイド投与の原則,投与法の実際,副作用と対策,神経ブロック,神経的ケア,ターミナルケアなど,記述は具体的,懇切丁寧で,大変わかり易く実践的な書である. 2版の序 1986年に『がんの痛みからの解放』と題してWHOから出版された WHO方式癌疼痛治療法の第2版が1996年に発刊された. 第1版が概念的な要素が強い傾向であったのに比べて, 第2版は,より実際的になったと思われる. 『がんの痛みからの解放』第2版を読み,WHO方式の補足説明書的役割を目的に 『がん患者の痛みの治療』を出版したが,筆者がその内容や方向性に 誤りがないことを再確認した. モルヒネが癌の痛みの治療に用いられるようになったのは決して 最近のことではない.筆者が医者になった1970年ころにも臨終が近くなると モルヒネが投与された.しかし,少量で,しかも回数制限付きだったために, 苦しみから解放されることはなかった. このことは,モルヒネという薬自体がすばらしいのではなく,その使い方, すなわちモルヒネの投与方法や副作用対策が著しく改善されたのである. したがって実際の使用法,言い換えれば患者一人一人に対応した痛みの治療法が 重要になる.しかも,長期的にみれば,がん患者の痛みは病気の進展・ 増悪に伴って必ず強くなるので,痛みの治療は臨終まで継続的に 行わなければならない. さらに,モルヒネの普及に伴って大量投与例が増えてきたが, 痛みがコントロールされない症例やモルヒネ徐放剤のコストの面などから, リン酸コデインや神経ブロック療法が再度注目されるようになった. このような立場で,初版の『がん患者の痛みの治療』を見直すと, 不備な点が多くみられたので改訂することにした. 改訂にあたっては,オピオイドの至適量の決め方(疼痛時頓用加算法)や 神経ブロックの適応となる痛みについて,できる限りわかりやすくしたつもりである. また,巻末には追補として診療所の医師や院外薬局の協力を得られるように, がん性疼痛の治療体制についても,救急医療になぞらえて試案を提言した. 今回の改訂にあたって,同僚の佐藤智君ならびに東北大学麻酔学教室の諸先生方に お世話になったことを感謝します.また改訂の労をとってくださった 中外医学社の青木三千雄社長ならびに久保田恭史氏をはじめとする 編集部の方々に深謝の意を表します. 1997年9月 山室 誠 初版の序 WHOが提唱した癌性疼痛治療3段階方式は画期的な方法だが, 実際に現場で行ってみると戸惑うことが多い.6年以上の経験を経て, 最近ようやく指針らしきものがみえてきた.そのうえで改めてWHO方式を見直すと, すばらしい概念に立脚した癌性疼痛治療だが,実施上での説明不足があるように 思われる.したがって,WHO方式の補足あるいは使用説明書があれば, もっと普及すると思われる. さらに本邦で独特の発展を遂げたペインクリニックの神経ブロックの技術を WHO方式に加えることによって,癌性疼痛の治療効果は一層向上し, より多くの癌患者が痛みから開放されるはずである. しかし,癌患者の痛みの治療は薬や技術だけでは不十分である. 癌性疼痛の管理ではなく,癌患者の訴える痛みの治療が必要になる. それにはホスピス精神を基礎にした緩和医療が不可欠と考えられる. 筆者が10年ほど前に天羽敬祐先生に監修していただき出版した 『図説 痛みの治療入門』の癌性疼痛の治療には,神経ブロックによる方法しか 書いていなかった.また2年前に,教室から関連病院に赴任していく 麻酔科医のために東北大学麻酔学教室と協力して, モルヒネの使用法を中心に『癌疼痛対策マニュアル '92』という小冊子を 試行錯誤で制作した. そこで,一般病院で緩和医療を志す立場から『図説 痛みの治療入門』と 『癌疼痛対策マニュアル '92』をもとに 癌の痛みの治療説明書''として, 初心者を対象に本書を書いた. したがって,ある程度モルヒネを使いこなしている先生方からみれば, リン酸コデインからの開始,モルヒネ水溶液からMSコンチンヘの移行への こだわりなど,かえって煩わしいと思われる点が多々あるかもしれない. しかし,まだ多くの医療従事者が麻薬の使用に躊躇している.しかもこれらの人々が 癌の痛みの治療に参加してくれなければ在宅ターミナルケアなど夢にすぎない. 「急がば回れ!」の諺に従い,煩わしさはあっても安全・確実な方法を最優先させ, ペインクリニックへの紹介時期についても言及した. 在宅医療のために癌性疼痛治療を学ぼうとする開業医の先生,あるいは 研修医や看護婦などに本書を読んでいただければと願っている. そして本書が,痛みに苦しむ癌の患者の治療に多少なりとも役に立てば, 筆者にとって最上の幸せである. 最後に,本書を執筆するにあたって協力してくださった東北大学麻酔学教室の 兼子忠延助教授,小川佐千夫先生,仙台徳洲会病院麻酔科の安田朗雄先生に 深謝します. また本書の刊行にあたり多大な御尽力をいただいた中外医学社の青木三千雄社長 および久保田恭史氏をはじめとする編集部の方々に感謝の意を表します. 1994年8月 山室 誠 《目次》 目次 1.癌性疼痛患者の実情 1 癌患者の主訴とその対策の遅れ 2 癌患者からのメッセージ 2.麻薬による癌性疼痛の治療 1 麻薬に対する基礎知識 A.麻薬使用に対する誤解 B.麻薬中毒に対する誤解 C.癌性疼痛管理での麻薬 2 オピオイド(麻薬性鎮痛薬)の効果と個人差 A.酒と盃の仮説 B.オピオイドの血中濃度からみた“酒と盃の仮説” C.至適オピオイド投与量の決め方 (1)初回投与の経過観察による方法(単回投与法) (2)疼痛時の追加投与による方法(臨床的応用 - 疼痛時頓用加算法) (3)疼痛時頓用加算法 3.WHO方式の特長 1 鎮痛薬の段階的使用(by the ladder) 2 定時に投与(by the clock)+疼痛時頓用薬の常備 3 ダブルブロック 4 副作用には対症療法(薮医者方式) 4.オピオイド投与の原則 1 痛みにあわせたオピオイドの投与 2 オピオイドの至適量(滴定とチェック) 3 投与ルートの変更 4 予防的副作用対策 5.オピオイド投与法の実際 1 経口的オピオイド投与法の実際 A.WHO方式の改変 B.実際の投与方法の指針 (1)第1段階:NSAIDsの投与 (2)第2段階:リン酸コデインの追加 (3)第3段階:モルヒネへの移行 (4)MSコンチンでの維持 (5)経口モルヒネの鎮痛必要1日量について 2 非経口的オピオイド投与法の実際 A.持続注入法 (1)持続皮下注入法 (2)持続静注法 (3)持続硬膜外腔注入法 (4)モルヒネ以外の鎮痛薬の持続注入法 B.経直腸投与(坐薬による投与) C.ケタラール(塩酸ケタミン)+ドルミカム(ミダゾラム)の持続投与法 3 鎮痛補助薬 A.ステロイド B.抗痙攣薬 C.抗うつ薬 D.抗不安薬 E.睡眠薬 6.オピオイド投与による副作用と対策 1 オピオイドによる重篤な副作用はない A.呼吸乱ァ・意識障害 B.麻薬中毒 2 通常みられるオピオイドの副作用 A.便秘 B.吐き気・嘔吐 C.眠気 D.精神症状(見当識・記憶・認知・思考障害,幻覚,妄想,異常行動など) E.その他の症状 (1)口内乾燥感 (2)発汗 (3)掻痒感 (4)ふらつき感 (5)排尿障害 (6)呼吸乱ァ (7)麻薬中毒 7.神経ブロック 1 神経ブロックとオピオイドの併用 2 鎮痛と麻酔 3 神経ブロックの方法 A.意義と目的 B.適応 4 神経ブロックの実施法 A.局所注入法=トリガー ポイント ブロック B.(脊椎)硬膜外ブロック C.仙骨硬膜外ブロック D.腹腔神経叢ブロック E.上・下腹(動脈)神経叢ブロック F.くも膜下フェノールブロック(時にアルコール) G.交感神経節ブロック H.経皮的コルドトミー I.三叉神経(各氏jブロック,三叉神経節ブロック J.硬膜外電気刺激療法 K.星状神経節ブロック L.ファッセット リゾトミー(Facet's rhizotomy) 8.精神的ケア---終末期医療における向精神薬の使用法 1 患者の精神的症状 A.不安,不眠,翌、つ気分に対して B.見当識障害,幻覚妄想など譫妄状態によると考えられる問題行動 2 家族への対応 9.WHO方式と神経ブロックの併用 10.ターミナル ケア---終末期の鎮痛 1 終末期の疼痛管理の現状 2 終末期の鎮痛が不完全な要因について A.不安と疼痛の増悪 B.Total Painとしての治療が不十分 3 終末期のParadox A.痛みの治療におけるParadox B.痛みをもつ患者のParadox 4 Death Education(死の教育) 5 地域に密着した緩和ケア病棟の設立 6 追補:わが国における癌性疼痛治療体制についての提言 A.癌性疼痛治療3群体制について B.癌性疼痛治療3群体制の運用方法 C.おわりに 文 献 索 引