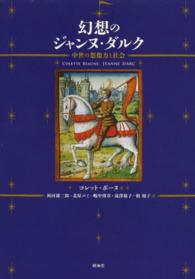出版社内容情報
《内容》 今日,運動負荷試験は冠動脈疾患のみならず心不全を含むあらゆる心臓病の診断に不可欠なものとなっている.本書はこの心臓病における運動負荷試験の基礎,方法,解釈,薬物効果の評価から運動療法とトレーニング効果までを著者自らの経験をもとに実践的に解説したものである.その最新の理論と実際を臨床的な見地から総括的に多数の図や実例を入れて解りやすく述べた初めての書である. 2版の序 早いもので,本書の初版が上梓されてからすでに5年が経過した.幸いにして本書が循環器学を目指す多くの若手医師やコメディカルの方々から好評をもって迎えられたことは,著者の大変慶びとするところである. 初版の序文でもふれたように,運動負荷試験は循環器を専攻する医師がまず取り組まなければならない最も身近な診療分野であるにも関わらず,それまで啓蒙的かつ包括的な日本語の専門書がなかったことが,本書が長年にわたって受け入れていただけた理由ではないかと考えている. 循環器病学は病態学,診断学,治療学のいずれもその進歩は極めて速く,5年も経つとほとんどすべてを書き直さなくてはならなくなってしまうといっても過言ではない.運動心臓病学Exercise cardiologyの領域においても,最近5年の間に運動負荷心電図の自動解析は完全に日常診療の中に取り込まれたし,また当時まだ数少ない施設でしか行われていなかった心肺運動負荷試験は,新しいコンピュータ化された呼気ガス分析装置の開発・普及に伴って,今ではどこの施設でも行えるルーチン検査になりつつある.核医学検査も然りで,当時は心筋虚血の診断や心筋viabilityの評価などが学会を賑していたが,今ではこれらも完全なルーチン検査となり,学会における心臓核医学の熱気は失せつつあるといえる. しかし幸いなことに運動心臓病学の分野におけるこれらの進歩は,いわば諸検査の普及・ルーチン化であり,大幅な書き直しが必要なほどの新しい知見は得られていないといえる.そこで本書第2版では主に初版の訂正と新しい流れにそぐわなくなったところを修正するにとどめた.次の版においては大幅な改定が必要になることは覚悟の上である. 初版上梓時,著者はちょうど国立循環器センターから自治医科大学に移ったところであり,所属は自治医大でありながら「著者の施設」とあるのは国立循環器センターのことである旨断わっているが,第2版においてもデータの大部分は当時の国立循環器病センターで得られたものであることをここで再度お断わりしておく. 運動心臓病学は,これからもますます応用範囲が広がり,重要性が増すと考えられる. 本書が多少なりとも皆様の助けになれば幸いである. 1993年6月 斎藤宗靖 初版の序 運動負荷試験は循環器疾患の診断に不可欠である.すべての人間はたえず行動しており,循環器疾患の臨床症状の多くは行動や労作に伴って出現することが多いからである.冠動脈疾患における胸痛はもちろんのこと,心不全における息切れや不整脈も運動と密接に関係している.すなわち,心臓病は単に形態的な異常のみならず,機能的な異常を伴う疾患であり,循環系に何らかの侵襲を加えて初めてその異常が検出されることが多いといえる.生体に対する侵襲の中では,運動がもっとも生理的であり,ここに心臓病学における運動負荷試験の重要性があるといえる. 運動負荷試験の歴史は古く1933年に始まるが,当初その目的は虚血性心疾患の診断にあった.以来,運動負担試験といえば虚血性心疾患の診断を目的とした運動負荷心電図検査のことをさしていたが,近年,運動負荷試験の評価法として単に心電図のみならず,核医学的な手法や,さらに最近では呼気ガス分析の手法が取り入れられ,また虚血性心疾患のみならず心不全を含むあらゆる心疾患がその対象となりつつある.また米国に遅れること10年,わが国においても最近心臓リハビリテーションとしての運動療法が注目を集めているが,この分野も運動負荷試験の関連分野として重要になりつつある. このようにみてくると,運動負荷試験は古くて,しかも常に新しい学問の分野であるといえる.米国においては常に最新の運動負荷試験に関する単行書が刊行されているが,わが国において運動負荷試験に関する書物の出版が極めて少いのが実情である.運動負荷試験は,循環器を専攻する医師にとって最も身近な分野であり,また極めて臨床的な部分である.この意味で運動負荷試験に包括される幅広い分野を,臨床的な見地から総括的に理解しておくことは大変重要であると考えられる.これが,本書を執筆した動機である. 本書では心臓病における運動負荷試験を包括的に解りやすく書いたつもりである.その内容は,運動生理学・循環病態学・運動負荷心電図学・心臓核医学・呼気ガス分析による新しい心疾患の病態診断・運動負荷試験による薬剤効果の評価・リハビリテーションとしての運動療法など広い分野に渡っているが,そのすべての分野における最新の理論と実際を,文献的考察や欧米の成書を参考にしながら,著者の国立循環器病センターにおける10年間の経験に基づいて書いたものである.近年,分担執筆による刊行書が多い中にあって,敢えて単行書として1人で執筆した理由は,均質な内容,同じレベルで統一しようとしたためである.そのために著者の多少不得手とする分野に関しては,国立循環器病センター放射線診療部植原敏勇氏(心臓核医学),同心臓内科吉岡公夫氏(心肺運動負荷試験),同小児科矢沢健司氏(小児の運動負荷試験)の御協力を得ましたことを,この場を借りて御礼申し上げます. 最近,著者は国立循環器病センターから自治医科大学に移ったが,文中にある著者の施設は国立循環器センターのことをさしており,またここに記載されているテータはすべて国立儒官期病センターにおいて得られたものであることを,ここにおことわりしておく. これからますます応用範囲が広がり,重要性が増すと考えられる運動負荷試験の分野 において,本書が多少なりとも皆様の助けになれば幸いである. 最後に本書の出版にあたり,御協力を頂いた中外医学社編集部の皆様に深謝します. 1988年9月 自治医科大学大宮医療センター開設準備の合間をぬって 斎藤宗靖 《目次》 目次 §1.運動負荷試験の基礎 A.健常者における運動反応(運動生理学) 1 1.骨格筋の特性 2 2.運動時の筋肉におけるエネルギー代謝 2 3.運動時の生体反応 4 a.運動時の循環系の調節 4 b.運動時の心血管反応 5 c.運動と呼吸 8 4.運動の種類 8 a.動的運動と静的運動 8 b.有酸素運動と無酸素運動9 5.最大酸素摂取量 10 B.冠動脈と冠循環 13 1.冠動脈の解剖 13 a.冠動脈 13 b.冠静脈 14 c.心室壁内細小動脈 14 d.側副血行路 15 2.心筋酸素供給と冠循環 15 a.冠循環の調節機序 16 b.心筋酸素消費と冠血流 19 c.心筋酸素消費の臨床的な指標 21 d.心筋酸素消費量指標の臨床的意義 21 3.狭心症の発生機序 22 C.運動と心機能 25 1.心機能の重症度部類 25 2.運動と血行動態反応 26 a.動的な運動における血行動態反応 26 b.等尺性運動における血行動態反応 27 3.不全心における運動反応 28 §2.運動負荷試験の方法 A.運動負荷試験の目的 33 B.運動負荷試験の方法 34 1.運動負荷の方法 34 a.運動の種類 34 b.単一水準定量負荷と多段階負荷 34 c.最大負荷と亜最大負荷 37 2.症状限界性多段階トレッドミル負荷試験 37 a.トレッドミル負荷試験のプロトコール 37 b.トレッドミル負荷試験の適応 41 c.トレッドミル負荷試験の禁忌 42 3.トレッドミル負荷試験の実際 44 a.トレッドミル負荷試験に必要な機器 44 b.トレッドミル負荷試験の実際 46 c.トレッドミル負荷試験の中止基準 53 4.等尺性運動負荷試験 56 a.等尺性運動負荷試験の方法57 b.等尺性運動負荷試験の臨床的意義 58 C.運動負荷心電図 60 1.運動負荷心電図の取り方 60 a.双極誘導法 60 b.標準12誘導心電図の記録法 60 c.運動負担心電図誘導法と虚血の検出率 60 d.きれいな心電図の取り方 61 2.コンピュータによる運動負荷心電図の自動解析 62 a.心電図コンピュータ解析の歴史 62 b.現在発売されている運動負荷心電図自動解析装置 63 c.Marquette社製CASE 66 §3.虚血性心疾患における運動負荷心電図の解釈 A.運動負荷心電図の診断原理 71 1.感度と特異度 71 2.cutoff levelとROC曲線 73 B.運動負荷心電図の診断基準 77 1.健常者における運動負荷心電図 77 2.運動負荷心電図診断基準の提唱 79 a.MASTERの陽性基準 80 b.BELLETの基準 80 c.GOLDBARGの基準 80 d.その他の診断基準 80 3.運動負荷心電図の各診断基準 82 a.ST低下 82 b.ST上昇 88 c.陰性U波 91 d.運動誘発性不整脈 92 C.心疾患の病態と運動負荷心電図 94 1.冠動脈疾患の重症度と運動負荷心電図 94 2.運動負荷試験における性差 特に女性の運動負荷心電図 95 a.冠動脈疾患の有病率と性差 95 b.運動負荷心電図の感度,特異度 95 c.偽陽性率が高いことの説明 96 d.鑑別診断 97 3.脚ブロック症例における運動負荷心電図 97 a.右脚ブロック 97 b.左脚ブロック 98 4.電解質・薬物と運動負荷心電図 99 a.低カリウム血症 99 b.低カリウム性アルカローシス 99 c.ジギタリス 100 d.抗狭心症薬とST変化 100 e.その他の薬剤の影響 100 5.syndrome“X” 100 6.偽陽性ST低下の機序としての心筋障害 102 7.左室肥大と運動負荷心電図 102 D.心筋梗塞疾患者における運動負荷心電図 104 1.ST低下 104 2.胸痛の出現 105 3.ST上昇 106 4.運動誘発性不整脈 106 5.運動耐容量・血圧反応など 106 §4.虚血性心疾患以外の疾患における運動負荷試験 A.小児における運動負荷試験 113 1.小児における運動負荷試験の適応 113 2.小児における運動反応 114 3.小児における運動負荷試験の方法 116 4.各種小児心疾患における運動負荷試験 117 a.左室,右室流出路狭窄 117 b.左室,右室容量負荷 119 c.不整脈疾患 120 d.川崎病 120 B.高齢者の運動負荷試験 123 1.加齢現象と運動 123 2.高齢者における運動負荷試験 124 C.不整脈と運動負荷試験 126 1.運動時の電気生理的反応と不整脈 126 a.運動誘発性不整脈の機序 126 b.運動時不整脈消失の機序 126 2.運動誘発性不整脈 127 a.上室性不整脈 128 b.心室性不整脈 128 c.房室ブロックおよび脚ブロック 129 d.WPW症候群 129 D.特殊な目的のための運動負荷試験 130 1.心臓リハビリテーションのための運動負荷試験 130 a.心臓リハビリテーションにおける運動負荷試験 130 b.運動負荷試験プロトコール 130 c.呼気分析とBORG指数 131 2.弁膜症における運動負荷試験 132 3.血行再建術後の運動負荷試験 133 a.血行再建術の適応決定 133 b.ACバイパス術の効果判定 133 c.経皮的冠動脈形成術の効果 134 §5.運動負荷心臓核医学検査 A.運動負荷試験における心臓核医学検査の位置付け 139 B.運動負荷心筋シンチグラム 141 1.201TI運動負荷心筋シンチグラムの原理 141 2.負荷心筋シンチグラムにおける運動負荷試験 142 3.運動負荷心筋シンチグラムの実際 143 4.運動負荷心筋シンチグラムの解釈 144 a.虚血と梗塞の鑑別 145 b.陰影欠損の部位診断 146 c.偽陽性例の診断 150 d.肺野タリウム集積 150 5.運動負荷心筋シンチグラムの臨床的意義 155 a.有意冠動脈病変検出における感度,特異度 155 b.運動負荷心電図偽陰性,偽陽性例における有用性 155 c.冠動脈病変部位診断における有用性 155 d.心筋梗塞症患者における負荷心筋シンチグラムの意義 156 e.経皮的冠動脈形成術と負荷心筋シンチグラム 156 6.負荷心筋シンチグラムの定量的評価 157 a.関心領域(ROI)法 157 b.circumferential profile法 158 c.washout rate法 158 7.断層心筋イメージング法 159 8.その他の負荷心筋シンチグラム 161 C.RIアンギオグラフィー 163 1.RIアンギオグラフィーから得られる情報 163 2.運動負荷RIアンギオグラフィーの方法 163 a.first pass法 163 b.平衡時法 164 3.運動負荷RIアンギオグラフィーの実際 165 4.運動負荷RIアンギオグラフィーによる心筋虚血の検出 165 5.運動負荷RIアンギオグラフィーの長所,短所 167 §6.Cardiopulmonary Exercise Test-運動負荷試験における呼気分析の応用 A.Cardiopulmonary Exercise Test-心肺運動負荷試験 171 1.心肺運動負荷試験の意義 171 2.心肺運動負荷試験の適応 172 3.嫌気性代謝閾値 173 a.骨格筋のエネルギー代謝 174 b.嫌気性代謝閾値の考え方 175 c.嫌気性代謝閾値の求め方 178 4.心肺運動負荷試験のプロトコール 178 a.トレッドミル プロトコール 180 b.自転車エルゴメータ試験プロトコール 181 5.呼気ガス分析法 181 a.VO2の測定 181 b.VCO2の測定 182 c.VO2,VCO2の測定の実際 182 B.心肺運動負荷試験の臨床応用 184 1.慢性心不全 184 a.WEBER,JANICKIによる心機能分類 184 b.心機能分類と血行動態 185 2.慢性肺疾患 187 a.最大酸素摂取量の制限因子 187 b.閉塞性肺疾患 187 c.拘束性肺疾患 188 3.心臓リハビリテーションにおける心肺運動負担試験 188 §7.運動負荷試験による薬剤効果の評価 A.運動負担試験による抗狭心症薬の効果判定 191 1.運動負荷試験からみた抗狭心症薬の効果 191 a.β遮断薬 191 b.硝酸薬 194 c.硝酸薬とβ遮断薬の併用効果 196 d.カルシウム拮抗薬 197 2.運動負荷試験による薬剤効果判定の問題点 201 a.運動負荷試験の再現性と慣れの効果 201 b.運動負荷方法とプロトコール 202 c.運動終点の設定 203 3.負荷心筋シンチグラムによる薬剤効果の判定 203 B.心不全治療薬の薬剤効果判定 205 §8.運動療法とトレーニング効果 A.トレーニング効果の機序 209 1.健常者における運動療法の効果とその機序 209 a.運動療法の効果 209 b.最大酸素摂取量増加における末梢性機序 210 c.トレーニング効果における中枢性機序 211 d.トレーニング効果における自律神経の関与 212 2.冠動脈疾患患者における運動療法効果とその機序 212 a.心筋虚血のない冠動脈疾患患者におけるトレーニング効果 213 b.心機能の改善と中枢効果 215 c.冠動脈疾患患者における側副血行,心筋虚血の改善 215 d.狭心症患者におけるトレーニング効果 216 3.運動療法効果とその機序に関するまとめ 217 4.運動療法と冠動脈疾患の二次予防 217 B.運動療法と運動処方 219 1.運動テ法の種類-その長所と短所 219 2.運動処方 220 a.アメリカスポーツ医学協会による運動療法プログラム 220 b.YMCardiac therapy 222 c.HRCの運動療法理論 224 C.非監視型在宅運動療法 226 1.運動療法の対象 226 2.運動負荷試験と運動処方 226 3.心拍数による運動処方の問題点 229 4.運動療法の効果 230 5.トレーニング効果の阻害因子 230 6.運動療法の精神的効果 230 索引 237