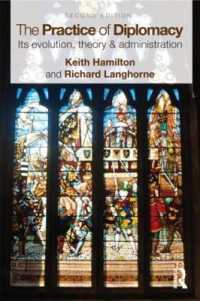出版社内容情報
《内容》 第3版の序 本書は日常診療現場における臨床検査の適切な利用方法と成績の解釈,考え方について,図,表を多用してわかりやすくまとめることを目標とした.初版上梓以来10年を俟たず3回の改訂増補に至ったことは本領域の進歩,変遷が急速であることを物語ると同時に,本書のチャート形式が多くの方々に受け容れられたと思い著者らの慶びとするところである.それだけに著者らはより大きな責任を感じ,また果たすべく改訂に取り組んだ.まず,いくつかの新たに日常検査に採用されつつある検査項目を追加し,データの蓄積によって少しずつ解釈が変りつつある項目とか,方法論の変更からシフトを来たした正常値などの見直しを行った.もちろん,このような変化の激しい部分,項目は方法論に進歩の余地がみられる比較的新しい項目に多く,尿一般検査,血球算定などの分野ではほとんど改訂の余地はない.しかし,免疫血液学領域では今後とも新知見が加わり,臨床診断情報としては未だ不確定の部分が多いと思われ,近い将来さらに整理を要する部分であることをお断りしておきたい. 本書の性格上,例外的な事態とデータに関する配慮も解説しておいたが,チャート化はしていない.また,本書は検査数値に過誤はなかったものとの前提で記述されているので,サンプリング誤差に関して絶えず注意しながら数値をよんで戴きたい.本書が臨床検査室,検査センターの利用にあたって診療各科医師あるいは研修医,医学生諸氏に少しでも役立つことがあれば著者らの最も幸いとするところである.また,より一層本書の充実を求めて努力を傾ける心算であるが,過誤,御助言などお気付きの節は御遠慮なくお寄せいただければ幸いである. 改訂まで計画後1年以上いろいろと努力された中外医学社荻野邦義さんに著者ら一同心から感謝の意を表する. 1991年12月 著者ら 2版 序 初版上梓以来3年を待たずして再版の機会を得た.この間多くの読者の方々から貴重な御意見を賜わり心から感謝する次第である. 再版に際して新たに血清コリンエステラーゼ,血清マグネシウム,クームス試験などあきらかに脱落と思われる部分を補足した.また,最近日常臨床検査項目として扱われ,経験を重ねつつある腫瘍マーカー(CA-19-9,CA-125)と細胞免疫検査のうちリンパ球に関する検査を追加した.新しい検査項目の臨床的評価は広く普及したのちに定まるのが常であるが,研修医あるいは学生諸氏の便を考えると本書にも一項設けたほうがようと思われたことによる. 日進月歩の本領域すべてを網羅することは至難のわざで,完璧は期し難いが読者諸氏の忌憚のない御意見を戴き,また改版の機会を得て新たにすることができればと望むものである. 1986年12月 著者ら 序 医療のなかで臨床検査はこの30年間にめざましい発展を遂げた.世界的にみてもほぼ7~10年周期で画期的な開発,発見があり,それを契機にまた進歩普及をくりかえしてきたように思う.すなわち,1950年代の酵素測定の検査への導入,1960年代の自動化,1970年代のラジオイムノアッセイによる微量成分の定量と内分泌学への応用,現在の臨床免疫等,遺伝子工学の成果と臨床検査への導入である. これらの開発,発見によって臨床検査の種類,項目もこの30年間に教科書だけからみても4~5倍増となり,総検査件数に至っては年率8~10%増が先進諸国の統計に明らかである.そして数多い医療情報のなかで,臨床検査成績が重要な位置を占めることは既に医師,患者とも充分認識するところとなった. この多種類,多項目の臨床検査は既に,単に利用するという意味ではなく,如何に効果的に,しかも効率よく医療の現場に生かして使うかが問われる時代となった. 本書は以上のような観点から,既に普及してどこでも,誰でも実施できる検査について,成績を手にしたとき見逃がすことのできない要点だけを簡単に記述することを試みた.検査項目別に(1)検査の意義,(2)異常値を示す病態,(3)組み合せと鑑別診断,(4)正常範囲と生理的変動,(5)変動要因と誤差の順に記し,測定手技は解釈に関連する事項を除いて省略した.特に検査の妨害要因に関してはわかっている限り記載することを心懸けた.図表を多用したのは平易な解説を目指したことによる.また,いわゆる一般血液検査の項目はやや簡単すぎるかもしれないが,既に永年の経験と他に立派な成書もあり要点のみでよいとの判断から少くなった.これに対して,内分泌系の解説にかなりの頁数をとっているのは,本分野がどちらかといえば新しい検査領域で実地医家になじみが少いと思われたことによる. 数多い臨床検査を利用するに当って,多忙な実地医家の方々に,また研修医,専門課程高学年生の参考になれば著者らの幸いとするところである.また,本領域の進歩,発展の速度はめざましく,あるいは考え違いの記述もあるかと思われる.御教示,忌憚のない御意見をお寄せいただくことを希望する. おわりに,多数の図表,原稿を整理し上梓にまで漕ぎつけた中外医学社 荻野さんほかの方々に長日月の努力に感謝の意を表する. 1984年5月 著者ら 《目次》 目次 1.序説 〈林康之〉 1 一般検査 2.尿蛋白 〈林康之〉 9 3.尿糖 16 4.尿ケトン体 20 5.尿ビリルビン 22 6.尿潜血反応 24 7.尿細菌 27 8.尿沈渣 30 9.喀痰 35 10.糞便 39 11.髄液 44 血液(一般)検査 12.ヘモグロビン 〈大場康寛〉 47 13.ヘマトクリット 51 14.赤血球数 55 15.赤血球恒数 59 16.網赤血球数 65 17.末梢白血球数 68 18.末梢好中球数 73 19.末梢リンパ球数 78 20.Tリンパ球,Bリンパ球およびリンパ球機能試験〈佐藤尚武〉 81 21.末梢好酸球数 〈大場康寛〉 94 22.末梢血液像 97 23.特殊染色標本 〈岡村一博〉 103 24.骨髄像 〈大場康寛〉 107 25.Ph1染色体(フィラデルフィア染色体) 113 26.血小板数 115 27.血小板機能検査 118 28.プロトロンビン,部分トロンボプラススチン時間 〈岡村一博〉 123 29.トロンボテスト・ヘパプラスチンテスト・プロトロンビン-プロコンバーチンテスト 133 30.線溶,血栓検査 136 31.フィブリン体分解産物(FDP)とDIC 141 32.毛細血管抵抗試験 〈大場康寛〉 147 33.赤血球沈降速度(赤沈) 150 血液化学分析検査 34.血清総蛋白 〈林康之〉 154 35.血清蛋白分画(電気泳動) 160 36.血清免疫グロブリン 〈中井利昭〉 166 37.血清尿素窒素 〈林康之〉 175 38.血清クレアチニン 180 39.血清クレアチン 〈中井利昭〉 183 40.血清尿酸 〈林康之〉 189 41.血中アンモニア 194 42.血糖 196 43.ヘモグロビンA1Cとフルクトサミン 〈中井利昭〉 201 44.血清総コレステロール 〈林康之〉 204 45.血清中性脂質 209 46.血清リン脂質 213 47.血清遊離脂肪酸 216 48.血清リポ蛋白分画 218 附)血清アポ(リポ)蛋白 222 49.血清アミノトランスフェラーゼ 225 50.血清アルカリホスファターゼ 231 51.血清乳酸脱水素酵素/α-ハイドロキシ酪酸脱水素酵素 (LDH/HBD) 237 52.血清コリンエステラーゼ 243 53.血清γ-グルタミルトランスペプチダーゼ(γ-GTP) 246 54.血清ロイシンアミノペプチダーゼ(LAP) 253 55.血清(尿)アミラーゼ 257 56.血清リパーゼ 262 57.血清クレアチンカイネース(クレアチンホスフォキナーゼ)および血清アルドラーゼ 265 58.血清酸性ホスファターゼ 〈中井利昭〉 270 59.血液ガス測定(pH,PaCO2,PaO2) 〈徳田秀光〉 275 60.血清ナトリウム,カリウムイオン 〈林康之〉 282 61.血清塩素,炭酸イオン 287 62.血清カルシウム,リン 〈中井利昭〉 290 63.血清鉄 〈林康之〉 296 64.血清フェリチン 〈中井利昭〉 300 65.血清銅,亜鉛 〈林康之〉 304 66.血清マグネシウム 〈中井利昭〉 307 67.血清ビリルビン 〈林康之〉 310 負荷試験 68.インドサイアニングリーン試験 〈大場康寛〉 314 69.フェノールスルホンフタレイン試験 317 70.FISHBERG試験/脱水試験 〈岡村一博〉 321 71.クレアチニン クリアランス 325 72.セクレチン試験およびPFDテスト 〈中井利昭〉 328 免疫血清検査 73.CRP/シアル酸 〈岡村一博〉 334 74.RA試験 337 75.COOMBS試験 〈大場康寛〉 340 76.抗核抗体検査 〈岡村一寛〉 344 77.溶連菌抗体 346 78.ウイルス肝炎関連抗原抗体検査 〈林康之〉 350 79.ウイルス抗原抗体検査 354 80.臓器指向性の高い腫瘍マーカー (AFP・PIVKA-II・CA19-9・SLX・NSE・SCC・CA125など) 〈中井利昭〉 358 81.臓器指向性の低い腫瘍マーカー (CEA・TPA・IAPなど) 369 内分泌系検査 82.ACTH 〈中井利昭〉 375 83.成長ホルモン(GH) 381 84.黄体化ホルモン(LH)・卵胞刺激ホルモン(FSH) 388 85.プロラクチン 393 86.抗利尿ホルモン(ADH) 398 87.甲状腺刺激ホルモン 405 88.T4,free T4,T3,free T3およびreverse T3(甲状腺ホルモン) 410 89.サイロイドテストとミクロゾームテスト・TSHレセプター抗体 417 90.RT3UとTBG(サイロキシン結合グロブリン) 420 91.副甲状腺ホルモン(PTH) 423 92.インスリン・C-ペプチド 431 93.グルカゴン 440 94.コルチゾール 444 95.17-OHCSと17-KS(17-ケトステロイド) 451 96.エストロゲン・プロゲステロンとアンドロゲン 459 97.レニン・アンギオテンシン・アルドステロン 463 98.心房性ナトリウム利尿ペプチド(ANP) 472 99.カテコラミン(血中,尿中) 475 100.カテコラミン代謝産物(尿中) 483 101.ガストリン 489 102.ソマトスタチンおよびVIP 494 附1.化学検体の保存と取り扱い方 〈林康之〉 497 附2.血中薬物濃度測定の利用 〈中井利昭〉 499 索引 501