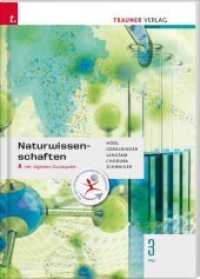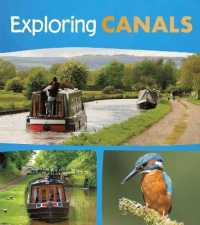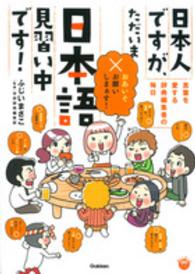内容説明
各種債券の引受・消化の構造から将来の国債管理について提言。明治時代の国債引受シ団の形成事情を調べ、大正から昭和戦間期、および近年における各種の債券の流通市場において弱度あるいは準強度の効率性が成立していたかを計量経済学の手法を用いて検証する。
目次
戦前債券市場の推移
戦前国債市場構造の分析―月次データによる弱度効率性のテスト
日次データによる戦前国債市場構造の分析(弱点の効率性のテスト;イベント・スタディ)
戦前金融債市場構造の分析
戦前地方債市場構造の分析
戦後債券市場の変遷
1950年代以降の電電債市場構造の分析
戦後金融債市場構造の分析
縁故地方債市場構造の分析
国債と金利自由化
1970年代以降の国債市場構造の分析
まとめと政策的含意
著者等紹介
釜江廣志[カマエヒロシ]
1948年兵庫県生まれ。1970年京都大学経済学部卒業。1975年一橋大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退学。小樽商科大学講師、山口大学助教授、一橋大学教授を経て、東京経済大学経済学部教授、一橋大学名誉教授、博士(商学、一橋大学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。