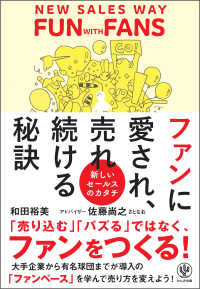内容説明
「海水を飲むな」―世界の定説を信じ、渇きに負けて死んでいった多くの遭難漂流者たちを救いたい。この思いにとりつかれた著者を四回目の漂流実験にかりたてた。1975年10月7日、手製のゴムボート《ヘノカッパ2世号》は、沖縄へ向けサイパン島を発った。とちゅう、台風にあうなど、太平洋上を漂流すること50日、彼は無事に帰ってきた。著者自らの生命を賭けた、感動の冒険記。
目次
第4次漂流実験
なぜ漂流実験をやるのか
漂流実験の足跡
第4次漂流実験の目的
りこうな魚
漂流中の生活
台風20号との闘い
生還
世界の定説への挑戦
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
あんこ
2
海外の漂流記も何冊か読んだけれども、日本人が書いたものはすごく身近に感じるし、心の深いところに響いてくる気がする。海難事故で漂流時、一定期間、一定量なら海水を飲んでも大丈夫(A・ボンバールの説)らしい。これを実証するために昭和50年に実験漂流したのが著者の記録だ。(真水2+海水1)の混合液にすると生理食塩水と同じ濃度になり、長期の飲用が可能になるそう。マグロ漁船に見習いとして乗り釣りの技術を習得。ボートを自作。すごいバイタリティの著者。太平洋ひとりぼっちの孤独から大声でちゃんちきおけさを歌ったという。2016/02/10
圭
2
【再読】海難事故時、海水を一定量、飲料とする事が可能であるというアラン・ボンバールの海水引用理論の検証のため、数々の実験を行った著者の記録。その実験によれば、真水+海水の混合液(2:1)は医療注射液のリンゲル液と同様の濃さであり、短期間かつ一定量以下なら問題なく、その旨の医学博士の見解も書かれている。何日でも救助を待てる十分な食料と真水があるなら、定説通り、海水を飲まない方が良いが、救助がいつ来るかわからず、真水の量が不足している状況なら、延命日数を延ばすため海水を希釈するのは確かに一つの選択肢だと思う。2013/11/30
rincororin09
1
漂流モノが好きでいろいろ読んでいるが、これは自らの意思で漂流したお話し。実験であれ遭難であれ、生き残るためには強い意志が必要だと思った。2019/12/15
ai
0
この本も私の価値観にすごく関わっている大切なもの。2009/07/25
-

- 電子書籍
- GetNavi2020年2月号