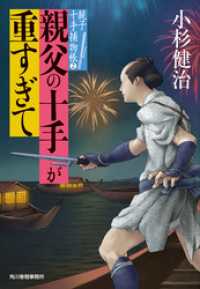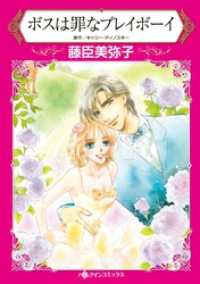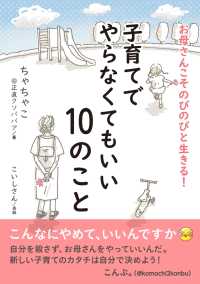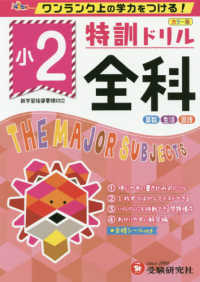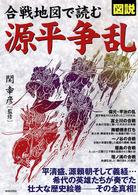内容説明
ホットグループとは、義務感あるいは帰属意識ではなく、仕事そのものによって動機付けられた自生的かつ随時的の生きた存在である。仕事が終われば解散するというミッション中心の随時的グループである。複雑なるものを単純化し、予期せぬものに対処するうえで最適な組織形態というべきである。本書はホットグループが何をできるかだけでなく、それが必要とするリーダー、いくつかの問題についても述べている。
目次
第1部 最強集団の知られざる生態(奇跡の集団ホットグループ;希望の種を蒔く;戦略はミッションに従う ほか)
第2部 成果を挙げる「熱いやつら」の育て方(いかにして「やつら」の魂に火を付けるか?―リーダーたる者の条件;「人」の共鳴からスタートする―指揮者型リーダーのための一二の心得;野性の叡智を躍動させる―パトロン型リーダーのための一〇の心得)
第3部 「破壊的」な成果を生む秘策(多様なものに自由を与える;親組織とのトラブルを回避する方法;「想定外」の動きで大組織を変革する方法 ほか)
著者等紹介
リップマンブルーメン,ジーン[リップマンブルーメン,ジーン][Lipman‐Blumen,Jean]
クレアモント大学院大学教授。ウェルズリー大学卒業、ハーバード大学大学院にて博士号を取得後、行動科学高等研究所(カリフォルニア州パロアルト)フェローを経て、1982年より、クレアモント大学院大学P.F.ドラッカー経営大学院にてリーダーシップ論主任教授。専門は、リーダーシップ、マネジメント、公共政策、危機管理。全米教育協議会次長、大統領府政策スタッフを経験。現在教鞭をとるほか、連邦政府、州政府、企業、NPOを対象にコンサルティングに従事。マネジメントの父とされるクレアモント大学院大学のピーター・F・ドラッカー教授にきわめて近い。最近著『有害リーダーの魅力―なぜ従うのか、いかに克服するか』は、『ファースト・カンパニー』誌より、2004年度優秀ビジネス書ベスト10に選ばれる。『結合力―相互依存社会におけるリーダーシップ』は、ピューリッツァー賞にノミネート。『ホットグループ』は、全米出版社協会学術専門書部門ベストブック・オブ・ザ・イヤーに選ばれる。著書6冊、論文80本以上
レヴィット,ハロルド・J.[レヴィット,ハロルドJ.][Leavitt,Harold J.]
スタンフォード大学ビジネススクール教授。ハーバード大学卒業、MIT(マサチューセッツ工科大学)大学院より博士号取得。シカゴ大学、カーネギー・メロン大学、ロンドン・ビジネススクール、INSEADを経て、スタンフォード大学ビジネススクール教授。専門は、スモール・グループ、コミュニケーション・ネットワーク、マネジメント教育、思考方法、技術のマネジメント。スタンフォード大学ビジネススクールのエグゼクティブ・コース、シンガポールでのエグゼクティブ・コースの責任者、タイのマネジメント教育機関の顧問を務めてきた。教鞭をとるほか、ベル研究所、フォード財団、カイザー・パーマネンテ、ヴァリアン・アソシエイツ、ストレート・タイムズのコンサルティングに従事。著書『マネジメント心理学』は5版を数え、18カ国語に翻訳されている。『ハーバード・ビジネス・レビュー』『アドミニストラティブ・サイエンス・クォータリー』『マネジメント・サイエンス』等への寄稿多数
上田惇生[ウエダアツオ]
ものつくり大学名誉教授、立命館大学客員教授、ドラッカー学会代表。1938年埼玉県生まれ。64年慶応義塾大学経済学部卒。経団連会長秘書、国際経済部次長、広報部長、ものつくり大学教授(マネジメント、社会論)を経て、同大学名誉教授。立命館大学客員教授。ドラッカーの経営思想について執筆、講演多数。2003年より『週刊ダイヤモンド』にて「経営学の巨人の金言・至言―3分間ドラッカー」を連載中。ドラッカー自身からもっとも親しい友人、日本での分身とされてきた。渋沢栄一賞選考委員、埼玉ちゃれんじ企業経営者選考委員会代表。ドラッカー経営思想の普及によりベスト・リスクマネジャー・オブ・ザ・イヤー2001(リスクマネジメント協会)受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mura_ユル活動
Shinya
popon
malty