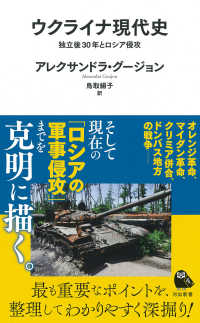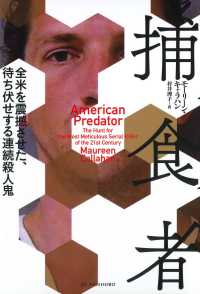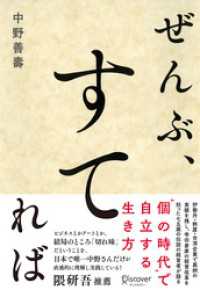出版社内容情報
経済論壇および経済政策の現場で活躍する硬派エコノミストが、世界と日本の経済論戦の意味を読み解き、その大胆な見取り図を描く。
内容説明
緊縮vs.反緊縮終わりなき闘い。ケインズ主義、MMTの台頭、そしてパンデミック対策に至る論戦の見取り図を鮮やかに描く。
目次
第1章 いまなぜ反緊縮か
第2章 緊縮と反緊縮―交錯する思想と理論
第3章 変転するケインズ主義の政策戦略―ケインズ主義1から2へ
第4章 保守派の転成―緊縮主義からオルトライト・ケインズ主義へ
第5章 躍り出た現代貨幣理論(MMT)
第6章 政府債務の将来負担と財政の維持可能性
第7章 コロナ禍に対応する経済政策
第8章 ケインズ主義3―反緊縮のための財政金融統合政策
著者等紹介
野口旭[ノグチアサヒ]
1958年生まれ。東京大学経済学部卒業。同大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退学。専修大学経済学部助教授・教授等を歴任。博士(経済学・中央大学)。著書に『昭和恐慌の研究』(共著、東洋経済新報社、2004年。日経・経済図書文化賞受賞)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
hurosinki
6
現在著者は日銀審議委員。硬派という触れ込みだが、ややこしいのはMMT批判の第5章ぐらい?珍奇な内容はあまりない…というか筆者の主張する政策(財政拡張とそれを支える金融緩和)はアベノミクスと大した違いはない(本書で度々肯定的に言及される)。長期的な低インフレ・低金利を論拠に、恒常的な需要不足が起きていると述べるサマーズの長期停滞論を引き、金融緩和と財政拡張による需要のマクロ的拡大の必要性を説く。需要不足の要因が気になるが、終盤の議論によれば社会の生産力が際限なく拡大することで必然的に起きるとのこと(p3902022/01/11
Go Extreme
1
いまなぜ反緊縮か 緊縮と反緊縮―交錯する思想と理論 変転するケインズ主義の政策戦略―ケインズ主義1から2へ 保守派の転成―緊縮主義からオルトライト・ケインズ主義へ 躍り出た現代貨幣理論(MMT) 政府債務の将来負担と財政の維持可能性 コロナ禍に対応する経済政策 ケインズ主義3―反緊縮のための財政金融統合政策2021/09/06
えだ
0
反緊縮的な言説を怪しげなMMTと一緒くたにし、色眼鏡で見てしまっていたけど、要するにそれは(良い意味で)ケインズ主義の展開版にすぎないのであって、さらにそれは新奇で未実施の提案というわけでもなく、実はいま世界各国がマクロ経済政策として進めている現実に追いつきそれらを読み解くために必要な知識ですらあるのだった、という気付き。 また、MMTとは異なり、決して財政拡大を無条件で肯定しているわけではない、という点も重要だろう。(cf.ラーナー・サミュエルソン命題)2021/12/04