出版社内容情報
男子高校生の実に1割以上が所属し、高視聴率を叩き出す高校野球。人気の秘密を経済学的視点から分析し、汗と涙の裏側を探る。高校野球は「重要無形文化財」!
高校球児は「特別天然記念物」!
男子高校生の10人に1人が野球部
平日昼間に視聴率20%超
超人気コンテンツには強い「仕掛け」があった!
汗と涙の裏側にある特殊構造に迫る
◎高校生が野球部に入ると年間いくらかかる?
◎学校数が多い都道府県は甲子園でも強い?
◎高校野球の審判になるには?
◎高校野球だけ特待生が問題視されるのはなぜ?
◎高野連が不祥事にあれほど厳しいのはなぜ?
◎甲子園の外野席が無料なのはなぜ?
他のスポーツと違うのには理由があった!
野球伝来からの歴史を辿りながら、大人たちがどのように甲子園という舞台装置を演出してきたのかを分析する。
「本書の目的は、高校スポーツの一つに過ぎない高校野球が100年の長きにわたって続いてきた理由について、経済学的思考法を用いて体系的に説明することである。」(本書「はじめに」より)
はじめに
第1章 野球は“非効率”なスポーツ
第2章 高校野球は“重要無形文化財”
第3章 “聖地”甲子園の謎
第4章 陰の主役・審判
第5章 沖縄の高校野球に学ぶ
第6章 高校野球の将来
おわりに
参考文献
中島 隆信[ナカジマ タカノブ]
中島 隆信(ナカジマ タカノブ)
慶應義塾大学商学部教授
1960年生まれ、83年慶應義塾大学経済学部卒業。
現在、慶應義塾大学商学部教授、博士(商学)。
著書: 『日本経済の生産性分析』(日本経済新聞社、2001年)。
『大相撲の経済学』(東洋経済新報社、2003年)。
『お寺の経済学』(東洋経済新報社、2005年)。
『オバサンの経済学』(東洋経済新報社、2007年)。
『障害者の経済学(増補改訂版)』(東洋経済新報社、2011年)。
『刑務所の経済学』(PHP研究所、2011年)。
『経済学ではこう考える』(慶應義塾大学出版会、2014年)。
『家族はなぜうまくいかないのか』(祥伝社、2014年)、他。
内容説明
高校生が野球部に入ると年間いくらかかる?学校数が多い都道府県は甲子園でも強い?高校野球の審判になるには?高校野球だけ特待生が問題視されるのはなぜ?高野連が不祥事にあれほど厳しいのはなぜ?甲子園の外野席が無料なのはなぜ?他のスポーツと違うのには理由があった!野球伝来からの歴史を辿りながら、大人たちがどのように甲子園という舞台装置を演出してきたのかを分析する。
目次
第1章 野球は“非効率”なスポーツ
第2章 高校野球は“重要無形文化財”
第3章 “聖地”甲子園の謎
第4章 陰の主役・審判
第5章 沖縄の高校野球に学ぶ
第6章 高校野球の将来
著者等紹介
中島隆信[ナカジマタカノブ]
1960年生まれ、83年慶應義塾大学経済学部卒業。現在、慶應義塾大学商学部教授、博士(商学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Willie the Wildcat
おさむ
ゲオルギオ・ハーン
きょちょ
Garfield
-
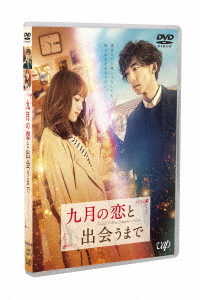
- DVD
- 九月の恋と出会うまで 豪華版







