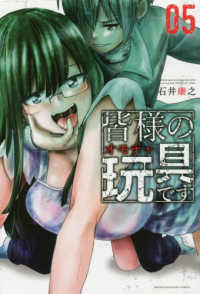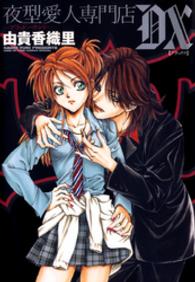出版社内容情報
長期不況の中で、労働組合は死の淵に立っている。退出・発言モデルの展開と従業員代表制経済分析など最新の研究成果を踏まえながら、労組関係の現状を解明する。
内容説明
ベア・ゼロ、リストラの嵐、組織率低下、無組合企業の増大―長期不況の中で、日本の労働組合は死の淵に立っている。「退出・発言モデル」の展開と従業員代表制の経済分析など日米欧の労働経済学の最新成果を踏まえながら、労使関係の現状をミクロ的・数量的に解明する。
目次
序章 本書の目的・内容・メッセージ
第1章 現代労使関係への新たな接近―分析枠組みの設定
第2章 日本の雇用システムと労使関係―文脈の再定義
第3章 労働組合組織率はなぜ低下したか―先行研究の批判的評価
第4章 労働組合の賃金効果と発言効果―実証分析
第5章 現代日本の労働組合と組合員の組合離れ―実証分析
第6章 無組合企業の労使関係―先行研究の批判的評価
第7章 無組合企業における発言機構、従業員参加、賃金決定―実証分析
著者等紹介
都留康[ツルツヨシ]
1954年福岡県に生まれる。1977年大阪市立大学経済学部卒業。1982年一橋大学大学院経済学研究科博士課程単位取得。1982年一橋大学経済研究所講師。1985年同助教授。1985‐87年マサチューセッツ州立大学およびオスナブルュック大学客員研究員。1990年マサチューセッツ工科大学客員研究員。1995年一橋大学経済学研究所教授、現在に至る
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Mc6ρ助
20
『たしかに、労働者の価値観やニーズが多様化し、それへの組合の対応が不十分なのはまぎれもない事実・・しかしながら、そもそもそれ以前の問題として、賃金水準や雇用の安定などの基本的労働条件に対する労働組合の取組みの評価や、 それらの方面での組合の有効性の認識は、組合員たちの間でけっして高くはないのである。そして、こうした組合への低評価が低参加に帰結しているというべきである。(p136)』労働組合の有用性の証明を組合員に対してなさなければならない状況、それ自体が労働組合の成り立ちとはそぐわない、のではなかろか。2025/01/10