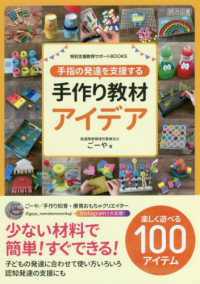出版社内容情報
●疲れたらコーヒーを飲む
●疲れたときは寝るのが一番
●甘いもので自分にごほうび
……こんなこと、していませんか? 実は疲労を取るには全部「×」な方法です。
「いつも体が重い」
「寝ても寝てもだるく、疲れがとれない」
「会社に行くだけでヘトヘトになる」
「休みの日に何をしていいかわからない。結局、一日じゅうゴロゴロしている」
「週末に寝だめをすると、休み明けはかえってぐったりしてしまう」
……あなたはこんな悩みを抱えていませんか?
「ゆっくり休みたいのに休めない」のは、日本では「休むこと」イコール「なまけてること」という考えがしみついていることにあります。疲労は熱や痛みと同じ、体からの警告です。本来は「今日は疲れているので、休みます」と言えなくてはおかしいのです。
本書では、これまで栄養や運動に比べて軽視されてきた「疲労」と「休息」について科学的な解説を加え、
・人はなぜ疲れるのか
・疲れても無理をして休まずにいると、人間の体はどうなるのか
・どんな休み方をすれば最も効果的に疲れがとれるのか
……といった疑問に答えていきます。
さらに、休養を7種類に分類し、それらを組み合わせて、自分がもっともリフレッシュできる休み方を見つける方法も伝授します。
「日本人の約8割が疲れている」というデータもあります。ただ、世界各国と比べて平均労働時間がとくに多いわけではありません。日本人は「休み下手」なのです。
本書を読んで、単に寝る、休息するといった「守りの休養」から、「攻めの休養」へ今すぐシフトしましょう!
内容説明
この本を読むと、こんなことがわかります。人はなぜ疲れるのか。疲れても無理をして休まずにいると、人間の体はどうなるのか。どんな休み方をすれば最も効果的に疲れがとれるのか。
目次
第1章 日本人の8割が疲れている(疲れている人は25年間で2割も増えた;疲労による経済損失は1.2兆円に上る ほか)
第2章 科学でわかった!疲労の正体(疲労とは何かちゃんと知っていますか?;疲労は病気につながるサインである ほか)
第3章 最高の「休養」をとる7つの戦略(「活動→疲労→休養」のサイクルから抜け出そう;日常のサイクルに「活力」を加えてみる ほか)
第4章 眠るだけでは休養にならない(睡眠は活力のカギを握る;睡眠はマルチな力をもっている ほか)
第5章 新しい「休み方」を始めよう(仕事が一段落しなくても、まず休む;これから疲れそうだから、先に休んでおく ほか)
著者等紹介
片野秀樹[カタノヒデキ]
博士(医学)、一般社団法人日本リカバリー協会代表理事。株式会社ベネクス執行役員。東海大学大学院医学研究科、東海大学健康科学部研究員、東海大学医学部研究員、日本体育大学体育学部研究員、特定国立研究開発法人理化学研究所客員研究員を経て、現在は一般財団法人博慈会老人病研究所客員研究員、一般社団法人日本未病総合研究所未病公認講師(休養学)も務める。日本リカバリー協会では、休養に関する社会の不理解解消やリテラシー向上を目指して啓発活動に取り組んでいる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
breguet4194q
旅するランナー
あすなろ@no book, no life.
Kazuo Tojo
アキ
-

- 和書
- クジラの生態