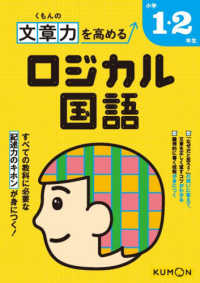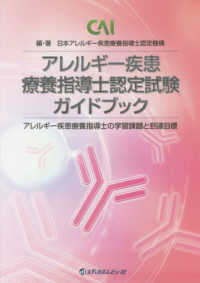出版社内容情報
本書の概要
本書では、探究的な学びの駆動力となる、「愉しさ」のある算数授業を、実践を通じて提案します。外因的な「楽しさ」と内因的な「愉しさ」。本書では、子どもの姿から「たのしさ」を見つめ直し、子どもの内面から湧き出す愉しさのある授業に焦点を当てました。正答を求めるだけの楽しさの先の、モヤモヤをスッキリさせる愉しさへ導く一冊です。
本書からわかること
愉しさが駆動する授業がわかる!
「個別最適な学び」や「?由進度学習」など、近年、学び?に焦点を当てた研究が広がっています。
他方、学びの主役である「?どもの姿」に視点を移すと、子どもたち自身が“算数の学びを愉しんでいるか”が重要であることはいうまでもないでしょう。算数・数学に没頭して愉しむことで、?どもたちは??の学びを深化させます。
本書では、【愉】と【楽】の辞書的な意味を授業場面に照らして援引し、問題が解けたという外因的な「楽しさ」と、更に学びを深めたいと湧き上がる内因的な「愉しさ」を区別しています。
学び方が多様化しても、子どもが没頭する「愉しさ」のある授業は常に欠かせない視点です。
一人ひとりの子どもが没頭する探究的な授業の姿を、本書でぜひご覧ください。
Chapter 1 算数の学びを愉しむとは?
Chapter 2 学びを愉しむ授業づくりのポイント
Chapter 3 学びを愉しむ19の姿
Chapter 4 没頭する学びを考える教師の鼎談
こんな先生におすすめ
算数の授業をよりよくしたい先生
【目次】
目次
はじめに 2
Chapter 1 算数の学びを愉しむとは?
算数の学びを愉しむとは? 8
算数の学びを愉しまない姿とは? 16
教師は算数を愉しんでいるのか? 24
1年生でも学びを愉しめる 32
愉しさが学びを深化させる 40
Chapter 2 学びを愉しむ授業創りのポイント
愉しさのきっかけは一部の子どもから 50
愉しむ授業に必要な教材開発・発問吟味 58
子どもの「気づき」をキャッチする教師の「気づき」 66
「見方・考え方」から探究へとつなげる手立て 74
愉しさに必要な子どもの活動 82
Chapter 3 学びを愉しむ19の姿 91
「また同じ」で愉しむ(帰納的な考え方) 92
「次はこうなる」で愉しむ(類推的な考え方) 98
「いつでもできるよ」で愉しむ(一般化の考え方) 104
「でもさあ」で愉しむ(特殊化の考え方) 110
「だから」「分かった!」で愉しむ(演繹的な考え方) 116
「きまりがある」で愉しむ(関数の考え方) 122
「だったら」で愉しむ(発展的な考え方) 128
「これって前の……」で愉しむ(統合的な考え方) 134
「一つだとしたら」で愉しむ(単位の考え方) 140
「もし○○にしたら」を愉しむ(単純化の考え) 146
「例えば○○だとしたら」で愉しむ(概算の考え方) 152
「もし○○だとしたら」で愉しむ(置換の考え方) 158
「○○をたしたら」で愉しむ(補完の考え方) 164
「前の○○と似ている」を愉しむ(系統的な考え方) 170
「○○にもあるよ」を愉しむ(日常化の考え方) 176
「また違ったぞ」を愉しむ(失敗や試行錯誤) 182
「だからさあ」を愉しむ(説得したくなる説明) 188
「わあきれい」を愉しむ(美しさへの感動) 194
「そんな考え方があるんだ」を愉しむ(新たな発想を愉しむ) 200
Chapter 4 没頭する学びを考える教師の鼎談
「子どもが没頭する授業とは」 208
内容説明
没頭する学びの19の姿。正答を求めるだけの楽しさの先のモヤモヤをスッキリさせる愉しさへ。
目次
1 算数の学びを愉しむとは?(算数の学びを愉しむとは何か?;算数を愉しまない姿とは? ほか)
2 学びを愉しむ授業づくりのポイント(愉しむ授業に必要な教材開発・発問吟味;子どもの「気づき」をキャッチする教師の「気づき」 ほか)
3 学びを愉しむ19の姿(「また同じ」で愉しむ(帰納的な考え方)
「次はこうなる」で愉しむ(類推的な考え方) ほか)
4 没頭する学びを考える教師の座談会(「子どもが没頭する授業とは?」)
-

- 電子書籍
- 今日からヒットマン 13 ヒューコミッ…
-
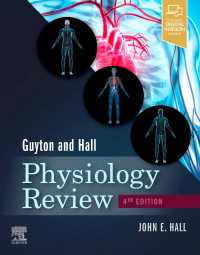
- 洋書電子書籍
- ガイトン&ホール生理学レビュー(第4版…