出版社内容情報
「理科DX」がもたらすものは、子ども主体の学び
本書の概要
1人1台端末が普及し、ここ数年で学習の形は大きく変わりました。デジタル技術を活用した教育の変革は「教育DX」と呼ばれますが、本書では理科授業におけるDXを「理科DX」と名付けます。理科DXは単なるデジタルツールの活用にとどまらず、理科の学びを深め、子ども主体の授業を大きく促進する切り札となるでしょう。初歩的な内容からNEXT GIGAの展望まで、アイデアあふれる24例の実践を通して、理科DXの現在とこれからを知ることのできる一冊です。
本書からわかること
「理科DX」はこれまでのICT活用と何が違う?
GIGAスクール構想による1人1台端末の普及は、学校教育におけるICT活用を一気に加速させました。理科の授業でも、多くの先生がICTを利活用していることでしょう。学習の利便性や効率性が上がり、個別最適な学びや協働的な学びの充実にも大きく寄与しています。では、これらのICT活用と「理科DX」は何が違うのでしょうか? 本書で重視しているのは、「子どもたちが主体性を発揮する理科授業」という視点です。デジタル技術の利活用が、指導者側の補完的な側面だけではなく、学習者側の主体的な学びへの転換や加速をもたらします。理科授業の変革の主人公は、あくまで子ども自身なのです。
アイデアあふれる24の実践事例
本書では、24の実践事例を以下のカテゴリーに分けて紹介しています。
・観察、実験を豊かにする理科DXアイデア
・協働が加速する理科DXアイデア
・学びを深める理科DXアイデア
・未来を拓く理科DXアイデア
デジタルワークシート、撮影した写真や動画の編集、3Dコンテンツ、AR、オンライン掲示板、プログラミング、シミュレーションソフト、生成AIなどを取り入れた実践からは、デジタルツールを手にした子どもたちが、教師の想定をいともたやすく超えていく姿を感じ取ることができるでしょう。また、PBLやブレンディッド・ラーニングなどの学習方法を取り入れた実践も紹介しています。
月刊誌『理科の教育』の人気連載を書籍化
本書は、一般社団法人日本理科教育学会の月刊誌『理科の教育』の人気連載「Let's Try!理科授業のDX」が元になっています。様々な先進的・意欲的な実践を掲載し、多くの支持を集めてきました。書籍化にあたって、大幅な見直しをするとともに、多くの書き下ろしも加え、さらなる内容の充実を図りました。連載ファンのみなさまにも、新たな気付きやアイデアを提供できる一冊です。
こんな先生におすすめ
・子どもたちの主体性が高まる理科授業をしたいと思っている先生
・デジタル技術を理科授業に活用したいと思っている先生
・これからの時代の授業デザインについて考えたい先生
【目次】
はじめに
序章 子どもが主体性を発揮する理科DX
第1章 理科DXの可能性
1 学習指導要領でも重視されている理科DX
2 理科DX 未来予想図
3 学校も地域も変わる理科DX
コラム1 学ぶ、遊ぶ、真似ぶ、超える DXな子どもたち
第2章 理科DX はじめの一歩
1 ノートやワークシートをデジタルに!
小学6年「電気の利用」:単元を通して、デジタルワークシートを活用する
2 「可視化」と「共有」で授業が変わる!
小学3年「身の回りの生物」:昆虫を比較して、体のつくりについて考える
3 撮影した写真や動画を活用しよう
小学6年「燃焼の仕組み」:他の班の記録との違いに気付き、実物に再注目する
4 見えない夜空をシミュレーションしよう
小学4年「月と星」:星の集まりは時刻によって見える位置が変わることを実感する
5 3Dコンテンツで疑似体験してみよう
小学3年「身の回りの生物」:バッタとチョウを比べる/「ナゾの虫」について考える
コラム2 理科のコンテンツをフォルダごと共有
第3章 観察、実験を豊かにする理科DXアイデア
1 子どもがワクワク! 「ネイチャーフォトビンゴ」
小学4年「季節と生物」:ネイチャーフォトビンゴを作ってみる
2 動画を並べて比較しよう
小学5年「物の溶け方」:物が水に溶ける量を調べる
3 ARの強みを生かしたリッチな観察
中学2年「動物の体のつくりと働き」:どのような仕組みで腕を曲げ伸ばしできるのか
4 校庭の樹木を同定して、詳しく調べてみよう
小学3年 総合的な学習の時間:身近な樹木について調べる
5 「誤差」を実感! データを吟味しよう
小学5年「振り子の運動」:シミュレーションソフトを活用して誤差を実感する
コラム3 いきものコレクションアプリ「Biome」
第4章 協働が加速する理科DXアイデア
1 フォルダ共有でいつでも使えるみんなの記録
小学4年「季節と生物」:春の動植物の様子を撮影し、フォームを使って提出する
2 異学年同士でも協働的に観察
小学校異学年:異学年グループで校内の生き物調査をする
3 教室にSNSを!クラウド活用で授業をアップデート
小学5年「物の溶け方」:水と食塩水を見分ける方法を考える
4 子どもの発見を共有する「Rikastagram」
小学校全学年:1年間継続して行った「Rikastagram」
5 データで協働するよさを味わおう
小学6年「てこの規則性」:「目盛り×おもりの数」ではなく「支点からの距離×おもりの重さ」
内容説明
「理科×ICT最前線」がもたらすものは主体的に学ぶ子どもの姿。「可視化」と「共有」で授業が変わる!月刊誌『理科の教育』の人気連載「Let’s Try!理科授業のDX」を書籍化。「いつでも、どこでも、誰とでも」使えるデジタルツールが、子どもの自由な発想と主体性を引き出す!
目次
序章 子どもが主体性を発揮する理科DX
第1章 理科DXの可能性
第2章 理科DX はじめの一歩
第3章 観察、実験を豊かにする理科DXアイデア
第4章 協働が加速する理科DXアイデア
第5章 学びを深める理科DXアイデア
第6章 未来を拓く理科DXアイデア
第7章 Q&A
著者等紹介
吉金佳能[ヨシカネカノウ]
宝仙学園小学校教諭。1983年茨城県生まれ。同校2代目校長であり、理科教育の大家である栗山重氏の「教えてはいけない、学ばせてもいけない、学びを支援することが教育だ」に挑戦し、子どもが夢中になる学びを追究する実践家。2018年、「未来の学び」をテーマとした私立小学校のコミュニティ「192Cafe(いちきゅうにカフェ)」を立ち上げる
横田直人[ヨコタナオト]
姫路市教育委員会指導主事。1984年兵庫県姫路市生まれ。小学校教員時代は、市内の教育研究会における授業実践をはじめ、初等理科教育の研究を重ね、現在は指導主事として市内の理科授業実践における指導助言を行っている。また、ソニー科学教育研究会兵庫支部の研修リーダーとして、「自然とひたむきに関わる子」「自然に感動するとともに、人間(自分自身)のもつ力に感動する子」の育成を目指して日々共同研究を行っている
下吉美香[シモヨシミカ]
神戸市立雲中小学校主幹教諭。1977年兵庫県神戸市生まれ。2005年より神戸市公立小学校に勤務。2006年からの9年間は神戸大学附属小学校に勤務し、子どもたちの可能性に衝撃を受け、以後、理科の授業研究に邁進中。2019~2020年には、評価規準、評価方法等の工夫改善に関する調査研究委員を経験。2021年全小理兵庫大会にて研究提案。日本理科教育学会『理科の教育』編集委員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
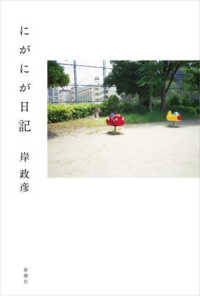
- 和書
- にがにが日記






