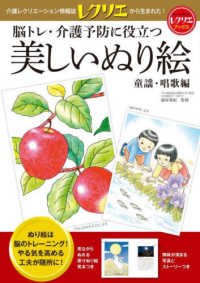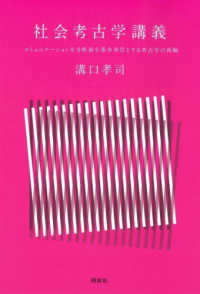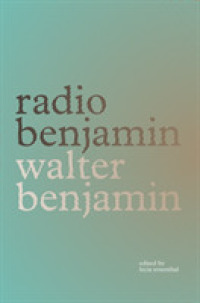出版社内容情報
国語の“しくみ”と“つながり”をイラストと図解で解説!
〈本書の概要〉
小学校教員の中で、国語に対する苦手意識をもっている割合は比較的高いと言われています。その要因は、教えるべき指導事項が小学校学習指導要領国語解説編で明示されているものの、用語の定義や解説は十分ではない(ざっくり理解できているつもりでも、実は定義が曖昧で指導に自信がもてない・・・)からのようです。その結果、教科書教材でそれらを具体化してどこまで教えればよいかなどについて指導の難しさを感じているのです。
そこで、小学校国語のトリセツとして、小学校国語の指導事項を図解・イラストとして示し、ビジュアル化・構造化した本書により、全国の先生方の明日の国語授業をサポートします。
〈本書からわかること〉
・指導事項の系統性
国語科は言葉の教育です。言葉は「国語」を学ぶ以前から私たちの日常に当たり前にありました。だからこそ、それを対象として学ぶ際には、教師がその力を系統的に捉えて指導することが大切になります。学習指導要領に示されている指導事項を、教科書教材でどう具体化させていくのかが重要なのです。そのためにも螺旋的・反復的に示されている指導事項の「しくみ」や「つながり」をあらためて理解することが必要です。
・授業づくりにおける喫緊の課題も解説
令和の日本型学校教育と言われるいわゆる「個別最適な学び・協働的な学び」、指導と評価の一体化、ICTを活用した国語授業づくりまで、単元や領域レベルでその具体の有り様を解説します。
・国語科の授業づくりにおける「よくある悩み」にも回答
「物語の読みでは、教師の読みをどこまで伝えてよいの?」「語彙指導の方法は?」「すべての子どもが読書感想文を書けるようになる指導方法は?」「話し合いを充実させるには?」など、授業づくりにおけるお悩みも回答しています。
・小学校国語科の用語解説付き
巻末付録として、小学校学習指導要領解説国語編に示されている、目標、指導事項、言語活動例の用語解説を掲載しています。知っているようで知らなかった用語の意味や定義を知ることができ、ここだけでも必見の内容です。
〈こんな先生におすすめ〉
・国語の授業づくりに苦手意識をもっている先生
・もっと系統的に「言葉の力」を育てたいと考えている先生
・国語授業をもっと楽しみたい先生
内容説明
国語の“しくみ”と“つながり”が見えると授業づくりはもっと楽しくなる!資質・能力の三つの柱。個別最適な学び・協働的な学び。指導と評価の一体化。44の重要なキーワードと10の疑問に図解で答えます!学習指導要領の目標・指導事項・言語活動例の用語解説(定義)も掲載。
目次
第1章 令和の日本型学校教育が展望する国語科の学び
第2章 国語科の“知識及び技能”
第3章 国語科の“思考力、判断力、表現力等”
第4章 国語科における指導と評価の一体化
第5章 ICTを活用した国語科の授業づくり
第6章 国語科の授業づくり Q&A
著者等紹介
樺山敏郎[カバヤマトシロウ]
大妻女子大学 教授。早稲田大学大学院教育学研究科卒(教育学修士)。鹿児島県内公立小学校教諭、教頭、教育委員会指導主事を歴任後、2006年度から2014年度まで文部科学省国立教育政策研究所学力調査(兼)教育課程調査官を務める。2015年度より現大学へ。2022年度より現職。教育出版小学校国語・中学校国語教科書編集委員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。