出版社内容情報
評価規準の設定方法の具体を実践から学ぶ
本書の概要
田村学(國學院大學教授)の『学習評価』(東洋館出版社)では、具体的な学習活動に応じた評価規準の設定方法を明確に示しました。その手順を実際に反映しベースとしながら、子どもの豊かな見取りと、質の高い授業を実現した選りすぐりの10実践(生活科・総合的な学習の時間各5本、実践者:「柴胡の会」)を掲載。編著者の田村学による、学習評価の考え方、各事例への解説とともに、これからの生活・総合の具体的な授業づくりがよくわかります。
本書からわかること
田村学先生による生活・総合の評価方法の解説
学習評価は、教育課程にも、子供自身にも、地域や保護者にとっても機能すべき重要な行為です。つまり、誰もが分かりやすいものであること、複雑ではなく簡便であること、個人や実施者によって違いが生まれるのではなく安定的であることなどが求めらます。本書ではまず、『学習評価』(東洋館出版社、2021年刊行)で整理した、妥当性と信頼性を備えた学習評価の設定方法を、田村学先生の解説でいまいちど確認します。
評価規準の明確な設定で、豊かな見取りと質の高い授業を!
令和5年度日本生活科・総合的学習教育学会全国大会の開催地である、神奈川県相模原市の公立学校の教員を中心とした研究会「柴胡の会」による実践10本を掲載します。どれも、評価規準の明確な設定により、豊かな子ども見取りと、資質・能力の育成を実現した授業です。末尾には、田村学先生の解説で、どこがポイントであるかが述べられています。
こんな人におすすめ
生活・総合の質の高い授業を目指す先生がた。また、生活・総合以外にも、評価の設定の具体的な方法や子どもたちの事実から見取り、資質・能力の育成を目指す授業づくりに課題意識のある先生がたに、おすすめです。
内容説明
評価規準の明確な設定がもたらす子どもの豊かな見取りと質の高い授業を実現した10実践を掲載。評価規準設定の方法論とそれを具現化した実践で、生活・総合の授業づくりがよく分かる!
目次
第1章 資質・能力を明確にする知識の構造化(学習指導要領の改訂と学習評価;「知識の構造化」との関係;「主体的・対話的で深い学び」「知識の構造化」再考 ほか)
第2章 具体の学習活動に応じた評価規準の設定方法(評価規準の設定;評価規準の表現様式;「知識・技能」の観点に関する評価 ほか)
第3章 資質・能力の育成と学習評価 実践編(生活科 評価規準の設定の手順;総合的な学習の時間 評価規準の設定の手順)
著者等紹介
田村学[タムラマナブ]
國學院大學人間開発学部初等教育学科教授(文部科学省視学委員)。新潟県公立小学校教諭、新潟県上越市立大手町小学校教諭、上越教育大学附属小学校教諭、新潟県柏崎市教育委員会指導主事を経て、文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官・国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官。文部科学省初等中等教育局視学館として学習指導要領作成に携わる。平成29年4月より現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
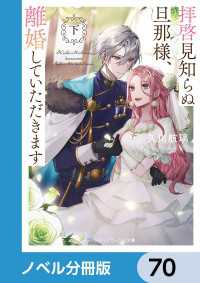
- 電子書籍
- 拝啓見知らぬ旦那様、離婚していただきま…






