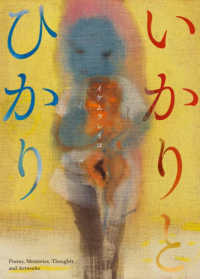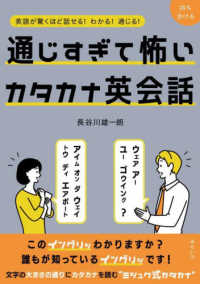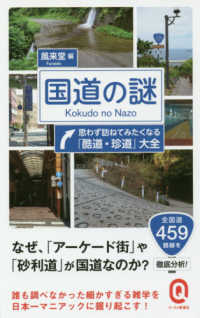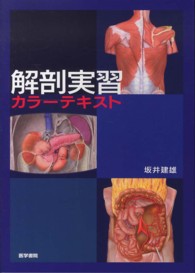内容説明
教師が子どもとつながる、子どもと子どもをつなげる。理論と方法論をつなぎすべての子どもをインクルードする学級経営を提案!子どもが社会で生きていくために必要な「安心できる人間関係」をつくる。
目次
第1章 学級経営とは、適切な「つながり」を育むこと(学校教育が育てるべき人とは;今、求められる学級経営とは;学級経営を支える教師の専門性とは ほか)
第2章 つながりをつくる10のしかけ(「つながりをつくる10のしかけ」とは?;「ミカタ」をみがく;「ココロ」をかさねる ほか)
第3章 「つながりのある学級」をつくる一年間(一年間の道すじを見通すことの大切さ;形成・介入期(四月)
衝突・一次成長期(五月~七月) ほか)
著者等紹介
上條大志[カミジョウマサシ]
小田原市立足柄小学校総括教諭。教育相談(特別支援教育)コーディネーター。日本授業UD学会湘南支部副支部長。星槎大学大学院教育学研究科修了。修士(教育)。星槎大学客員研究員。特別支援教育士。神奈川県優秀授業実践教員表彰。主な研究分野として、通常学級におけるインクルーシブ教育、特別支援教育の視点からの学級経営など。校内研修や講座等で講師を務める。所属学会等として、日本授業UD学会、日本LD学会、日本学級経営学会、発達性dyscalculia研究会、小田原支援教育研究会ほか(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
あやか
0
★★★☆☆ 人は何かを挑戦するとき「失敗しても大丈夫だ」と感じさせてくれるものや信頼できる人がいるから挑戦できる。子育てで大切なのは大人が子どもの喜びも悲しみもすべての感情を共感すること。自分の存在価値は、他者に対してどれだけ自分が貢献できているかにより確認できる。ちょっとしたことでも「ありがとう」と言われる他者貢献体験の積み重ねが大事。自分が担任して何とかするという考え方だけではなく、どの教師が担任しても、その子が落ち着いて学校生活を送れるようにする必要がある。2学期の目標は子どもと子どもをつなげる。2024/07/29