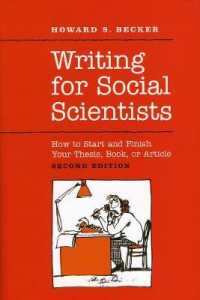目次
1 国語科における「書くこと」
2 「書くこと」は嫌われている
3 「第三の書く」の展開
4 書くことの多角化
5 「第三の書く」と発問
6 文学教材における「第三の書く」
7 説明的文章における「第三の書く」
8 伝記教材における「第三の書く」
著者等紹介
青木幹勇[アオキミキユウ]
1908年高知県に生まれる。宮崎県師範学校専攻科卒業。宮崎県師範学校、東京高等師範学校、東京教育大学等の附属小学校及び文教大学に勤務。著書に『青木幹勇授業技術集成』(全5巻、明治図書出版、1989年)他多数。1953年より25年間にわたりNHK「ラジオ国語教室」放送の担当、授業研究サークル「青玄会」代表、月刊誌『国語教室』(非売品)編集・発行責任者等も務める。2001年逝去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。